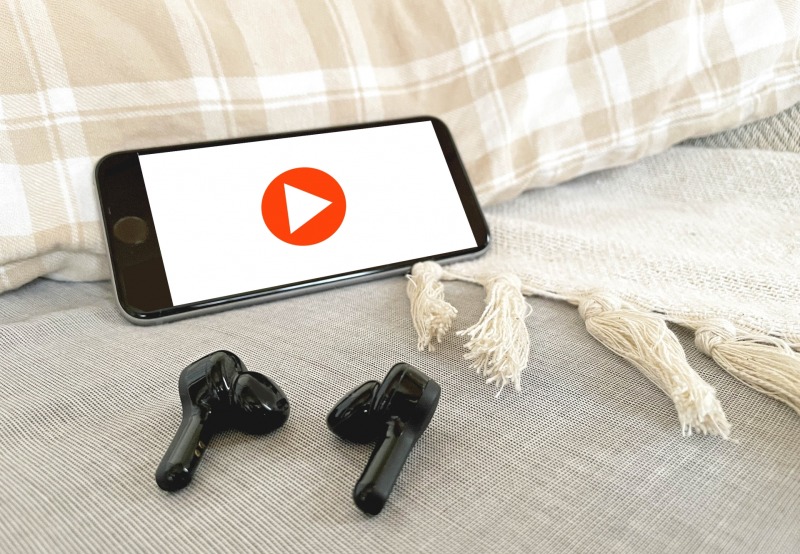「自分のYouTubeチャンネルをもっと多くの人に知ってもらうために、SNSを上手く活用できないだろうか」という悩みはありませんか?
多くのクリエイターや企業が直面しているのが、コンテンツの露出不足と、効果的なマーケティング戦略が取れていないことです。
もちろん、YouTubeだけでも成果を目指すことは可能ですが、SNSを組み合わせることでその可能性をさらに広げることが可能です。
しかし、SNSを運用する際は、不適切な投稿による炎上リスクや、投稿内容が各SNSの特性に合っていないと効果を発揮できないという注意点も存在します。
そこでこの記事では、YouTubeとSNSを組み合わせて運用するメリットと、相性のいいSNSの選び方、そして実際に運用する際の注意点を解説します。
「自分のチャンネルを成長させたい」「SNSの活用法を知りたい」という方はぜひ最後までご一読ください。
YouTubeとSNSを組み合わせて運用するメリット

YouTubeとSNSを組み合わせて運用するメリットは、以下の4つが挙げられます。
- 宣伝効果が期待できる
- クロスプロモーションが可能になる
- コミュニケーションの促進に繋がる
- 既存のコンテンツを活用できる
それぞれの利点は、マーケティング戦略を最適化し、多角的なアプローチによって視聴者との結びつきを強化できるということです。
結果として、効果的なブランディングと収益化に繋がります。
それでは、各メリットについて以下で詳しく見ていきましょう。
メリット①:宣伝効果が期待できる
YouTubeとSNSの組み合わせによる運用では、高い宣伝効果が期待できます。
YouTubeの動画コンテンツをX(旧:Twitter)やInstagramといった他のSNSに共有することで、それぞれのプラットフォーム特有のユーザーにアプローチできるためです。
例えば、魅力的なサムネイルやメッセージ、動画のURLを投稿することで、その動画に興味を持ったユーザーをYouTubeチャンネルに誘導できます。
その結果、異なるターゲット層にもリーチ可能であり、YouTubeでは定着していない新しい視聴者層にもアプローチが可能です。
また、より広い範囲での拡散により、チャンネル登録者数の増加や収益化の促進にもつながります。
メリット②:クロスプロモーションが可能になる
複数のプラットフォームを横断したクロスプロモーションにより、コンテンツをより多くの人に届けることができます。
異なるプラットフォームでファンを獲得し、ブランドの認知度を全方位から高めることが可能です。
例えば店舗を経営している場合、顧客相談やコミュニケーションをInstagramで行い、詳細な情報を動画で伝える活動をYouTubeで行うといった使い分けが可能です。
このように、各プラットフォームの特性を活かしたコンテンツを作ることで、あらゆる角度からブランドや製品の魅力を発信することが可能です。
コンテンツの相乗効果によって視聴者のエンゲージメントを高め、最終的には売上増加にも繋がる可能性があります。
なお、クロスプロモーションを行う際は、各プラットフォームの特性をうまく利用し、統一感を持ってブランドメッセージを伝えることがポイントです。
メリット③:コミュニケーションの促進に繋がる
YouTubeは動画投稿と閲覧をメインとしたプラットフォームであり、即時的なコミュニケーションを行うには限界があります。
そこでX(旧:Twitter)などの他のSNSと組み合わせることで、視聴者との直接的なコミュニケーションが促進されるメリットもあります。
視聴者とのより深い繋がりを築くことで、ロイヤリティの高いファンの獲得にも期待できるでしょう。
例えば、YouTubeで投稿した動画に対してXで意見・感想を求めることで。コミュニティ内でのブランドや製品に対する積極的なフィードバックが得られやすくなります。
メリット④:既存のコンテンツを活用できる
YouTubeに投稿した長尺の動画コンテンツは、YouTube Shortsで活用できることはもちろん、TikTok、Instagramといった他のSNSの短尺動画や画像としても再活用できます。
コンテンツを再活用する際は、各SNSの利用者が好むコンテンツ形式に合わせることで、より多くの視聴者にリーチできます。
動画のハイライトやキーポイントを抽出し、短い動画として再構築するのも良いでしょう。
特に、TikTokとYouTubeはアルゴリズムの仕組みが似ているため、両プラットフォームでの成功につながるケースもあります。
これによって、コンテンツ制作の効率を高めるとともに、同じコンテンツでも異なる視聴者層にアプローチが可能です。
こうしたYouTube以外のプラットフォームでの露出を意識することで、新たな流入源にもなります。
YouTubeと相性のいいSNS

YouTubeと特に相性のいいSNSは、以下の4つです。
- X(旧Twitter)
- TikTok
- LINE
下記にて、各SNSでの効果的な活用方法について詳しく確認していきましょう。
相性のいいSNS①:X(旧Twitter)
YouTubeコンテンツの拡散には、X(旧Twitter)が極めて有効です。
YouTube動画のリンクをツイートすることで、瞬時にフォロワーへと情報が届き、動画へのアクセスが促されます。
また、リポストや「いいね」といった機能によって動画コンテンツのシェアも容易なため、さらなる拡散へと繋がりやすいのも特徴です。
その他のYouTubeとXの組み合わせ方の具体的な例は、次のとおりです。
- 視聴者によるフィードバックを受けるために、動画について意見を求めてみる。
- クリップ(動画の一部分)や動画のハイライトをツイートし、視聴者の関心を誘う。
- 特定のハッシュタグを使い、特定のトピックやトレンドに関連した動画として注目してもらう。
それぞれの戦略は、視聴者との安定したコミュニケーションを保ちつつ、YouTube動画に対する視聴回数や評価、登録者を増やすのに効果的です。
また、ユーザー交流が活発化するのもXを利用するメリットです。コラボ依頼やタイアップの依頼などは、ほとんどがXかInstagramのDMで行われるため、YouTubeを運用している方はX利用がおすすめです。
相性のいいSNS②:Instagram
Instagramを活用することの最大のメリットは、ストーリーで双方向のコミュニケーションが取れることです。例えば、ストーリーの質問機能で、悩みを募集して、質問に答えることで濃いファンを作ることができます。
また、InstagramはビジュアルコンテンツがメインのSNSであることで知られています。
そのため、YouTubeの動画コンテンツを視覚に訴えかけるような方法でプロモーションするのに適しています。
例えば、InstagramでのYouTube動画の活用は以下のように行えます。
- YouTubeの動画プレビュー、サムネイルやハイライトを共有することで、動画への興味を喚起し視聴を促す。
- ストーリーズにYouTube動画のプレビューをアップし、スワイプアップ機能(ストーリーズ中にリンクを挿入し、上にスワイプすると該当ページに遷移する機能)を使って本編へ誘導する。
- IGTVを活用し、長尺のYouTube動画もInstagram内で視聴できるようにする。
- ユーザーのカルーセル投稿(複数の写真やビデオを1つの投稿でスライドショー形式に見せる機能)にYouTube動画のハイライトを配置する。
このようにInstagramでYouTube動画を共有・再活用することで、動画のリーチ(到達範囲)を広げられるため、新規の視聴者獲得に繋がります。
相性のいいSNS③:TikTok
一般的に若年層ユーザーが多く、短い動画コンテンツがメインのTikTokも、YouTubeと相性のいいSNSの一つです。
YouTube動画のハイライトや視聴者の興味を引く瞬間をTikTokで共有することで、新しいチャンネル視聴者を獲得する絶好の機会が生まれます。
YouTubeコンテンツの効果的なTikTokでのシェア方法には、以下があります。
- TikTokのトレンドを取り入れた動画を投稿して、YouTube動画への興味を惹く。
- TikTokのプロフィール欄にYouTubeチャンネルへのリンクを配置し、フォロワーの誘導を図る。
- YouTubeの動画からTikTok用の短い動画を作りシェアする。
若い視聴者を獲得したい場合や、新規の視聴者層を開拓したい場合は、TikTokを活用してみるといいでしょう。
相性のいいSNS④:LINE
LINEはプライベートなコミュニケーションに特化したSNSであり、YouTube動画のパーソナライズなプロモーションを行うのに適しています。
具体的には、公式LINEアカウントを利用して最新の動画や情報を登録フォロワーに直接届けることができます。
これは、チャンネルへの熱量が高い視聴者にアプローチしたいときに高い効果を発揮するでしょう。
YouTubeコンテンツをLINEで宣伝する際の手法は、以下のとおりです。
- 公式アカウントを作成し、新しいYouTube動画をアップロードした通知を送る。
- 視聴者がすぐにアクセスできるようにニュースレターやメッセージで動画リンクを共有する。
- 特定の動画やイベント情報を公式アカウント経由で先行してファンに知らせる。
ただし、この方法は公式LINEアカウントに登録している視聴者に限定されるため、広告のメイン手段とすることはできません。
とはいえ、LINEは日本での利用率が高いため、YouTube動画の視聴者層のエンゲージメントをさらに高めたい場合はおすすめです。
YouTubeとSNSを組み合わせて運用するときの注意点

YouTubeとSNSを組み合わせて運用するときの注意点は、以下のとおりです。
- 離脱率が上がる可能性がある
- チャンネル登録に直接繋がらないこともある
- 各SNSの特性に合わせた投稿が必要になる
- 拡散性が高い分、炎上に留意する必要がある
- SNSのフォロワーが少ないと拡散力が期待できない
それぞれの注意点について、次項で具体的な説明をします。
注意点①:離脱率が上がる可能性がある
YouTubeとSNSを組み合わせた宣伝は非常に有効な手法ですが、懸念すべき点として離脱率の上昇リスクがあります。
離脱率とは視聴者が動画視聴を途中でやめる割合のことを指します。
SNSからYouTubeに遷移する際、多くはSafariなどのブラウザで動画が開かれます。
これが使用感を損ね、視聴者が動画を途中で閉じるリスクを高めてしまいます。
また、SNSは短いコンテンツが好まれます。
長いYouTube動画をそのまま投稿すると、視聴者の注意を引き続けることが難しいため、SNSに適した短い動画を作成する必要が生じるでしょう。
注意点②:チャンネル登録に直接繋がらないこともある
SNSからYouTubeに遷移させる場合、チャンネル登録に直接繋がるとは限りません。
なぜなら視聴者がブラウザを通じて動画を視聴する場合、YouTubeにログインしていない状態であることが多いためです。
その結果、チャンネルを登録することや、動画にグッドボタンをつけるハードルが上がってしまいます。
注意点③:各SNSの特性に合わせた投稿が必要になる
YouTubeのコンテンツをSNSで宣伝する際には、SNSごとの特性を理解し、それに合わせたアプローチを取ることが重要です。
SNSの特性を活かした投稿をするためには、次のアプローチが有効です。
- 各SNSで人気のフォーマットを分析し、それに沿った動画を制作する。
- ハッシュタグやキーワードを適切に使用して露出を高める。
- 視聴者からのエンゲージメント(反応)を高めるため、対話を促すための要素を取り入れる。
このように、SNSによって視聴者層、コンテンツの形式、対話性が異なることをふまえた戦略が必要です。
注意点④:拡散性が高い分、炎上に留意する必要がある
SNSの特性として、コンテンツが迅速かつ広範囲に拡散される可能性があります。
これは大きな宣伝効果となる反面、コンテンツが炎上(ネガティブな反応が大量に広がる現象)してしまうリスクもあります。
炎上のリスクを避けるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 不正確またはセンシティブな情報を避ける。
- 文化的、社会的な文脈に考慮したコンテンツを発信する。
問題が生じた際には、以下のように行動することが求められます。
- ネガティブなコメントや批判に対しては、迅速に反応する。
- 炎上時には透明性のある誠実な対応を心がける。
- 場合によっては公式の謝罪声明を発表し、対策についても共有する。
- 信頼を築くため、炎上後も定期的にフォローアップする。
このように、デリケートなテーマや確証のない情報は慎重に扱い、仮に炎上が起きてしまったら、素早く・誠実に対応することが大切です。
注意点⑤:SNSのフォロワーが少ないと拡散力が期待できない
SNSを使ってYouTube動画の宣伝を行う際には、SNSアカウントのフォロワー数も重要な要素となります。
フォロワー数が少ないとコンテンツの拡散力も低くなり、期待した宣伝効果を得ることができません。
もし宣伝のために新しくアカウントを作る場合、成長するまでに時間が必要なため、根気よく長期間にわたって管理していくことが大切です。
この場合は、以下の戦略を検討してみてください。
- コンテンツの質:高品質で価値のあるコンテンツを提供し、フォロワーを増やす。
- エンゲージメント:視聴者と積極的に会話し、コミュニティを形成する。
- インフルエンサーとのコラボレーション:フォロワー数が多いアカウントと交流する。
また、SNSでの存在感を保つためには、定期的にコンテンツをアップすることが大切です。
可能な範囲で、狙ったターゲット層に響くプロモーションを行い、自然とコンテンツを共有したくなるような関係を築きましょう。
YouTubeで成果を上げたいならSNSを活用するのがおすすめ
YouTubeでの成果を高めたいなら、SNSの活用が効果的です。
宣伝効果が期待できるだけでなく、クロスプロモーションが可能になること、コミュニケーションの促進に繋がること、コンテンツの再活用が可能になることなどさまざまなメリットがあります。
しかし、同時に注意すべき点もあるため、注意を払ったSNS運用が必要です。
YouTubeとSNSを上手く組み合わせれば、チャンネルの登録者数や再生時間をさらに伸ばすことが可能なので、ぜひ試してみてください。
YouTubeとSNSの最適な組み合わせで効果を最大化したいとお考えの方は、ぜひNOGICにご相談ください。
専門の知識を持ったメンバーが、チャンネルの状況やニーズに合わせた最適な戦略を提供いたします。
YouTube運用での成果を上げることを目指す際には、視聴者が動画をどれほど見ているのかを示す「平均視聴時間」に着目してみることがポイントです。
自社の動画コンテンツが視聴者にどれだけ見られているかを把握できるほか、チャンネルの成長戦略を練る際にも役立ちます。
一方で、しっかりと平均視聴時間を把握していない場合、YouTubeのアルゴリズムから不利な扱いを受けるリスクもあり、チャンネルの成長が妨げられる恐れもあります。
本記事では、YouTubeの平均視聴時間の重要性や確認・改善方法について解説します。
平均視聴時間は、自分のYouTubeチャンネルを伸ばすのに重要な指標なので、ぜひ最後までご一読ください。
YouTubeの平均視聴時間とは平均再生時間と類似した指標

YouTubeの平均視聴時間とは、平均再生時間と類似した指標です。
平均視聴時間とは、その動画を視聴者全員を平均した際に何分見たかを表す指標になっています。具体的には以下の計算式で表せます。
- 動画尺 × 視聴者維持率 = 平均視聴時間
平均再生時間は、一本の動画がどのくらいの時間視聴されたかを示す指標であり、下記の式で計算されます。
- 平均再生時間 = 合計動画再生時間 ÷ 動画の開始回数
例えば、20秒の動画を1人のユーザーが最後まで視聴し、別のユーザーが半分の10秒間視聴した場合、平均再生時間は以下のようになります。
- 動画の合計視聴時間:20秒 + 10秒 = 30秒
- 動画の開始回数:2回
- 平均再生時間 = 30秒 ÷ 2回 = 15秒
この15秒という数字が平均視聴時間であり、動画が平均してどれだけの時間見られているかを示す重要な指標です。
また、アルゴリズムに優遇されるためには、視聴者維持率と平均視聴時間の両方が大事です。
この際に、「動画尺が長ければ、平均視聴時間は増えるが視聴者維持率が落ちてしまう」と悲観する必要はありません。
また、自分の動画の視聴者維持率を知りたい場合は、YouTubeアナリティクスを用いることで、他の動画との比較が見られます。
YouTubeで平均視聴時間が大切な指標となる理由

YouTubeで平均視聴時間が大切な指標となる理由は、以下の2つです。
- 理由①:再生回数が増えやすいため
- 理由②:広告収入が上がりやすいため
次項でそれぞれ解説します。
理由①:再生回数が増えやすいため
YouTubeで平均視聴時間が大切な理由の1つは、再生回数が増えやすくなる点にあります。
平均視聴時間が長ければ長いほど、YouTubeのアルゴリズムにより評価され、おすすめに出やすくなるのです。
それにより、ホーム画面、検索結果ページ、関連動画セクションなどでの露出が増えるため、インプレッション数(動画が表示される回数)が増加します。
インプレッション数が増えると、自然と動画の視認性が高まり、結果として再生回数の増加が期待できます。
平均視聴時間を伸ばすことで、再生回数が増えやすくなり、視聴者を獲得する機会も増やすことが可能です。
理由②:広告収入が上がりやすいため
平均視聴時間がYouTubeで重要視されるもう1つの理由は、広告収入の増加が期待できるためです。
動画の平均視聴時間が長いほど、動画内で視聴者に表示される広告の数は増えるためです。
例えば、15秒あたりに広告が1回表示されると仮定します。
| 平均視聴時間 | 表示される広告の数 |
| 15秒 | 1回 |
| 1分 | 4回 |
このように、1つの動画が視聴される時間が長ければ長いほど、その動画で表示される広告の数も増えるため、収益機会は増大します。
- このように、平均視聴時間が長い動画は、同じ再生数であってもより高い広告収入を期待できるという利点があります。
YouTubeの平均視聴時間を確認する方法

平均視聴時間で大事なポイントは、ターゲット層からの平均視聴時間が高いかどうかです。
そのため、YouTubeアナリティクスを活用し、ターゲット層に近い動画で平均視聴時間が長いか確認することが重要です。
YouTubeの平均視聴時間を確認する方法は、以下の2つです。
- パソコンからYouTubeアナリティクスを使う場合
- スマホからYouTubeアナリティクスを使う場合
それぞれの方法を詳しく解説していきましょう。
方法①:パソコンからYouTubeアナリティクスを使う場合
パソコンからYouTubeアナリティクスを使って自分の動画の平均視聴時間を知りたい場合の手順は以下の通りです。
- YouTubeにアクセス:YouTubeにアクセスし、アカウントにログインします。
- YouTube Studioに進む:プロフィールアイコン(画面右上の位置)をクリックし、「YouTube Studio」を選択します。
- 分析セクションへ:左のナビゲーションバーで「分析」をクリックします。
- エンゲージメントタブを選択:上部タブから「エンゲージメント」を選択します。
- 平均視聴時間を確認:画面中央の「視聴時間」グラフで確認できます。特定の動画の詳細を見たい場合は、「コンテンツ」タブから該当動画を選択し、「分析」ボタンをクリックします。
ターゲット層に近い動画で平均視聴時間が長いかを確認する場合は、「リーチ」の中のある、この動画がおすすめに表示されているコンテンツ下の詳細を調べることで把握できます。
これにより、視聴者がどれだけの時間コンテンツを視聴しているか、その動画のパフォーマンスを把握できます。
方法②:スマホからYouTubeアナリティクスを使う場合
スマートフォンを使って平均視聴時間を確認する場合、YouTube Studioアプリを使用する必要があります。
以下のステップで操作を行ってください。
- YouTube Studioアプリを開く:スマートフォンで「YouTube Studio」アプリを開きます。もしアプリのインストールがまだであれば、Google PlayやApp Storeからダウンロードしてください。
- 分析タブを選択:アプリの下部にある「分析」タブをタップします。
- 期間を選択:画面上部で確認したい期間を選択します。
- エンゲージメントを確認:スクロールして「エンゲージメント」セクションを見つけ、「平均視聴時間」の項目を確認します。
- 特定の動画の詳細を見る:「コンテンツ」タブから確認したい動画をタップし、「分析」を選択すると詳細データにアクセスできます。
この手順でも、視聴者がどれくらいコンテンツに興味を持っているかのパフォーマンス分析が可能です。
ターゲット層に近い動画で平均視聴時間が長いかどうかを確認する場合は、PCと同様の方法で確認できます。
YouTube平均視聴時間の目安

YouTubeの平均視聴時間の一般的な目安としては、40%以上の視聴率を目指すことが良いとされています。
例えばトータル10分の動画だと、平均視聴時間が約4分以上であれば理想的だと言えるでしょう。
ただし動画の長さによって、平均視聴時間の目安は下記のように異なります。
- 短い動画(例:5分以下):60 – 70%
- 中長編動画(例:5〜10分):50 – 60%
- 長編動画(例:10分以上):40 – 50%
それぞれの数値はあくまで目安であり、各チャンネルや動画内容に応じて目標値は変動する可能性があります。
- 常にコンテンツを分析し、視聴者が求める価値のある動画を提供し続けることが、長期的な成果に結びつくポイントとなるでしょう。
YouTubeの平均視聴時間を伸ばすためのポイント

YouTubeの平均視聴時間を伸ばすためのポイントは、以下の6つです。
- 最初の30秒で視聴者を惹きつける動画を作る
- どの視聴者層の平均視聴時間が長いのか分析する
- サムネイルで釣らない
- クリック率と平均視聴時間のバランスを取る
- ターゲットにハマった動画はじわじわ伸びることを理解しておく
- わかりやすく情報量の多い動画を作る
それぞれのポイントを押さえることで、視聴者に安定して視聴される動画作りが可能になります。
それでは、各ポイントについて具体的な方法を確認していきましょう。
ポイント①:最初の30秒で視聴者を惹きつける動画を作る
YouTubeの平均視聴時間を伸ばすためには、最初の30秒で視聴者を惹きつける動画を作りましょう。
動画を見るメリットを強調したり、視聴者に問題提示をしたりして惹きつける工夫が必要です。
- ストーリーテリング
- ビジュアル&オーディオの工夫
- 即効性のある情報提供
このようなポイントを取り入れ、動画の価値を素早く伝えることが求められます。
ポイント②:どの視聴者層の平均視聴時間が長いのか分析する
YouTubeの平均視聴時間を伸ばすためには、どの視聴者層の平均視聴時間が長いのかを分析し、理解することも必要です。
ターゲット層を正確に理解するためには、「YouTubeでどの動画を見た後におすすめされたか、関連動画から来たか」を分析することが有効です。
- データ分析
- ターゲティング
- 関連動画の分析
ここでの注意点としては、チャンネルとして狙っているターゲットと別の視聴者層が長く視聴しても、必ずしもチャンネルの成長に効果的とは限らないという点です。
分析を通して、ターゲットとなる視聴者層の平均視聴時間を伸ばせるようなコンテンツを作る必要があると言えます。
ポイント③:サムネイルで釣らない
YouTubeの平均時間を伸ばす際に、動画の内容と異なるサムネイルで視聴者を呼び込むのはおすすめしません。
なぜなら、ターゲット層以外の視聴者が動画を見ることで、視聴者維持率が下がってしまう恐れがあるからです。
また、ターゲット層以外の視聴者に拡散してしまうことで、動画全体のスコアが下がってしまう可能性もあります。
動画を投稿する際は、動画の内容と異なるサムネイルなどで視聴者を呼び込むのはやめておきましょう。
ポイント④:クリック率と平均視聴時間のバランスを取る
YouTube動画の平均視聴時間を伸ばすためには、クリック率(視聴者が動画を開始する確率)と平均視聴時間のバランスを取ることも重要です。
クリック数とは、広告やサムネイルがどれだけ見られたか(インプレッション)と、実際にどれだけクリックされたかを表す比率です。
ただし、クリック数が多いだけでは意味がありません。
なぜなら、クリック数が多くても平均視聴時間が短いなら、それは質の高い動画とは言いにくいからです。
大切なのは、ターゲットとなる視聴者に合わせた良質な動画を作ることです。
そのためには、サムネイル・タイトルの最適化や、動画内容の品質を上げることが必要となるでしょう。
ポイント⑤:ターゲットにハマった動画はじわじわ伸びることを理解しておく
YouTubeの平均視聴時間は、通常爆発的に伸びるわけでなく、じわじわ伸びていくことが一般的です。
ターゲット層に向けた動画であれば、長期的に再生されることが多いです。
一方で、稀に意図していない視聴者層からの平均視聴時間が爆発的に伸びることがあります。しかし、ターゲットと異なる視聴者層では、その人気が持続しないケースがよくあります。
そのため、ターゲット層からの平均視聴時間がすぐに増えなくても、他の視聴者層をターゲットにしないようにしましょう。
一時的なトレンドではなく、ターゲット層のニーズにこだわり続けることが重要です。
ポイント⑥:わかりやすく情報量の多い動画を作る
YouTubeで平均視聴時間を伸ばすためには、わかりやすく情報量の多い動画を作ることも不可欠です。
動画の長さが短いと、視聴者が動画を見る時間も必然的に短くなりがちです。
そのため、動画の長さを少し長めにしてみることは、視聴時間を伸ばす有効な手段の一つです。
ただし、ただ動画の長さを長めにしても、情報量が少なければ視聴者に離脱されてしまう可能性が高まります。
例えば、視聴者が学び、理解できるように情報を整理し、段階的に提示してみましょう。
また、解説に役立つ補足情報や関連するデータを提供し、視聴者の知的好奇心を刺激するのも有効です。
- このように、内容をより分かりやすく説明したり、追加の情報を提供したりすると、視聴者の興味を強く惹きつけることができます。
平均視聴時間と平均再生率の違い

YouTubeにおける平均視聴時間と平均再生率は、動画のパフォーマンスを測る重要な指標ですが、それぞれ違いがあります。
2つの指標は動画のどの部分が視聴されているか(再生率)、視聴者がどれくらいの時間動画コンテンツを見ているか(視聴時間)を別々に示します。
まず、平均視聴時間は動画が再生された合計時間を視聴回数で割ったもので、以下の式が用いられます。
- 平均再生時間 = 合計動画再生時間 ÷ 動画の開始回数
視聴者がどれだけの時間動画を視聴したかがわかり、動画の魅力や視聴者がどの程度関心を持っているかを確認するのに役立ちます。
- 次に、平均再生率は、ユーザーが動画で視聴した部分の平均割合(%)です。
計算式が複雑なため、例を元に解説します。
- 1人のユーザーが動画を最後まで視聴した(動画の開始1回・25%再生1回・50%再生1回・75%再生1回・再生完了1回)
- もう1人のユーザーが動画の25%まで視聴した(動画の開始1回、25%再生1回)
上記のケースを以下のように数値化できます。
| ⑥ユーザー | ユーザー1 (完了) | ユーザー2 (25%まで) | 合計 |
| ①動画の開始回数 | 1 | 1 | 2 |
| ②動画の25%再生回数 | 1 | 1 | 2 |
| ③動画の50%再生回数 | 1 | 0 | 1 |
| ④動画の75%再生回数 | 1 | 0 | 1 |
| ⑤動画再生完了回数 | 1 | 0 | 1 |
これを計算式に当てはめると以下になります。
- 0.125× 2(①) + 0.25 × 2(②) + 0.25 × 1(③) + 0.25 × 1(④) + 0.125 × 1(⑤) ÷ 2(⑥)
これに基づいて、2人のユーザーがいた場合の平均再生率は、約68.75%(0.6875)となります。
平均視聴時間が長ければ、それだけ動画を通して長い時間視聴者を惹きつけられていることになり、平均再生率が高ければ、多くの視聴者が動画をはじめから終わりまで視聴していることを意味します。
モバイル視聴とPC視聴での平均視聴時間の違い

YouTubeの平均視聴時間は、視聴デバイスによって大きく異なります。この違いを理解し、ターゲットとなるデバイスに合わせたコンテンツ制作が重要です:
1. デバイス別の特性
モバイル:平均視聴時間は通常短め(2〜3分程度)で、移動中や空き時間に視聴されることが多い
PC/デスクトップ:平均視聴時間が長め(5〜7分程度)で、より集中した視聴環境での利用が多い
テレビ/セットトップボックス:最も長い平均視聴時間(8分以上)で、リラックスした環境での視聴が主
2. デバイス別の最適化ポイント
モバイル向け: 冒頭15秒で核心に入る、縦型動画も検討、テキストは大きく
PC向け:詳細な情報提供、画面分割や小さなテキストも可能、より複雑な内容も許容される
テレビ向け:高画質・高音質、テキスト少なめ、ビジュアル重視
3.YouTube Studioでの分析
アナリティクスの「視聴者」タブにある「デバイスの種類」セクションで、自チャンネルのデバイス別視聴状況を確認できます。この情報を基に、主要視聴デバイスに最適化したコンテンツ制作を検討しましょう。
主要な視聴デバイスを把握し、そのデバイスでの視聴体験を最適化することで、平均視聴時間の向上につなげることができます。
YouTubeの平均視聴時間についてよくある質問

本章では、YouTubeの平均視聴時間についてよくある質問についてまとめています。
今回は以下について回答していきます。
- YouTubeの平均視聴率は?
- YouTubeの平均視聴時間の見方は?
- YouTubeの平均視聴時間が3分なのは短い?
- Youtubeの視聴時間をあげるためにできる工夫は?
- YouTubeの平均視聴時間が動画より長いのはなぜ?
以下でそれぞれ詳細に解説します。
Youtubeの平均視聴率は?
YouTubeの平均視聴率(Audience Retention)は、視聴者が動画をどの程度視聴したかを示す指標です。
一般的に、視聴率が50%以上であれば良好とされ、特に60%以上を維持できれば非常に高いエンゲージメントを示します。
この指標は、視聴者が動画をどこで離脱するかを把握し、改善点を見つけるために重要です。
視聴率が高いほど、YouTubeのアルゴリズムがその動画を推奨しやすくなり、より多くの視聴者に届く可能性が高まります。
Youtubeの平均視聴時間の見方は?
YouTubeの平均視聴時間は、YouTube Studioのアナリティクスで確認できます。
まず、YouTube Studioにログインし、左側のメニューから「アナリティクス」を選択します。
次に、「エンゲージメント」タブをクリックすると、動画ごとの平均視聴時間が表示されます。
この指標は、視聴者が動画を視聴した平均時間を示し、コンテンツの効果を評価するのに役立ちます。
また、視聴者の離脱ポイントを分析し、動画の構成や内容を改善するためのヒントを得られるためおすすめです。
Youtubeの平均視聴時間が3分なのは短い?
YouTubeの平均視聴時間が3分というのは、動画の長さや内容によって判断が異なります。
例えば、10分以上の動画で平均視聴時間が3分であれば、視聴者が途中で離脱している可能性が高く、改善の余地があります。
しかし、5分以下の短い動画で3分の視聴時間は比較的良好と考えられます。
視聴時間を向上させるためには、最初の数秒で視聴者の興味を引き、動画全体を通して価値のある情報やエンターテインメントを提供することが重要です。
YouTubeの視聴時間をあげるためにできる工夫は?
YouTubeの視聴時間を上げるためには、いくつかの工夫が必要です。
まず、動画の冒頭で視聴者の興味を引くことが重要です。強力なイントロやクリフハンガーを用いて、視聴者が続きを見たくなるようにします。
次に、動画の内容を分かりやすく、魅力的に構成することも大切です。セグメントごとにテーマを明確にし、視覚的な要素を活用して視聴者の関心を維持します。
また、動画の長さを適切に保ち、無駄な部分をカットすることで、視聴者が最後まで視聴しやすくなります。
最後に、視聴者とのエンゲージメントを高めるために、コメントやコミュニティタブを活用し、視聴者のフィードバックを取り入れて改善を図ることも効果的です。
YouTubeの平均視聴時間が動画より長いのはなぜ?
YouTubeのアナリティクスで平均視聴時間が動画の実際の長さより長く表示されることがあります。この現象にはいくつかの理由があります。
・リピート視聴の影響: 視聴者が動画内の特定のセクションを繰り返し見ると、その累積時間が平均視聴時間に反映されます。例えば、5分の動画で視聴者が特定の部分を何度も再生すると、平均視聴時間は5分を超えることがあります。
・バックグラウンド再生:YouTube Premiumユーザーがバックグラウンドで動画を再生し続けると、実際の動画長より長い再生時間が記録される場合があります。
・エンドスクリーンでの滞在:視聴者が動画終了後もエンドスクリーンに留まり、次の動画を選んでいる時間も視聴時間としてカウントされることがあります。
・計測上の技術的要因:まれに、再生速度の設定や一時停止の処理方法によって、視聴時間の計算に差異が生じることがあります。
このような現象は通常、コンテンツが非常に高い評価を受けており、視聴者が何度も視聴している証拠と考えられます。エンゲージメントの高さを示す良い指標ですので、むしろポジティブに捉えるべきでしょう。
平均視聴時間はYouTubeにおける大切な指標
YouTubeにおける平均視聴時間は、動画の品質やチャンネルのパフォーマンスを示す重要な指標です。
視聴者が動画を最後まで視聴することで再生回数が増え、広告収入の向上にもつながります。
しかしながら、チャンネル運営者には動画コンテンツの質をどのようにして高めるかという課題が残ります。
もしこの記事でご紹介したポイントを用いても平均視聴時間が伸びない場合や運用の方向性に迷う場合は、ぜひNOGICへご相談ください。
YouTubeチャンネル成長のため、無料診断も実施しています。
「YouTubeでの更新頻度を上げるべきか」「毎日投稿をした方がいいのか」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
更新頻度を極端に落としてしまうと視聴者の関心が薄れてしまうリスクがありますが、実際YouTubeの更新頻度はそこまで重要ではありません。
更新頻度よりも動画の質を高めることに重きを置くことが大切です。
この記事ではYouTubeの更新頻度がなぜそこまで重要でないのかを解説します。
そのうえで、YouTubeの適切な更新頻度や質の高いYouTube動画・チャンネルを作るためのポイントについても紹介します。
「YouTubeチャンネルの成長に悩んでいる」「効果的な動画マーケティングを実施したい」という方はぜひ最後までご一読ください。
YouTubeの更新頻度はそこまで重要ではない

YouTubeでの動画更新頻度について、一般的には以下の誤解が存在しています。
- 「週〇〇日の投稿が良い!」とされる一定のルールがある
- 「毎週水曜日、金曜日、日曜日に動画が上がるから見に行こう!」というような視聴者の習慣がある
しかし、一定のルールや視聴者の習慣、いわゆるYouTubeの更新頻度はそこまで重要ではありません。
更新頻度よりも、以下のような改善を優先するべきだからです。
| 項目 | 内容 |
| コンテンツの質 | 視聴者は高品質のコンテンツを好む傾向があり、更新頻度よりもコンテンツのクオリティを重視する傾向がある。 |
| ユーザーのロイヤリティ | 視聴者がチャンネルに対して持つロイヤリティは、更新頻度よりもコンテンツの継続的な価値に影響されることが多い。 |
| 利便性 | ユーザーは自分の都合の良い時に動画を視聴するため、厳密な更新スケジュールよりもアクセスのしやすさや見やすさを優先することがある。 |
これらはあくまでも一例で、そのほかにも多くの指標があります。
つまり、更新頻度だけが必ずしもチャンネルの成功や視聴者のエンゲージメントに決定的な影響を与えるわけではないということです。
重要なのは、継続的に魅力的なコンテンツを提供し、視聴者との関係を築いていくことです。
動画の品質、チャンネルへのロイヤリティ、利便性などを高めるという施策の方が、単純に更新頻度を高めるよりも視聴者の満足度やチャンネルの成長に大きく影響する可能性が高いのです。
YouTubeでは更新頻度よりも質の高い動画を出すことが重要

YouTubeで動画を制作・公開する際、更新頻度よりも質の高い動画を出すことが重要である理由にはいくつかの背景があります。
- 更新頻度が低くても質の高い動画を出せば拡散されていく
- 質の高い動画が求められるようになった背景
視聴者が求める高品質なコンテンツを提供することで、YouTubeでの成功と持続的な成長を実現できます。
更新頻度を追求することも重要ですが、質を犠牲にしてまで頻繁に投稿することは得策ではありません。
以下で、それぞれの理由を説明します。
更新頻度が低くても質の高い動画を出せば拡散されていく
YouTubeにおいては、更新頻度を上げるよりも高品質な動画を作成して投稿することが重要です。
優れた動画は視聴者にとって価値があると認識され、自然と共有されやすくなるためです。
特にYouTubeのアルゴリズムは、ユーザーの関心や視聴履歴に基づいて質の良いコンテンツを推薦するように設計されています。
更新頻度が高すぎると個々の動画にかけられる時間や労力が少なくなり、結果として質の低下を招くリスクがあるため、無理に頻度を追求することは避けるようにしましょう。
質の高い動画が求められるようになった背景

YouTube上で高品質な動画が求められる背景には、動画の平均品質が向上している実態もあります。
YouTubeは激しい競争市場であり、目立つためには高品質な動画が必須です。
他のクリエイターたちも質の高い動画を投稿しているため、質が低いとその中で目立つことが難しくなり、結果として拡散の可能性も低くなると言えます。
そのため、更新頻度よりも品質にフォーカスし、より多くの拡散を狙い、視聴者から長期的に関心を持たれるチャンネルにすることが重要です。
YouTubeの適切な更新頻度は?

YouTubeの適切な更新頻度はチャンネルのジャンルや対象視聴者によって大きく異なることが明らかになっています。
一般的には週に1〜2回が基本ラインとされていますが、ニュースやトレンド系のチャンネルではより頻繁な更新が求められる一方、教育コンテンツやドキュメンタリーなどの制作に時間がかかるコンテンツでは月に1〜2回でも十分効果を発揮するケースが増えています。
「視聴者のライフスタイルやコンテンツ消費パターンに合わせた更新頻度」が重要であり、単一の理想的な頻度は存在しないことが強調されています。
質の高いYouTube動画を出すという前提で自社のチャンネルにとって適切な更新頻度を考えていきましょう。
更新が少なすぎても離脱や伸び悩む原因になる
YouTubeでの活動においては、更新頻度が低すぎるというのも、チャンネルの成長速度を大きく阻害する要因になります。
一般的に、視聴者は定期的に新しい動画が投稿されることを期待しているためです。
特にYouTubeはコンテンツの新鮮さが非常に重要視されるプラットフォームであるため、更新頻度が低いと視聴者は「全然投稿されない」と感じます。
これにより「もっと更新しているチャンネルを見よう」と考える視聴者も少なくありません。
さらにチャンネル登録をしてくれていた視聴者が見切りを付け、登録を解除する原因にもなり得ます。
質を担保する前提で更新頻度を高めていくことがポイント
これまで解説したように、質を維持しつつ更新頻度を高めていくことがYouTubeチャンネルの成長のポイントです。
高品質のコンテンツを提供することを前提としている場合、更新頻度は高ければ高いほど視聴者を惹き付け、YouTubeのアルゴリズムにも有利に働きます。
ただし、無理をして質の低下を引き起こさないように注意が必要です。
多くの場合、週に1〜2回の更新が一般的な目安であり、視聴者が想定している範囲での定期的なスケジュールを作成することが推奨されます。
このバランスを取りながら、自チャンネルにとって適切な更新頻度を見つけ出すことが大切です。
最終的には、チャンネルの内容やターゲットオーディエンス、制作能力などに基づき、個々の状況に適した更新戦略を練ると良いでしょう。
質の高いYouTube動画・チャンネルを作るためのポイント

質の高いYouTube動画・チャンネルを作るためには、以下の点を押さえることが大切です。
- 特定のターゲット層に向けた専門性の高い動画を作る
- 映像・音声など動画そのもののクオリティを高める
- ストーリー性があり視聴者の興味を引く動画を作る
- キーワードが盛り込まれた動画を作る
- エンゲージメントを高める工夫をする
- 更新頻度だけではなく投稿時間も考慮する
- アナリティクスを使って分析を行う
- ショート動画とロング動画を組み合わせる
それぞれのポイントを実践することによって、興味を持ってもらえるだけでなく、視聴者との関わりを深め、YouTube上での価値を高めることができます。
ポイント①:特定のターゲット層に向けた専門性の高い動画を作る
YouTubeで成功するためには、特定のターゲット層を明確に定め、その層に特化した専門性の高いコンテンツを作成することが重要です。
ターゲット層が興味を持つ特定のトピックや分野を深く掘り下げることで、そのニーズに合わせた詳細な情報提供が可能となります。
例えば、以下のポイントを意識するだけでも、その分野における信頼性の高い情報源となります。
- 視聴者の潜在的な質問に答える
- 豊富な実例とともに伝える
- 分かりやすい解説を行う
継続的な更新を通じて専門知識を深め、ターゲット層に響く質の高い動画を提供することで、視聴者の愛着や忠誠心を高めることができるでしょう。
ポイント②:映像・音声など動画そのもののクオリティを高める
YouTube動画の品質を高めるには、映像や音声そのもののクオリティにも細心の注意を払う必要があります。
高解像度のカメラやクリアな音質のマイクを使用し、視聴体験を重視した品質管理を心がけることで、ユーザーに快適な視聴環境を提供できます。
また、編集技術を駆使して不要な部分をカットするほか、視聴者の興味を引きつけるエフェクト(特殊効果)やトランジション(映像の切り替え効果)を活用するとより効果的です。
ポイント③:ストーリー性があり視聴者の興味を引く動画を作る
YouTube動画にストーリー性を持たせることで、視聴者との感情的なつながりを築き、興味関心を引くこともできます。
例えば、感動的な体験を共有したり、教訓を含んだ物語を展開したりするなど、十分な時間をかけてクオリティの高いストーリーテリングを実現することが望ましいです。
ストーリーを通じて情報を伝えることで、視聴者は動画の中に自分自身を投影しやすく、より動画内容に関心を持つようになります。
ポイント④:キーワードが盛り込まれた動画を作る
YouTubeで視聴者に動画を見つけてもらいやすくするためにも、キーワードが適切に盛り込まれた動画を作りましょう。
SEO(検索エンジン最適化)に関する知識を活用し、ターゲット層の視聴者が使用する検索キーワードをリサーチして、タイトルや説明文、ハッシュタグに盛り込む必要があります。
キーワードの活用によって、検索結果やおすすめリストへ表示される可能性が高まり、YouTubeにおけるリーチ(動画の到達範囲)が拡大します。
なお、キーワードについてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
参考:YouTubeのキーワード設定はなぜ重要?調査方法や活用ポイントを解説!
ポイント⑤:エンゲージメントを高める工夫をする
質の高いYouTube動画・チャンネルを作るためのポイントとして、エンゲージメントの向上を狙うことも挙げられます。
エンゲージメントとは、視聴者が動画にどれほど積極的に関わっているかを測る指数です。
コメントを残したり、動画に評価をつけたり、友達に共有したりするなどの行動の多さに基づいた指標であり、エンゲージメントが高いほどYouTubeのアルゴリズムから好まれやすくなります。
その結果、おすすめ動画としてピックアップされる可能性も高まります。
エンゲージメントを高めるためには、視聴者へのコメントや評価、共有を促すCTA(行動喚起)を動画内に挿入することが効果的です。
エンゲージメントについてより詳しく知りたい方は、併せて以下の記事を参考にしてください。
参考:YouTubeのおすすめ動画の仕組みは?再生回数を伸ばす方法も解説
ポイント⑥:更新頻度だけではなく投稿時間も考慮する
YouTubeでは、更新頻度だけではなく投稿時間も考慮することが重要です。
視聴者が特にアクティブな時間帯に動画を投稿することで、リアルタイムな反応を得やすくなります。
再生回数やコメントを増やすためには、金・土・日曜日や午後6時〜午後9時のタイミングを狙っての公開がおすすめです。
繰り返しになりますが、質を担保したうえで定期的に良いコンテンツを提供できるかというポイントは忘れないようにしましょう。
YouTubeの投稿時間については、以下の記事も参考にしてください。
参考:YouTubeの動画を投稿する最適な時間は?動画の再生数UPのコツを徹底解説!
ポイント⑦:アナリティクスを使って分析を行う
YouTubeアナリティクスの活用によって、動画のパフォーマンスを分析し、視聴者の属性や行動を理解できます。
再生回数や視聴時間をチェックすることはもちろん、ターゲット層がどのキーワードで検索しているかを知ることもできます。
こうしたデータを基にして、動画のテーマやタイトルの最適化を行ったり、効率的な更新頻度に調整したりできます。
YouTubeの視聴者の傾向を理解し、戦略的に活用することは、チャンネルの成長を促進させるうえで不可欠です。
ポイント⑧:ショート動画とロング動画を組み合わせる
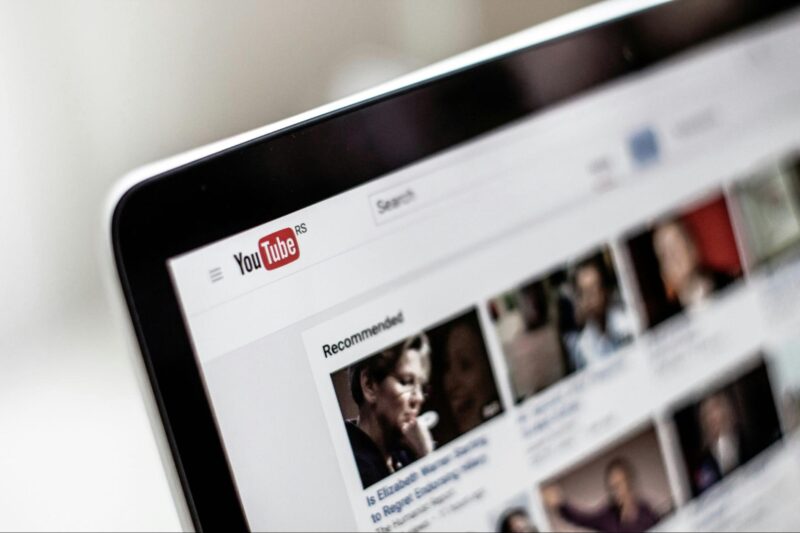
重要なトレンドとして、多くの成功しているYouTubeチャンネルが「ショート動画とロング動画のハイブリッド戦略」を採用していることが挙げられます。この戦略は特に更新頻度の悩みを解決する新しいアプローチとして注目されています。
YouTube Shortsは、比較的少ないリソースで制作でき、アルゴリズム上も優遇される傾向があります。最新データによると、ショート動画は新規視聴者の獲得に特に効果的で、チャンネル発見の入り口として機能します。
具体的な活用法としては、週に1本の質の高いロング動画に加えて、その内容からピックアップした2〜3本のショート動画を平日に分散して投稿するアプローチが効果的です。これにより、更新頻度を上げつつも、制作負担を大幅に増やさずに済みます。
既存のロング動画から効果的にショート動画を作成するコツは、以下の点に注意することです。
- 動画内の最も印象的な10〜30秒のシーンを抽出する
- 縦型フォーマット(9:16)に最適化し直す
- キャッチーなキャプションを追加する
- 冒頭3秒で視聴者の注目を引く要素を入れる
- ロング動画へのCTAを最後に加える
この「一度作って複数形式で展開する」アプローチは、現在のYouTube戦略として特に効果的であることが多くの事例で証明されています。
YouTubeでよくある投稿頻度

YouTubeでよくある投稿頻度は、以下が挙げられます。
- 毎日投稿
- 曜日固定の投稿
それぞれの投稿頻度はそれぞれメリットとデメリットがあるため、自分のコンテンツと目的に合った方法を選ぶことが重要です。
次項では、それぞれの投稿頻度の特徴と留意点を詳しく解説します。
毎日投稿
YouTubeにおける毎日投稿は、視聴者との継続的なつながりを作り出し、YouTubeのアルゴリズムにも有利に働く可能性があります。
しかし先述したとおり、内容の質を落としてしまうと、根強いファンでさえも遠ざけてしまう危険があります。
- 内容の多様性(異なるトピックやフォーマットを用意すること)を考慮してコンテンツカレンダーを作り、前もって撮影や編集を行う
- 視聴者の期待に合わせて、あらかじめ定めた品質基準を満たすことを意識する
- 複数の動画をバッチ制作(一度に多くの動画を同時に制作すること)し、作業を効率化する
- 必要に応じて外部のエディター、カメラマンに専門的な作業を委託する
- コミュニティタブやソーシャルメディアを使って、視聴者からのフィードバックを得て、質の向上に役立てる
など、毎日投稿を行う際でも品質へのアプローチは減らさないようにしましょう。
曜日固定の投稿
同じ曜日に投稿するルーティンを作るのもYouTubeでよく見られる投稿頻度です。
これにより、視聴者は新しい動画がいつ公開されるかを予測しやすくなります。
投稿する動画やテーマについて予告動画やティーザーを事前に公開することで、次のコンテンツへの期待感を高めるのもいいでしょう。
ただし、先述したように曜日固定の投稿をしたとしても、視聴者からその曜日に毎週動画を観てもらえるとは限りません。
質を落とさないことが最優先なので、曜日固定にすることで質が低い動画を投稿することはやめておきましょう。
YouTubeの更新頻度・投稿頻度でよくある質問

本章では、YouTubeについてよくある質問についてまとめています。
今回は以下について回答していきます。
- YouTubeの投稿頻度を決めるアルゴリズムは?
- YouTubeの更新頻度を増やすことで収益は上がる?
- YouTubeの投稿時間は関係ない?
- 動画の毎日投稿が伸びない原因は?
- YouTubeで毎日投稿は禁止されているの?
以下でそれぞれ詳細に解説します。
YouTubeの投稿頻度を決めるアルゴリズムは?
YouTubeのアルゴリズムは、投稿頻度を直接決定するわけではありませんが、一定の投稿頻度を保つことはアルゴリズムに好影響を与えます。
アルゴリズムは、視聴者のエンゲージメント、視聴時間、視聴者維持率などの指標を基に動画を推奨します。
定期的な投稿は視聴者に期待感を与え、エンゲージメントを高めることができます。
特に、視聴者が新しいコンテンツを定期的に期待するようになると、視聴者のリテンション率も向上します。
その結果、アルゴリズムがチャンネルをより多くの視聴者に推奨する可能性が高まります。
YouTubeの更新頻度を増やすことで収益は上がる?
YouTubeの更新頻度を増やすことは、収益向上に寄与する可能性があります。
頻繁に新しい動画を投稿することで、視聴者の関心を維持し、再生回数が増えるためです。
再生回数が増えると、広告の表示回数も増え、結果的に広告収益が上がります。
ただし、これまで解説してきたように、ただ頻度を上げるだけではなく、コンテンツの質を保つことが重要です。
質の低い動画を大量に投稿すると、視聴者の離脱を招き、逆効果となる可能性があります。
YouTubeの投稿時間は関係ない?
YouTubeの投稿時間は、視聴回数やエンゲージメントに影響を与える可能性があります。
視聴者の多くがオンラインである時間帯に動画を公開することで、初動の再生回数を増やし、アルゴリズムに有利に働くことがあるためです。
例えば、視聴者が多い夕方や週末に投稿することで、より多くの視聴者にリーチできる可能性があります。
また、視聴者の多くが特定の地域にいる場合、その地域のピーク時間に合わせて投稿することが効果的です。
YouTube Analyticsを活用して、視聴者のオンライン時間を分析し、最適な投稿時間を見つけることが重要です。
動画の毎日投稿が伸びない原因は?
動画の毎日投稿が伸びない原因にはいくつかの要素があります。
まず、コンテンツの質が低い場合、視聴者の関心を引き続けることが難しくなります。量を優先して質を犠牲にすると、視聴者が離れていく可能性が高いです。
次に、視聴者が毎日新しい動画を見る時間や興味がない場合も、再生回数が伸びにくくなります。
さらに、動画のテーマや内容が視聴者のニーズや興味に合っていない場合も、エンゲージメントが低下します。
視聴者のフィードバックを活用し、コンテンツの質を向上させることが重要です。また、投稿頻度を視聴者のペースに合わせることも考慮すると良いでしょう。
YouTubeで毎日投稿は禁止されているの?
YouTubeで毎日投稿が禁止されているという誤解がありますが、実際にはプラットフォーム側からの投稿頻度に関する明確な禁止ルールは存在しません。
しかし、短時間に大量の動画をアップロードすると、YouTubeのシステムがスパム行為と判断し、一時的に投稿制限がかかることがあります。これは1日に数十本以上の動画を一度にアップロードするような極端なケースに限られます。
重要なのは、毎日投稿すること自体ではなく、以下のポイントです。
・コンテンツの品質を維持できるか
・チャンネルのテーマや目的に合致しているか
・視聴者のニーズに応えているか
現在のYouTube運用においては、「闇雲な毎日投稿」よりも「戦略的な投稿計画」の方が効果的です。チャンネルの成長段階や制作リソース、視聴者の行動パターンを分析した上で、最適な投稿頻度を決定することをおすすめします。
毎日投稿がチャンネルにとって最適な選択であれば実施すべきですが、無理をして質を落とすくらいなら、週に1〜2回の高品質なコンテンツ投稿の方が長期的な成功につながる可能性が高いでしょう。
更新頻度だけに固執せず質の高さを追求するのがYouTube運営のコツ!
更新頻度を高めたりや毎日投稿をしたりすることはYouTubeチャンネルの成長に役立つように思えますが、質が低いコンテンツをただ多く作るだけでは逆効果です。
むしろ、チャンネル成長の妨げになる可能性があります。
そのため、まずは動画の質を高めることに重きを置いた戦略を考えるのが大切です。
NOGICでは、YouTubeチャンネルの現状を徹底的に分析し、その結果に基づいた戦略をご提案しています。
「チャンネルがなかなか伸びずに悩んでいる」「社内リソースが不足している」などのお悩みがある方は、ぜひNOGICにご相談ください。
「YouTubeのキーワード設定は本当に必要?」「どうやって最適なキーワードを見つけ出せばいい?」とお悩みではないでしょうか。
YouTubeのキーワードを正しく設定することで、動画の検索順位向上を目指せます。
そこで本記事では、YouTubeのキーワード設定の必要性と調べる方法、おすすめのキーワードツール、キーワードの活用方法を解説します。
またキーワード以外に必要な動画SEOの情報もまとめました。
YouTubeチャンネルを効率的に伸ばしたい人はぜひ参考にしてください。
YouTubeのキーワード設定は必要?

YouTubeのキーワード設定は、動画のテーマを明確にし、ターゲットに合わせたコンテンツ作りをする際に必要です。
適切なキーワード設定は、YouTube上での検索結果の表示に影響し、動画の視聴率やチャンネルの成長を促進します。
特に、YouTubeはGoogleに次ぐ検索エンジンとしての役割を果たしているため、SEO(検索エンジン最適化)も意識することが大切です。
ただし、調査の進め方やキーワードツールの選び方、キーワードの活用方法を間違えると成果が出なくなってしまうためこれから一つ一つ詳しく説明します。
YouTubeでのキーワードの見つけ方を、3つの実践的な方法で紹介します。
- YouTubeのサジェストから調べる
- キーワードツールを使用する
- YouTube Studioのアナリティクスから調べる
それぞれ詳しく説明します。
YouTubeのサジェストから調べる
YouTubeのサジェストとは、ユーザーが検索窓に入力すると表示される予測候補のキーワードです。
これらのキーワードを利用して、視聴者がどういった言葉で動画を探しているかを調査できます。
サジェストからキーワードを調査する方法は、YouTubeの検索窓に関連する語句を入力し、表示される候補から適切だと思われるものを選定します。
YouTubeのサジェストから調査するメリットは、無料で手軽に関連キーワードを探すことができる点です。
しかし検索されるボリュームや関連キーワードの広がりなどが得られないため、市場におけるニーズの深さを把握することは難しいなどのデメリットもあります。
そのため、ユーザーのおおまかなニーズを手軽に知りたいという方に向いている調査方法と言えるでしょう。
キーワードツールを使用する
キーワードツールは、キーワードの競合性や検索ボリューム、関連キーワードの発見など、より詳細な情報を提供してくれるSEOツールです。
YouTubeコンテンツを市場のニーズに合わせて作るのに役立ち、初心者からプロまで多くのYouTuberが活用している手段です。
キーワードツールのメリットは、YouTubeで視聴者がどのような内容を求めているかを詳しく理解でき、コンテンツの企画や方針を決める際に力強いサポートになることです。
ただしツールによっては無料だとサービスが限られてしまうなどのデメリットがあるため、初心者の方やコストを削減したい方は、ツールを見極めながら自分に合ったものを利用することをおすすめします。
YouTube Studioのアナリティクスから調べる
YouTube Studioのアナリティクス機能を利用すると、自分の動画に流入してきた視聴者が検索したキーワードを調査できます。
確認方法は下記の通りです。
- YouTube Studioからアナリティクスを選択
- リーチを選択
- 右下にある「YouTube 検索語句」を確認
この調査方法を活用すると自分の動画に対するユーザーの需要を詳細に把握できます。
しかし、「YouTube 検索語句」はデータが蓄積されなければ見られないため、チャンネルを立ち上げて間もない時期には活用できません。
そのため、YouTubeチャンネルが活性化してきたタイミングに他の調査方法と併用しながら活用することをおすすめします。
以下の記事におすすめの分析ツールをまとめているので、ぜひ参考にしてください。
参考:YouTube分析ツールおすすめ紹介5選!特徴や選び方を徹底解説!
YouTubeのキーワードツールおすすめ5選【無料あり】

ここからは、おすすめのYouTubeのキーワードツールを5選紹介します。
- ラッコキーワード【無料あり】
- Googleトレンド【無料あり】
- Googleキーワードプランナー【無料あり】
- Keyword Tool【無料あり】
- ahrefs
各ツールの詳細について、順に説明します。
ラッコキーワード【無料あり】
ラッコキーワードとは、サジェストキーワードを取得できるツールです。
無料の範囲内でもサジェストキーワードや共起語など、YouTubeを運営するために必要な情報を取得できます。
これにより、関連性の高いキーワードや視聴者が求める内容を簡単に把握できます。
有料機能を使用すれば、より詳細なデータやSEO競合分析が行え、動画コンテンツの表示を増やすための戦略を立てやすくなります。
動画制作における効果的なキーワード選定は、視聴者に動画を見つけてもらうために大切なポイントです。
Googleトレンド【無料あり】
Googleトレンドは、Googleのトレンドデータの活用によって、現在どのようなキーワードやトピックに人気が集まっているかを知れるツールです。
話題のキーワードを把握しやすいため、トレンドに敏感なコンテンツを制作する際におすすめです。
月間検索数は分かりませんが、関連性の高いトピックスや検索傾向をビジュアルで確認できるため、企業として動画コンテンツの企画を立てる際にも有効です。
Googleトレンドを活用すれば、人の関心事を捉えた動画を作成でき、視聴者の獲得につなげることが期待できます。
Googleキーワードプランナー【無料あり】
Googleキーワードプランナーは、Google Adsに組み込まれている公式のツールです。
キーワードごとの月間検索数や、関連キーワードを無料で調べることができます。
特に関連キーワードの発見は、動画制作のアイデアに役立つでしょう。
有料プランではより具体的な数字が分かりますが、無料でも大まかな検索数が分かるため、始めの一歩としては十分な情報を提供してくれます。
広告運用を考えている企業であれば、クリック単価などの情報を得ることができるため、YouTube広告における予算配分の参考としても活用できます。
Keyword Tool【無料あり】
Keyword Toolは、何千ものキーワードを発見できる、プロにもおすすめの高性能ツールです。
このツールの強みは、ブラウザをYouTubeに絞り、動画に適したキーワード選定が行えることです。
SEO界の著名人からも評価されており、信頼性の高さから人気を集めています。
また、有料版ではさらに機能が拡充され、月間検索数の取得などが可能になるため、動画マーケティングの精度をさらに上げる際など長く活用できるツールと言えるでしょう。
ahrefs
ahrefsはSEO分析に特化した有料ツールであり、プロにも多く利用されています。
キーワードだけでなく、検索エンジン上での上位表示コンテンツや予測流入キーワードなどを深く分析できるなどの強みがあります。
ahrefsは多機能であるため、初心者にはやや扱いが複雑かもしれませんが、YouTube運用に慣れたら使いこなしていけるツールです。
特に競合分析やユーザーニーズの解析において、より細かい情報を取得し、効率的な戦略立案に役立ちます。
YouTubeのSEOについて詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。
参考:YouTubeで上位表示を目指すならSEO!具体的なSEO対策を全て解説
YouTubeのキーワードの活用方法

ここからは、YouTubeでキーワードを上手に活用するための方法を以下に分けて解説します。
- タイトルの左側に入れる
- 概要欄の説明欄にハッシュダグで入れる
- 動画のタグに入れる
- YouTubeチャンネルの基本情報に入れる
- キーワードをテーマにして動画を作成する
これらの各ポイントについて、詳しくみていきましょう。
タイトルの左側に入れる
YouTubeの検索アルゴリズムは、タイトルの左側に配置されたメインキーワードを重要視します。
メインのキーワードを1つタイトルの左側に入れることで、動画の内容をYouTubeの検索アルゴリズムが正確に把握しやすくなるため、動画の検索順位も向上する可能性があります。
この際、文章が不自然にならないような入れ方を意識し、タイトルから動画の内容を推測できることが大切です。
検索結果の上位に表示されると、検索流入の可能性を高めることができるため、特にスタート時は積極的に実践するとよいでしょう。
概要欄の説明欄にハッシュタグで入れる
YouTubeの概要欄にハッシュタグを使ってメインとするキーワードを3〜4個入れましょう。
概要欄は、動画のコンテンツを補足し視聴者に追加情報を提供する重要な部分です。
この概要欄にハッシュタグを使ってキーワードを入れるとYouTubeの検索アルゴリズムにより動画が適切に分類され、検索結果においてより高い位置に表示される可能性が高まります。
さらに、説明文章にも同様のキーワードを自然に織り交ぜることで、その効果を増幅させることが可能です。
しかし、動画の内容と関連性のないキーワードは避けるようにしましょう。
関連性のないキーワードの使用は、視聴者に誤解を招いたり、YouTubeのガイドラインに反したりする可能性があります。
YouTubeのハッシュタグ機能・概要欄機能について詳細を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
参考:Youtubeハッシュタグのつけ方や効果を徹底解説!おすすめ人気タグのつけ方もご紹介
参考:YouTubeの概要欄とは?見方や編集方法・書かない場合の懸念点まで解説
動画のタグに入れる
YouTubeにおけるタグは、動画の内容と特性を明確に伝える上で非常に大切です。
タグを適切に使用することで、動画がYouTubeの検索アルゴリズムや推薦システムによって正しく分類され、対象の視聴者に適切に表示されます。
ただし、以下の点には特に注意が必要です。
- 動画に関連性が高いキーワードを選択すること
- タグの数は最大でも15個までに留めること
- 動画と関係のないタグは避けること
- 抽象度の高いキーワードと具体的なキーワードをバランス良く入れること
また同じチャンネルにある動画に共通のタグを設定すると、関連動画として表示されやすくなるため、ユーザーの回遊率アップなども期待できます。
YouTubeチャンネルの基本情報に入れる
YouTubeチャンネルの基本情報にキーワードを設定することも、チャンネルの独自性と方向性を定義する上で役立ちます。
基本情報に入れるキーワードは商品のパッケージに貼るラベルに似ており、視聴者やYouTubeのシステムに対して、チャンネルの主要なテーマや内容を明示します。
キーワードは、3〜5個の関連性が高いものを選ぶとよいでしょう。
YouTube Studioの基本情報から設定可能です。
キーワードをテーマにして動画を作成する
適切なキーワードを調査できれば、YouTubeチャンネル自体の方針が決めやすくなります。
市場やトレンドをリサーチし、その中で適切なキーワードを選定することは、ターゲットとする視聴者層に対して、彼らが本当に求めているコンテンツを提供するためには欠かせません。
YouTubeで成功するためには、自分が発信したいことではなくキーワードを軸に動画企画を行い、視聴者が求める情報やエンターテインメントを提供し続けるチャンネルを目指すことが大切です。
YouTubeのキーワード以外に必要な動画SEO対策

YouTubeのキーワード以外でも、動画SEO対策のために必要な5つのポイントを紹介します。
- 平均再生率が上がる工夫をする
- 視聴者との交流(インタラクション)を促す
- タイムスタンプ機能を使用する
- 終了画面を設定する
- 字幕エディタを利用する
それぞれのポイントについて、どのような意味があり、どのように活用するのが効果的なのか見ていきましょう。
平均再生率が上がる工夫をする
動画の成功を左右する平均再生率は、視聴者が視聴を続ける時間の割合を指します。
平均再生率を上げるためには以下の3つが重要です。
- サムネイル・タイトル・内容の一貫性
- 冒頭の15秒〜30秒の工夫
- 適切な音楽やBGM
- 視聴者への問いかけ
サムネイルとタイトルは視聴者がクリックするかどうかの決め手になるため、内容とのギャップがないように心がけましょう。
また、動画の冒頭は視聴者が最も注目するポイントのため、興味を引きつける工夫が求められます。
適切なBGMや問いかけは、視聴者が心地よく視聴したり、飽きさせなかったりするために重要です。
それぞれを意識することで、平均再生率を高めることができるでしょう。
視聴者との交流(インタラクション)を促す
視聴者との交流、特にコメント機能を通じたコミュニケーションは、動画の活性化に欠かせません。
積極的な交流は視聴者に好印象を与え、YouTube側にも動画へのエンゲージメントとして評価されます。
例えば、動画内で視聴者に質問を投げかけたり、アンケートを実施したりしてコメントを誘う工夫をします。
いずれも視聴者の参加意欲を刺激し、お互いにとってメリットのある状況を作り出すものです。
YouTubeは視聴者との交流のある動画を好む傾向があるため、視聴者と積極的に関わることは動画の評価アップにつながります。
タイムスタンプ機能を使用する
タイムスタンプ機能は、視聴者に見たい部分へのアクセスを容易にし、動画の利便性を高めます。
設定方法は簡単で、概要欄に「0:00 今日のトピック」などの時間とタイトルを記入すれば完了です。で
また、タイムスタンプ機能の導入は、キーワードを自然にに盛り込む機会になったり、、Google検索上で動画を目立ちやすくなったりなどのメリットもあります。
さらに動画内にチャプター機能を入れたいのであれば、次の3つの条件をクリアしましょう。
- 最初のタイムスタンプが 00:00 で始まるようにする
- 3つ以上のタイムスタンプを昇順で記入する
- チャプターの最短の長さは10秒にする
タイムスタンプ機能やチャプター機能を活用することで、より視聴しやすい動画を提供できます。
終了画面を設定する
動画の最後には終了画面を設定して、他の動画への視聴やチャンネル登録を促すことが大切です。
動画を最後まで見たユーザーは、内容に興味を持っていることが多いため、そうした視聴者を逃さないように工夫します。
例えば、人気のある動画や関連する動画を推薦したり、チャンネル登録を促すメッセージを入れたりすることが効果的です。
それにより視聴者が自然に次のアクションを起こしやすくなります。
字幕エディタを利用する
YouTubeの字幕機能は、視聴者の利便性を向上させるとともに、SEO対策にも役立ちます。
YouTube公式が字幕エディタの利用を推奨していることから、動画を評価してもらいやすくなるからです。
字幕を設定するには時間がかかりますが、多言語字幕を提供することで世界中の視聴者にアクセスしやすくなり、再生数の増加が見込めます。
また、動画の内容を正確に伝えるためにも、字幕は非常に有効です。
YouTubeで成功し収益化したいなら動画SEOを意識しよう
今回はYouTubeを収益化するためのキーワードの設定と動画SEO活用についてについてお伝えしました。
収益化を目指すなら、以下の要点を押さえましょう。
- まずは正しくキーワードを調査する
- キーワードを軸に視聴者が求めているコンテンツを作成する収益化にはキーワード設定以外の動画SEOも重要
しかし、動画コンテンツは数多く存在し、競争が激しいため常にトレンドを追い続ける必要があり、収益化するためにはキーワード設定以外の動画SEO対策も必要です。
YouTubeを収益化したい場合は、NOGICへお任せください。
具体的なアドバイスやサポートが必要な方は、無料の診断を受けることもできます。詳しくは、以下のページをご覧ください。
自社サービスの宣伝や消費者への商品訴求を行う際に、YouTuberの起用を考えたことがある方も多いのではないでしょうか。
人気があるYouTuberに、YouTuber自身のチャンネル内で自社商品を紹介してもらうことで、狙った年齢層へのリーチや、再生回数を伸ばすことが可能です。
一方で、費用面やキャスティングするYouTuberの選定など、頭を悩ませる要素も少なくありません。
こうした課題を解決すべく、本記事ではYouTuberをキャスティングするメリットや注意点、かかる費用やキャスティングの進め方について解説します。
本記事を参考にして、YouTubeチャンネルの成長と目的達成に役立ててください。
YouTuberをキャスティングするメリット5つ

YouTuberをキャスティングするメリットについて解説します。
- 狙った年齢層にリーチしやすい
- 特定の属性をもったユーザーをターゲティングしやすい
- 動画制作のプロに依頼できる
- 再生回数が伸びやすい
- SNSによる二次的な拡散も期待できる
それぞれのメリットを詳しく解説します。
メリット①:狙った年齢層にリーチしやすい
まずYouTuberをキャスティングすることにより、狙った年齢層にリーチしやすくなります。
YouTube公式によると、YouTubeは18歳から34歳の若者層が最も多く利用しており、他のメディアと比べても圧倒的な利用率を誇っています。
また総務省の調査によれば、全年代の利用割合は88.2%と非常に高く、あらゆる年齢層に対応していることも特徴です。
|
項目 |
調査利用率 |
|
10代 |
97.2% |
|
20代 |
97.7% |
|
30代 |
96.8% |
|
40代 |
93.5% |
|
50代 |
82.8% |
|
60代 |
68.1% |
|
全年代 |
88.2% |
そのため、YouTuberが確立しているフォロワー・コミュニティーに訴求できれば、狙った年齢層へ的確なアプローチが可能になるでしょう。
メリット②:特定の属性をもったユーザーをターゲティングしやすい
YouTuberのキャスティングは、特定の属性を持った視聴者を的確に狙いたい際にも役立ちます。
YouTuberは、個人が中心となりコンテンツを発信しているものがほとんどです。
そのため、その個性やライフスタイルが多くのフォロワーたちにとって共感の対象となり、特有のコミュニティを形成しています。
その結果、例えば以下のように様々な属性に基づいて対象を絞り込めるのです。
- 性別
- 年収
- 趣味・関心事
- 世帯構成(子どもの有無等)
これにより、特定の趣味、興味、生活様式を持つユーザーグループに対して高精度なターゲティングが行えるでしょう。
メリット③:動画制作のプロに依頼できる
動画制作のプロであるYouTuberは、高品質なコンテンツを作成し視聴者を魅了するための技術を持っています。
企業が自社で同様の品質を出すためには、プロのビデオグラファー、エディター、作家を雇い、高額な機材を取りそろえなければなりません。
一方、人気YouTuberは既にそれらをそろえており、企業は彼らと協力することでそれぞれを短期間かつ効率的に利用可能となるわけです。
さらに、彼らのコンテンツはすでに大きな支持を集めており、何が視聴者を惹きつけるのかを知り尽くしています。
そのため、YouTuberが保有する実績と経験を通じて、企業は多くの視聴者に受ける動画を着実に作成できます。
メリット④:再生回数が伸びやすい
YouTuberが参加している動画は、再生回数が急激に増加する傾向も見られます。
保有する大きなファンベースにより、瞬時に拡散される可能性を秘めているためです。
この仕組みを通じて、キャンペーンや商品の露出は最小限であっても最大限に拡大し、結果として次のメリットが得られることになります。
- ファンの結びつきの強さを活用したマーケティングの効果性向上
- 同じコストでより多くの視聴者にリーチ
- YouTuberの社会的証拠と影響力を活用したブランディング強化
- 興味のない層へのアプローチ
YouTuberが提供する高いレベルの拡散は、企業が大規模な予算を投じなければ達成することが困難です。
コストの効率化が望まれる中、YouTuberのキャスティングは特に価値ある選択と言えるでしょう。
メリット⑤:SNSによる二次的な拡散も期待できる
先ほども触れたように、YouTuberの動画コンテンツは、インスタグラムやXなどの様々なSNSプラットフォームで拡散されやすい特徴があります。
SNSは、ユーザー間のコミュニケーションツールとして広く利用されているものです。
そして一人のユーザーが気に入った動画を公開するだけで、そのユーザーの友人やフォロワーに即座に情報が伝わることになります。
またトレンドに敏感なSNSユーザー達は新しい動画を発掘し、見つけ次第すぐに友人たちと共有する傾向も見られます。
その結果、想定以上の拡散とリーチを実現できることもあるでしょう。
ただし、拡散を狙う場合は各SNSの特徴を踏まえた投稿を心がけてください。
YouTuberのキャスティングにかかる主な費用3つ

YouTuberのキャスティングにかかる主な費用は、以下の3つです。
- YouTuberの出演料
- 動画編集にかかる費用
- その他の諸費用
それぞれ見ていきましょう。
費用①:YouTuberの出演料
出演料はYouTuberの知名度やチャンネルの登録者数に左右されるため、相場は一概には言えません。
ただしタイアップ動画では、チャンネル登録者数に応じて出演料が計算される傾向にあります。
例えば、以下のような出演料が一つの目安です。
|
タイプ |
期間 |
相場 |
|
WEB広告出演 |
3か月 |
数万〜数十万円 |
|
WEB広告出演 |
1年 |
数十万〜数百万円 |
|
タイアップ動画 |
– |
登録者数×2〜4円 |
話題性のあるYouTuberを起用する場合は、それだけ高額になることを予測しておきましょう。
費用②:動画編集にかかる費用
動画コンテンツを制作する場合、動画編集の費用もかかります。
プロに編集を求める場合、そのスキルに応じた対価が必要です。
特にYouTuberの品質に準じた動画を求める場合、チャンネルでの編集スタイルを理解し、それを踏襲するために編集者に追加で費用がかかる可能性があるでしょう。
編集作業は手間と時間を要するため、費用はそれに比例して高くなる傾向にあります。
自社の商品やサービスをクオリティ高く紹介するためにも、予算内で最適な編集費用を見込むことが必要です。
費用③:その他の諸費用
YouTuberのキャスティング全体にかかる費用を考えるとき、撮影場所や小道具にかかる諸費用も重要です。
撮影場所としては、例えばスタジオ利用料や外部ロケ地の費用がかかります。
また小道具や装飾品の予算、YouTuberが外部から来る場合にかかる交通費や宿泊費も計上する必要があるでしょう。
それぞれの諸費用は案件によって異なるため、事前に詳細な計画を立て、見積もりを取ることが大切です。
YouTuberをキャスティングする場合の注意点

YouTuberのキャスティングは、注意深く行う必要があります。
本章では、以下2つのケースについて解説します。
- YouTuberに自身のチャンネル内でサービス紹介してもらうケース
- 自社チャンネル内でサービスを紹介してもらうケース
以下でそれぞれ詳細に解説するので、ぜひ参考にしてください。
YouTuberに自身のチャンネル内でサービス紹介してもらうケース
まず企業のターゲットオーディエンスと異なるYouTuberを選択した場合です。
企業イメージと異なるキャラクターや価値観を持つYouTuberが関与すると、企業の信頼性やブランド価値を損ねるリスクが生じます。
一度ブランド価値を損ねてしまうと、既存のファンも離れてしまう可能性があるため注意が必要です。
キャスティングするYouTuberによって、企業へのリターンが大きく変わるため、選定作業は慎重かつ戦略的に行いましょう。
自社チャンネル内でサービスを紹介してもらうケース
自社チャンネルのターゲット層とYouTuberのターゲット層がズレていると、YouTubeのアルゴリズム上望まないターゲット層にコンテンツが配信されてしまう可能性があります。
チャンネルの活性化に悪影響を及ぼす可能性があるのです。
具体的な失敗事例を紹介します。同じ美容ジャンルでも、ターゲットとする年齢層が異なるYouTuberとのコラボでの失敗例です。
- 若い世代をターゲットとした美容ジャンルアカウントが、中年層に影響力を持つ美容系インフルエンサーとコラボを行った結果、コンテンツでミスマッチを起こしてしまった。
- コラボ以前は、ニキビケアや二重アイテムの動画で再生回数1,000回を超えていたのが、コラボ相手の年齢層に合わせた「しわケア」を扱ってしまったことで、再生回数が300回以下に落ち込んでしまった。
この失敗例は、YouTubeにおける正しいターゲット層の理解とマッチングの重要性を示しています。
ターゲット層のニーズを満たすコンテンツ作りが、視聴者の関心を引き続き維持するうえで重要です。
また、ジャンル選定だけではなく、年齢層を含む具体的なターゲットの分析も不可欠でしょう。
幅広い共感を呼ぶには視聴者層とコンテンツの親和性に着目して、キャスティングを行う必要があります。
キャスティング候補を探す際のチェックポイント2つ

YouTuberのキャスティングを行う際、特に重要なチェックポイントが2つあります。
- 狙いたいターゲット層にリーチできるか
- 影響力はあるのか
2つのポイントを押さえて、効果的なYouTuberキャスティングを目指しましょう。
チェックポイント①:狙いたいターゲット層にリーチできるか
まず1つめのポイントは、狙いたいターゲット層にリーチできるかどうかです。
キャスティング候補を探す際には、自社サービスの内容・ブランドイメージに合わせて、どのような視聴者を獲得したいのかを明確にしましょう。
そして、その視聴者が好む動画のイメージやジャンルを考えます。
同じジャンルでも、動画のスタイルやトーンが異なれば視聴者の反応も変わってきます。
そのため、同ジャンルで影響力があるからと言って安易に選ばないことが大切です。
狙いたいターゲット層にリーチできるかどうかを判断するためには、以下の2つを意識するとよいでしょう。
- どういう動画を好んで見る視聴者を獲得したいのかを考える
- イメージに近い動画で再生回数を出しているチャンネルをピックアップする
それぞれ詳しく解説します。
どういう動画を好んで見る視聴者を獲得したいのかを考える
まず、どういう動画を好んで見る視聴者を獲得したいのかを考えることが重要です。
自社ブランドのイメージに沿って、どのような層にアプローチしたいのかを決める必要があります。
例えば、自社サービスが教育系であれば、知識やスキルを学びたいと思っている人や、自己啓発に興味がある人などがターゲット層です。
この場合は、分かりやすくて信頼感のある動画や、実践的で役立つ情報が盛り込まれた動画などが好まれます。
動画の傾向などを分析し、どのような視聴者を獲得したいのかしっかり検討しましょう。
イメージに近い動画で再生回数を出しているチャンネルをピックアップする
次に、自社ブランドのイメージに近い動画で再生回数を出しているチャンネルをピックアップすることです。
自社が狙っているターゲット層と同じような視聴者を持っているチャンネルを探すことで、リーチ対象にズレが生じません。
また、動画イメージが近ければ、その後の交渉や動画の完成度も高くなります。
例えば、自社のサービスが教育系であれば、「○○さんの仕事術」などのチャンネルが候補となるでしょう。
チェックポイント②:影響力はあるのか
2つめのポイントは、影響力はあるのかどうかです。
キャスティング候補を探す際には、単に再生回数が多いからと言って選ぶのではなく、影響力があるかどうかをチェックするとよいでしょう。
影響力とは、視聴者に対して何らかの行動や感情を促す力のことです。
例えば動画を見た後に視聴者に商品を購入してもらったり、サービスに登録してもらったりできれば、影響力があると言えるでしょう。
影響力がある人ほど、自分のチャンネルの認知度や信頼度を高められます。
影響力は、以下の3つの方法で測ることが可能です。
- 平均再生回数を確認する
- 動画のコメントを確認する
- 他のSNSも確認する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
平均再生回数を確認する
まず、平均再生回数を確認する方法です。
公開動画のいくつかが伸びているだけでなく、全体的に再生回数が多いかどうかに着目します。
影響力がある人のチャンネルほど、視聴者は動画の中身より人を見にくるため、平均再生回数が高い人はインフルエンス力が高いと言えるのです。
動画のコメントを確認する
次に、動画のコメントを確認する方法です。
視聴者からどういう風な見られ方をしているのかを確認します。
例えばアンチコメントや、視聴者からの指摘コメントが多い人は避けたほうがよいでしょう。
そういった人は信用度が低かったり、不満を持たれていたりする可能性があるからです。
その一方で「いつも理解しやすい」や「参考になる」といった肯定的なコメントをよく受けている人は、信頼できると考えられます。
他のSNSも確認する
最後に、他のSNSも確認することをおすすめします。
他のSNSの投稿に対しても多くのいいねやコメントがついていれば、視聴者がその人に対して好感や共感を持っていると言えるからです。
他のSNSでも人気を集めている人は、影響力があると言えるでしょう。
また複数のプラットフォームでの活動や支持は、より広い影響を示すため、異なる視聴者層へのアプローチも可能です。
YouTuberとのキャスティングを進める流れ【7ステップ】

YouTuberのキャスティングを進める際は、正確な流れを理解し、適切なキャスティングと効率的な商材のアピールが不可欠です。
YouTuberのキャスティングを進める具体的な流れは以下の7ステップです。
- 連絡方法の確認
- 打ち合わせの依頼
- 打ち合わせ
- 案件の詳細を伝える
- 案件自体に興味があるのかを確認する
- スケジュール通りに進行可能かを確認する
- 予算内でやってもらえるかを確認する
- 直近のアナリティクスを見せてもらえるかを確認する
- 類似案件の実績を確認する
- 他SNSでの拡散も予算内で可能かを確認する
- キャスティングするYouTuberの選定
- 詳細の交渉
- 契約(契約書を取り交わす)
- 案件の進行
各ステップは目標達成に不可欠であり、特に契約前の内容のすり合わせは後々のトラブルを防ぐために重要です。
適切なキャスティング、効果的なマーケティングを実現するためにも、それぞれのステップをしっかり押さえておきましょう。
ステップ①:連絡方法の確認
キャスティングを成功させるための最初のステップは、連絡方法の確認です。
YouTuberの連絡先を探すところから始めましょう。
多くのYouTuberは連絡先を公開しています。
連絡先が公式のWebサイト、YouTubeチャンネルの説明セクション、もしくはSNSプロフィールに載っていないか確認してみましょう。
なお連絡先が見つからない場合には、代替手段としてSNSでのダイレクトメッセージ(DM)を利用します。
例えば、InstagramやTwitterのDMです。
連絡を取る際は、相手への敬意を忘れずに礼儀正しく行いましょう。
また、事前にこちら側のプロフィールや企画内容を明確にしておくことで、YouTuberからの信頼を得やすくなります。
ステップ②:打ち合わせの依頼
次に、打ち合わせをお願いするステップです。
打ち合わせの依頼をする際には、案件の概略を伝えると同時に、対面またはオンラインでの詳細な打ち合わせをお願いしましょう。
この時点で、プロジェクトの期待値や意図する方向性などを簡潔に述べて、YouTuberの興味を引くことが大切です。
コミュニケーションを通じて案件についての理解を深め、相互の期待が合致するよう努めましょう。
初回のコンタクトは信頼関係の構築にもつながるため、丁寧かつ具体的なアプローチを心がけてください。
ステップ③:打ち合わせ
打ち合わせでは、以下の7つの情報を伝える必要があります。
- 案件の詳細を伝える
- 案件自体に興味があるのかを確認する
- スケジュール通りに進行可能かを確認する
- 予算内でやってもらえるかを確認する
- 直近のアナリティクスを見せてもらえるかを確認する
- 類似案件の実績を確認する
- 他SNSでの拡散も予算内で可能かを確認する
情報をしっかりと整理し、相手がマネージャー不在でも迅速に回答を得られるよう調整することが大切です。
案件の詳細を伝える
案件の詳細を伝える際は、プロジェクトの目的、目指す成果、狙うターゲット層、期待するアウトカムなどを包括的に説明します。
可能であれば、案件の背景や目標市場、キャンペーンの期間、期待される貢献なども詳細に伝えます。
これにより、相手が案件について詳しく理解し、具体的なビジョンを持って参加できるでしょう。
また、案件に関連する特別な要求や特定の制限事項があれば、それも明確に伝える必要があります。
案件自体に興味があるのかを確認する
次に、キャスティング候補に案件への興味や関心を持っているかどうかを確認しましょう。
その人が、プロジェクトにどれだけ熱意を持って取り組むかを判断する上で重要です。
例えば、候補者が案件の内容や目標に対して興味を示し、それに対する質問や提案を持っているかどうかで見極めます。
これにより、ただの仕事としてではなく、より積極的で創造的なアプローチを取る可能性があるかどうかを評価できるでしょう。
また、候補者の価値観や目標が案件の目的と一致しているかどうかも確認可能です。
スケジュール通りに進行可能かを確認する
さらに、案件がスケジュール通りに進行できるかどうかも確認します。
具体的には、案件のタイムライン、重要なマイルストーン、期限などについて話し合いましょう。
また、候補者が他に抱えている案件や予定されている活動が、プロジェクトのスケジュールにどのような影響を与えるかを理解することも重要です。
プロジェクトの進行に影響を与える可能性のある障害や制約を早期に特定し、それらに対処するための計画も立てておくと安心でしょう。
予算内でやってもらえるかを確認する
また、キャスティング候補者に予算内での対応が可能かどうかを確認することが不可欠です。
具体的な金額や支払い条件を初期段階で話し合うことで、後々の誤解やトラブルを避けることができます。
可能であれば、予算の制約内で最大限の価値を得るために、候補者がどのようなクリエイティブな提案や効率的な解決策を提供できるかも見ると良いでしょう。
直近のアナリティクスを見せてもらえるかを確認する
キャスティング候補者の実績と信頼性を正確に評価するためには、直近のアナリティクスデータを見せてもらうことが有効です。
これにより候補者のパフォーマンス、視聴者のエンゲージメント、コンテンツのリーチなどを具体的に把握できます。
またアナリティクスを見せてもらうことで、候補者が過去にどのような成功を収めてきたか、どのターゲット層にリーチしているかなど、重要な情報も得ることが可能です。
こうした情報の透明性と開示は信頼関係構築に不可欠であり、プロジェクトの成功に向けた良好なスタートを切るためにも役立つでしょう。
類似案件の実績を確認する
類似案件での実績を確認することも重要です。
キャスティング候補者が、特定のジャンルやテーマにおいてどれだけの経験と成功を持っているかを調べられます。
また、候補者が過去に手がけた類似のプロジェクトやキャンペーンの結果を見ることで、その能力やクリエイティビティ、対象市場への影響力も評価できるでしょう。
- 候補者が自身のプロジェクトに適しているか
- 必要なスキルや経験を持っているか
などを判断する上で非常に役立ちます。
他SNSでの拡散も予算内で可能かを確認する
最後に、予算内でYouTube以外の他SNSプラットフォームへのコンテンツ拡散が可能かどうかを確認します。
また過去の拡散キャンペーンの成功例や、特定のプラットフォームでの影響力を示す事例を求めることもおすすめです。
加えて、それぞれのプラットフォームに適したコンテンツ戦略やメッセージングをどのように展開するかも話し合う必要があります。
予算内で最大のリーチと影響力を得るために、効果的なマルチプラットフォーム戦略を策定しましょう。
ステップ④:キャスティングするYouTuberの選定
ステップ③までを踏まえて、キャスティングするのに最適なYouTuberを選定します。
複数の候補との打ち合わせをもとに、案件にぴったりのインフルエンサーを見極めましょう。
YouTuberの視聴者層やチャンネルのコンテンツスタイルが、自社の企画と相性が良いかを検討してください。
また、打ち合わせでのコミュニケーションにおける相手の対応の良さや、関心度も重要な選定基準になります。
最終的な判断は案件の成功に大きく影響するため、じっくりと時間をかけて検討しましょう。
ステップ⑤:詳細の交渉
詳細の交渉では、金額、納期、成果物の具体的な内容など、案件の全体像をしっかりと固めます。
提案内容について、より詳細に調整を行い、両者の理解と合意を深めていく段階です。
交渉がスムーズにいかない場合や、相手の対応に疑問を感じることがあれば、別の候補への変更も視野に入れなければなりません。
このステップでの明確な合意は、その後のトラブルを避けるために非常に重要になるため、注意深い対応を心がけましょう。
ステップ⑥:契約(契約書を取り交わす)
YouTuberとの契約は、必ず契約書を取り交わしましょう。
契約書には、具体的な作業範囲や報酬金額、納期など重要な条件を明文化し、両者が同意の上で署名します。
この流れには、後々のトラブルを未然に防ぐために特に注意を払うべきです。
契約書作成段階では法的な知識が求められることもあるため、不明な点があれば専門家に相談することをおすすめします。
ステップ⑦:案件の進行
案件がスケジュール通りに進行するためには、定期的な確認が重要です。
YouTuberに一任するだけではなく、進捗を把握しておくことで、計画通りに案件が進むようにする必要があります。
また、実際の内容に齟齬が生じないよう、コミュニケーションを密に取るとよいでしょう。
案件進行中に生じる疑問や変更点があれば、速やかに話し合い、互いの理解を深めていくことが、案件成功には不可欠です。
YouTuberのキャスティングなどYouTube運営にお困りの人はNOGICに相談
YouTuberのキャスティングは、商品やサービスのプロモーション、自社ブランドの認知拡大において非常に重要です。
しかし、適切なYouTuberを選ぶことは一筋縄ではいきません。
企業が直面する課題として、キャスティング相手の選定の難しさや費用対効果、キャンペーンの成功を左右するマッチングの重要性などが挙げられます。
また、企業のYouTubeチャンネル運営には複数のノウハウが必要であり、専門のマーケティング知識が不可欠です。
NOGICでは、こうしたYouTube運営全般にわたる問題に対し、専門知識および対策を提供しています。
ビジネス視点での集客から訴求、ターゲットに合った動画制作など、YouTubeチャンネルの成長サポートや、教育・研修系サービスのデジタルトランスフォーメーション(DX)を含め、幅広いサポートが可能です。
YouTubeの運営でお困りの際は、ぜひNOGICへご相談ください。
「YouTubeで登録者数を増やしたいけれど、どうすればいいのだろう?」「登録者を買うという方法もあるのかな?」とお悩みではないでしょうか。
実は、YouTubeの登録者を買うことは「可能」です。
しかし、YouTubeの登録者を買う行為は「リスクを伴う」ものです。場合によっては、アカウントを停止されるという厳しいペナルティを受けることにもなりかねません。
そこで本記事では、YouTubeの登録者を買うことの仕組み、値段の相場、およびそれに伴うデメリットを解説します。
規約違反のリスクを回避しながら、チャンネルの成長を促進するための安全かつ効果的なアプローチが知りたい方はぜひ参考にしてください。
YouTubeで登録者を買うことはできる?

まずは、実際に登録者の購入は可能なのか、購入した場合の仕組みや相場について具体的に解説します。
- YouTubeの登録者を買うことは可能
- YouTubeの登録者を買うときの仕組みは?
- YouTubeの登録者を買うときの値段(相場)は?
それぞれ、見ていきましょう。
YouTubeの登録者を買うことは可能
2023年12月時点で、YouTubeの登録者を買うこと自体は可能です。
実際に、インターネット上で登録者購入サービスを提供している業者を見つけることは難しくありません。
また、登録者を購入した人の体験談やブログ記事も見つかります。
YouTubeの登録者を買うときの仕組みは?
YouTube登録者を買う仕組みは、業者が持っている複数のアカウントを利用して、短期間にチャンネルの登録者を増やすという手法です。
具体的には、購入者のチャンネルに業者が持つアカウントが自動的に登録されます。
このとき、購入する登録者の数や増加の速度など、いくつかのオプションを選ぶことができる業者もあるようです。
YouTubeの登録者を買うときの値段(相場)は?
YouTubeの登録者を購入する際の値段(相場)は、業者によって異なりますが、一般的には以下の価格帯になっています。
また、比較のために再生回数を購入できるサービスの相場感についてもまとめました。
|
項目 |
費用 |
|
YouTubeの登録者購入費用 |
1人あたり5〜10円 |
|
再生回数購入費用 |
1万回あたり5,000〜8,000円 |
YouTubeの登録者数や再生回数が伸び悩んでいる場合、安価だと感じる方もいるかもしれません。
しかし登録者の購入はYouTubeのポリシー違反であり、チャンネルが取り消されるなどのペナルティを受ける可能性があります。
次の段落で起こり得るデメリットについて解説しますので、慎重に判断してください。
YouTubeの登録者を買うことで起こり得るデメリット

YouTubeの登録者を買うことで起こり得るデメリットは、以下の通りです。
- 規約違反になってしまう
- ペナルティが課される
- 再生回数につながりにくい
- 元々いる視聴者にバレてしまうこともある
- 運用のノウハウや実力がつかない
それでは、それぞれのデメリットを1つひとつ詳しく見ていきましょう。
デメリット①:規約違反になってしまう
YouTubeには守るべき利用規約が定められているため、運営を行ううえでそれぞれのガイドラインに従うことはもはや必須です。
特に登録者を購入する行為に関しては、下記の通りYouTubeのポリシーに抵触します。
自動システムを使用して、または何の疑いも持たない視聴者に動画を示して、視聴回数、高評価数、コメント数、その他の統計数を人為的に増やそうとする行為は、YouTube では許可されていません。
引用:YouTube ヘルプ「虚偽のエンゲージメントに関するポリシー」
この行為が発覚した場合、事前警告としてYouTubeから運営管理者へ事前警告が行われます。
この警告を軽視して規約違反を続けた場合、チャンネル削除やペナルティを受けるリスクが高まり、事実上チャンネルの運営自体が成り立たなくなる可能性も否定できません。
投資した時間と労力が水の泡になってしまうリスクを回避するためにも、登録者購入という行為は避けることが大切です。
デメリット②:ペナルティが課される
YouTubeの登録者を買うことで、チャンネルの一時停止や完全な削除といった厳しいペナルティが課される場合があります。
具体的には、もし違反警告を90日以内に3回獲得してしまうと、チャンネルへのペナルティが課されるリスクが高まります。
この事態になると、これまでに投じた時間、労力が一瞬にして無駄になってしまうでしょう。
また、たとえ一回の規約違反であっても、特に悪質だと判断された場合は即座にチャンネルが停止決定されることもあります。
そのため、登録者の不正購入によるリスクは非常に大きいと言えるでしょう。
デメリット③:再生回数につながりにくい
購入することでチャンネル登録者数が増えたとしても、それが実際の視聴やエンゲージメントへと繋がることはほとんどありません。
購入した登録者の多くが非アクティブなアカウントやボットによる偽アカウントである場合が多く、意思を持って動画を視聴することはないためです。
その結果、再生回数の増加やエンゲージメントの向上へと結びつかないうえ、YouTubeのおすすめにも表示されにくくなります。
YouTubeのアルゴリズムは、視聴者の満足度を重視するため、単純な登録者数の増加よりも実際に動画を視聴しているユーザー数や再生時間を優先的に評価します。
したがって、購入によって得られたチャンネル登録者数は、マーケティング戦略としても効果が低く、長期的な成功やブランド構築には結びつきません。
デメリット④:元々いる視聴者にバレてしまうこともある
YouTubeの登録者を買うデメリットとして、元々いる視聴者にバレてしまうことも挙げられます。
自動的に登録者数を増加させることは魅力的に見えるかもしれません。
しかし、登録者数が急増してもそれに見合った再生数やエンゲージメントが伴わなければファンや視聴者たちは疑問を持つはずです。
もしその異常に気づかれてしまうと、それまで築いてきた信用やコミュニティ内の立場が失われる可能性もあります。
元々いた視聴者が離れてしまうことにもなりかねないため、登録者を買うことは推奨できません。
デメリット⑤:運用のノウハウや実力がつかない
最後に、本来YouTubeを通じて獲得すべき実力が身に付かず、持続可能なチャンネル運用が困難になることも挙げられます。
YouTuberにとって大切なのは、チャンネルの健全な成長や視聴者とのつながりを大切にしながら、コンテンツを通じて価値を共有し続けることです。
しかし、登録者を購入する行為はこの流れを省略し、短期間で数値を増やすことによって表面的な成功を追求することと同義です。
つまり、健全な運営を通して得られたはずの、ノウハウやコンテンツクリエーションの技術、マーケティングスキルなどのノウハウは獲得できません。
また、YouTubeでは新たなトレンドやアルゴリズムの更新が行われています。
こうした変化に対応するための柔軟性や適応力も養われず、業界内での競争力を失うことにつながります。
YouTubeの登録者を買う方法

YouTubeの登録者は、Google検索などで出てくる業者を利用することで購入可能です。
購入価格は、1登録者あたり5〜10円程度とされています。
しかし、先に挙げたデメリットを考慮すると、絶対に推奨できない行為です。
登録者を買うことで生じるリスクは大きく、YouTubeの運営元に発覚した場合、チャンネルやアカウントの停止に追い込まれることも珍しくありません。
また、なかには詐欺まがいの業者も存在するため、お金を払ってもチャンネル登録者数が増えないという事態も考えられます。
それぞれのデメリットを理解したうえで、もしどうしても購入を考える場合は注意深く業者を選ぶ必要がありますが、健全な運用を心がけるのが最良です。
購入以外でYouTubeの登録者を増やす方法

ここからは、購入以外でYouTubeの登録者を増やすための具体的な方法を3つ紹介します。
- 専門性の高いチャンネルを作る
- SEO対策に力を入れる
- コンサルや運用代行サービスを利用する
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
登録者を増やす方法①:専門性の高いチャンネルを作る
YouTubeで登録者を増やすためには、まずターゲットを明確にして、視聴者に求められる専門性の高いコンテンツを投稿することが大切です。
そのジャンルに関して深く掘り下げた専門性の高い動画を投稿することで、視聴者の興味やニーズに応えることができるためです。
またテーマを統一することでチャンネルの内容が視聴者に理解されやすくなるため、登録者数の増加に期待できます。
登録者を増やす方法②:VSEO対策に力を入れる
より多くの視聴者に自分の動画を見つけてもらうために、VSEO対策は必要不可欠です。
具体的には、キーワードを研究して動画のタイトル、説明文、タグで適切に使うことがポイントです。
これによりYouTubeの検索結果で上位に表示されやすくなり、新規登録者獲得につながる可能性が高まります。
また、視聴者が関連する内容を検索した際にも動画が表示されやすくなります。
YouTubeのSEOについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。
参考:YouTubeで上位表示を目指すならSEO!具体的なSEO対策を全て解説
登録者を増やす方法③:コンサルや運用代行サービスを利用する
専門家の知識やサポートを得るために、コンサルや運用代行サービスを利用するのも有効な手段です。
「明確なターゲットが定まらない」「YouTubeの運用にリソースを割くことが難しい」「注力しているのになかなか成果が出ない」という場合などは、特に検討する価値があるでしょう。
プロから運用方法を学んだり、サポートを受けたりすることで効果的な戦略を立てられるようになり、結果的に登録者数の増加が見込める可能性があります。
また、コンサルタントや運用代行サービスの利用を通してチャンネルの成長に必要なノウハウや技術を身に付けられるため、ゆくゆくは自社や個人での運用も安定するでしょう。
YouTubeの運用代行サービスを検討している方は、以下の記事を参考にしてください。
参考:Youtube運用代行会社の相場について紹介!運用会社を使うメリットも徹底解説
YouTubeの登録者購入に関するよくある質問

最後に、YouTubeの登録者購入に関するよくある質問へ回答します。
- YouTubeの登録者を買うとどうなる?
- 実際に登録者を買っているYouTuberはいる?
ぜひ参考にしてください。
YouTubeの登録者を買うとどうなる?
YouTubeの登録者を購入すると、一時的に登録者数を増やすことができます。
ただし、この行為はYouTubeの規約に違反するため、チャンネルやアカウントの停止など厳しいペナルティを受けるリスクも高いです。
また、購入した登録者は非アクティブなアカウントや偽アカウントであるため、再生回数やチャンネルへのエンゲージメントにはほとんど貢献せず、本来求めている成果は上がりません。
さらに、なかには料金を払っても登録者数が全く増えない詐欺にあうケースも存在します。
実際に登録者を買っているYouTuberはいる?
業者が存在すること、またYouTube側が規約違反だと明示していることから、実際に登録者を購入するYouTuberも存在することが予想されます。
しかし、購入のデメリットが非常に大きいため、真に価値のあるYouTubeチャンネルを運営するうえで、登録者の購入はおすすめできません。
クリック率や再生回数向上のためのVSEO対策など、正当な手法でのマーケティング努力がYouTubeチャンネルの健全な成長には必要不可欠です。
YouTubeで登録者を買うのはNG!堅実な運用を心がけよう
今回の記事の要点をまとめると、以下のとおりです。
- YouTubeの登録者を買うことは技術的に可能だが、規約違反であるためペナルティが課されるリスクがある
- 購入した登録者が動画を視聴することはないため、チャンネルの健全な成長につながらない
- 登録者数を増やすためには適切なVSEO対策や専門性の高いコンテンツを作ることが大切
真に価値のあるチャンネルを育てるためには、専門性とVSEO対策を核とした正しい運用が必要です。
NOGICでは、無料のチャンネル診断から、適切な運用までトータルでサポートいたします。
サービスについての詳細やお問い合わせは、こちらのページからご確認ください。
また、NOGICのサービスについて深く知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
参考:失敗したYouTube企業チャンネルから成功へと導くNOGIC
「YouTubeのハッシュタグのつけ方がわからない!」
「YouTubeのハッシュタグにはどんな効果があるの?」
YouTubeに動画を上げようとした際、このようなお悩みでお困りの方が多いのではないでしょうか。
この記事では、YouTubeのハッシュタグのつけ方からどういった効果があるのか徹底解説します。
後半にはおすすめのハッシュタグや人気のハッシュタグの探し方もご紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。
YouTubeのハッシュタグとは?

YouTubeのハッシュタグとは、動画のタイトルや説明へ入力するキーワードのことです。
ハッシュタグには以下の特徴があります。
- キーワードと動画の関連性を高める
- 最新の投稿が優先されるため新参者でも露出を得られる
- ユーザーが興味のあるカテゴリの動画を簡単に検索できる
ハッシュタグをつけることで、動画が検索結果や関連動画に上位表示されやすくなり、再生回数の増加に繋がります。
また、入力されたハッシュタグは青い文字で掲載され、クリックすると同じタグを付けた他の動画を検索結果として表示します。
YouTubeのハッシュタグの意味
YouTubeのハッシュタグは、動画に関連するキーワードの先頭に「#」を付けて表現されるラベルの意味があります。
視聴者は、ハッシュタグをクリックすると関連する動画を検索可能です。例えば、音楽関連の動画の場合、#JPOPや#ライブといったハッシュタグを付けることが多いです。
ハッシュタグにより動画はより見つけやすくなり、再生回数の増加に繋がることも期待できます。
YouTubeのタグ(メタタグ)とハッシュタグの違いは?
YouTubeで使われるタグ(メタタグ)とハッシュタグには明確な違いがあります。
| 特徴 | タグ | ハッシュタグ |
| 目的 | YouTubeアルゴリズム向け | ユーザーへの伝達 |
| 設定場所 | 説明欄下のタグ欄 | 説明欄 |
| 最適な数 | 10〜15個以内 | 3〜5個前後 |
| 掲載 | 掲載されない | タイトル・説明欄に青字で掲載 |
タグは主にYouTubeのアルゴリズムを対象に、動画の内容やジャンルを伝えるために用いられる要素です。
一方、ハッシュタグは視聴者に動画の主要なポイントを伝えるために使用され、動画の説明欄に入れる方法です。
YouTubeにおけるハッシュタグの上手なつけ方コツ4つ
YouTubeにおけるハッシュタグの上手な付け方について4つのコツを紹介します。
- ビッグキーワード、人気のキーワードを入れる
- オリジナルのキーワードを作成する
- 抽象的なキーワードを入れる
- 重要なキーワードを先に入れる
各項目について、その重要性と具体的なアプローチ方法について詳しく説明します。
ビッグキーワード、人気のキーワードを入れる
ハッシュタグには、ビッグキーワードや人気のキーワードを入れることが大切です。
多くの視聴者が検索するため、チャンネルへの流入を見込むことができます。
例えば、「ダンス」や「歌ってみた」などは一般的なジャンルを示すビッグキーワードです。
また、流行の曲名や話題の事象は人気キーワードとして潜在的な視聴者に閲覧されやすくなります。
この方法で視聴者の間で関心の高い内容やトレンドに乗っかることが重要です。
オリジナルのキーワードを作成する
また、オリジナルのキーワードを作成し、それをハッシュタグとして活用するのも良いでしょう。
なぜなら、YouTubeチャンネルの独自性と、ブランドアイデンティティを際立たせるために役立つからです。
例えば、チャンネル名や提供する独特な動画シリーズの名前など、個性的で記憶に残りやすいキーワードを考案します。
このようにオリジナルのキーワードを用いることで、視聴者がチャンネルとそのコンテンツを直接的に関連付けることが可能です。
抽象的なキーワードを入れる
YouTubeでのハッシュタグ戦略では、抽象的なキーワードの使用も必要です。
例えば、「かっこいい」、「簡単」、「きれい」といったキーワードは、特定の感情や価値観を共有する視聴者層の関心を惹きつけられます。
また、抽象的なキーワードは、視聴者の感覚や感情に直接訴えかけることができ、様々な趣味・興味を持つ視聴者層にアピールできるでしょう。
重要なキーワードを先に入れる
最後に、YouTube動画のハッシュタグ設定では、動画の内容と最も密接に関連するビックキーワードを先頭に置きます。
それにより、動画のジャンルが一目で明確になり、視聴者が自分の興味やニーズに合ったコンテンツをより迅速に見つけることが可能です。
例えば、料理に関する動画では「レシピ」、旅行系の動画では「旅行ガイド」といった、動画の核となるテーマを示すキーワードを最初に設定します。
結果、視聴者はすぐに動画の主旨を理解し、自分が求めている情報に素早くアクセスできるでしょう。
YouTubeにハッシュタグを利用するメリット3つ

YouTubeにハッシュタグを利用するメリットは、以下の3つです。
- 再生回数が増える
- 関連動画の再生数が増える
- 新規の視聴者が獲得できる
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
再生回数が増える
ハッシュタグを活用すると、検索に引っかかりやすくなり、多くの視聴者が動画を見つけるチャンスも増加します。
なぜなら、YouTubeの検索アルゴリズムはハッシュタグの情報を利用して動画をカテゴライズし、検索結果に掲載しているからです。
その結果、関心を持つ視聴者が動画にアクセスしやすくなるため、自然と再生回数が増えます。
さらに、動画の内容を正確に示した適切なハッシュタグの選定は、見たい内容がマッチするユーザーに届きやすいです。
また、VSEO対策としても重要であり、YouTubeだけでなく、Google検索結果においても動画の掲載頻度を高めることが可能です。
関連動画の再生数が増える
YouTubeでは、視聴中の動画と関連性の高い動画を推薦として掲載する機能があります。
ハッシュタグを使用すると関連性が高いと認識され、視聴者が次に見るべき内容として動画が推薦される可能性も高いでしょう。
その結果、視聴者を関連動画に誘導しやすくなり、チャンネル全体の再生数アップに貢献できます。
また、動画同士がハッシュタグで紐づけられることによって、関連性を持たせたコンテンツ戦略の展開も可能です。
新規の視聴者が獲得できる
特定のハッシュタグを使うことで、そのキーワードに興味がある新規の視聴者を獲得できます。
なぜなら、同じ興味を持ったユーザーがハッシュタグから流入するのに役立つためです。
例えば、特定のテーマで動画を投稿している場合、関連するハッシュタグを使うことで、そのテーマに関心のあるユーザーが動画を発見しやすくなります。
同ジャンルの動画でハッシュタグを通じた新規の視聴者の流入は、チャンネルの発展に不可欠です。
YouTubeにハッシュタグを使用するデメリット2つ

YouTubeのハッシュタグ利用における2つのデメリットについて、これから詳しく紹介します。
- 視聴者が離脱してしまう可能性
- すぐに再生回数に結びつかない
それでは、それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。
視聴者が離脱してしまう可能性
注意すべき1つ目は、視聴者が動画から離脱してしまう可能性があることです。
例えば、動画のハッシュタグをクリックした視聴者は、他の類似コンテンツに興味を持ち、そちらの動画へと移動してしまう場合があります。
特に、人気の高いハッシュタグを使用した場合、大量に存在する関連動画の中に自分のチャンネルが埋もれてしまうリスクもあるでしょう。
これにより、視聴者が自分のチャンネルに留まる可能性が下がるかもしれません。
動画のタイトルや内容と関連したハッシュタグを選び、視聴者が動画の最後まで関心を持ちやすいように工夫が大切です。
すぐに再生回数に結びつかない
ハッシュタグを適切に使用した場合であっても、直接的に再生回数の向上に結びつくとは限りません。
もちろん、SEO(検索エンジン最適化)に間接的な影響を与える可能性はあります。
しかし、ハッシュタグからの流入が中心ではないため、視聴者が自分の動画にたどり着くまでにはある一定の期間が必要です。
ただし、時間経過によって再生数が伸びる可能性もあるため、ハッシュタグの効果は中長期的に評価する必要があるでしょう。
YouTubeハッシュタグにおすすめ・人気なタグの探し方

YouTubeハッシュタグにおすすめ・人気なタグの探し方は、以下のとおりです。
- 人気動画のハッシュタグを参考にする
- GoogleトレンドでYouTube検索からトピックを検索する
- YouTubeのサジェストキーワードを使う
それぞれのテーマについて、詳しく解説します。
人気動画のハッシュタグを参考にする
YouTubeで成功している動画は、多くの視聴者に支持されており、そのハッシュタグの選び方は非常に参考になります。
まずは同じジャンルの人気動画をピックアップし、その動画が使用しているハッシュタグや説明文の単語をリストアップしてみましょう。
人気動画のハッシュタグは多くのユーザーにクリックされる可能性を秘めており、動画の露出を高める可能性があります。
ただし、15個以上のハッシュタグは無効になることもあるため、3~5個程度の選定がおすすめです。
GoogleトレンドでYouTube検索からトピックを検索する
YouTubeのトレンドを確認する際には、GoogleトレンドのYouTube検索機能の活用がおすすめです。
Googleトレンドは、検索トレンドを分析するのに非常に便利な無料ツールで、どのような単語が注目を集めているかを簡単に調べられます。
そのなかから、ビッグキーワードを中心に、最近の検索傾向や人気の話題を押さえたキーワードからハッシュタグを選びましょう。
このようにトレンドに合わせたハッシュタグを使用できれば、より多くの視聴者を自分の動画に誘導することが可能です。
YouTubeのサジェストキーワードを使う
サジェストキーワードとはYouTubeの検索窓に関連する単語を入力した際に検索窓の下に掲載される関連するキーワードのことです。
キーワードは、日々のユーザーの検索傾向を反映しており、多くのYouTubeユーザーが既に関心を持っているテーマやキーワードになります。
サジェストキーワードは、ハッシュタグとして採用すると、そのキーワードに関心が高い視聴者が適した動画にたどり着きやすいです。
また、競合の他の動画と異なるアングルでサジェストされたキーワードを選ぶことによって、独自性のあるハッシュタグを作り出すこともできます。
そのため、YouTubeのサジェストキーワード機能を活用して、効果的なハッシュタグを見つけ出すせるでしょう。
YouTubeのハッシュタグに関する5個の注意点

これから、YouTubeに関する重要なハッシュタグの使い方について5つのポイントを紹介します。
- ハッシュタグは動画と関連性の高いものにする
- ハッシュタグ「♯」は小文字・半角にする
- ハッシュタグの単語間にスペースは入れない
- ハッシュタグの個数は3個以上15個以下にする
- YouTubeのポリシーを遵守して禁止ワードは使わない
それぞれのポイントについて詳しく解説していきましょう。
ハッシュタグは動画と関連性の高いものにする
ハッシュタグは、動画の内容やテーマに密接に関連している必要があります。
なぜなら、動画の内容を正確に反映していないハッシュタグは、ユーザーに誤解を招くだけでなく、YouTubeの検索結果にも悪影響を及ぼす可能性があるためです。
例えば、動画が料理のレシピに関する内容であれば、「#料理」「#レシピ」「#ヘルシー」「#簡単」「#おうちごはん」といった、内容にマッチするハッシュタグを選ぶことが大切です。
また、同ジャンルの人気動画のハッシュタグを参照すると、関連動画に掲載されやすくなります。
ハッシュタグ「#」は小文字・半角にする
ハッシュタグに使用される「#」は、常に半角の小文字である必要があります。
全角の「♯」や文字列「シャープ」として入力された場合、システムによってハッシュタグとして認識されません。
タイトルや動画の説明欄にハッシュタグを入力する際は、「#料理」「#旅行」「#DIY」といった形で、適切に小文字かつ半角の使用を心がけてください。
もし、全角文字を使用してしまうと、ハッシュタグが正しく機能せず、結果としてその動画が検索結果に上位表示されないので、注意が必要です。
ハッシュタグの単語間にスペースは入れない
ハッシュタグを利用する際のもう一つのルールは、単語間にスペースを入れないことです。
単語間にスペースを入れると、、ハッシュタグとして意図した通りの機能を果たしません。
例えば、「#おいしい デザート」と入力すると、「#おいしい」のみをタグとして扱い、「デザート」はテキストとして認識されてしまいます。
正しくは、「#おいしいデザート」と一つのフレーズとして続けて入力してください。
スペースを入れない入力により、ハッシュタグが一つの連続したキーワードとして機能し、視聴者が関連する動画をより効率的に見つけられます。
ハッシュタグの個数は3個以上15個以下にする
一般的に、1つの動画に対して推奨されるハッシュタグの数は、最低3~5個が良いとされています。
YouTubeでは、概要欄へ入力したハッシュタグのうち最初の3つがタイトルの下に優先表示される仕組みが継続しています。最新の分析によると、これらの表示されるハッシュタグがクリックされる確率は他のハッシュタグの約5倍高いことがわかっています。
そのため、最も関連性が高く、ユーザーの検索意図に合致するキーワードを最初の3つに設定することが重要です。
また、ハッシュタグが15個を超えると全てのハッシュタグが無効となるポリシーが明確化されました。
ハッシュタグを乱用すると、タグが適切に反映されなくなり、効果も薄れる可能性があるためです。
したがって、動画の内容に最も密接に関連するキーワードを選び、15個以下に絞り込むことも覚えておきましょう。
YouTubeのポリシーを遵守して禁止ワードは使わない
YouTubeにはコミュニティガイドラインが存在し、そのポリシーに反する表現や禁止ワードの使用はさけましょう。
なぜなら、嫌がらせや脅迫、下品・性的な言葉、暴力などの内容に関する動画は削除される可能性があるからです。
そのため、ガイドラインを遵守し、ハッシュタグを設定する際にも不適切な言葉を使用しないように注意しなければなりません。
最悪の場合、違反するハッシュタグがあると、レコメンドされなかったり、アカウントが凍結されたりもありますので十分に注意してください。
AI時代のYouTubeハッシュタグ戦略

近年、AIツールの発達により、YouTubeハッシュタグ戦略も大きく変化しています。2023年以降、多くの成功しているクリエイターはAIを活用したデータ分析でハッシュタグを最適化しています。
AIを活用したハッシュタグ分析と最適化
現在、複数のAIツールがYouTubeのデータを分析し、最適なハッシュタグを提案してくれます。例えば、TubeBuddy、vidIQ、RapidTagsなどのツールは、競合動画や検索トレンドを分析し、効果的なハッシュタグを提案してくれます。
これらのツールを使用することで、以下のような利点があります。
- 競合チャンネルの成功しているハッシュタグを特定できる
- 特定のキーワードの競争率と検索ボリュームを確認できる
- ニッチな市場で効果的なハッシュタグを発見できる
- AIが提案するハッシュタグの検証方法
AIが提案するハッシュタグを盲目的に使用するのではなく、以下のステップで検証することが重要です。
- 提案されたハッシュタグで実際にYouTube検索を行い、上位表示される動画の品質と関連性を確認する
- 提案されたハッシュタグの競合度をチェックし、過度に競争が激しいものを避ける
- 数回の動画でテスト使用し、パフォーマンスデータを収集して効果を測定する
このようなデータドリブンのアプローチにより、ハッシュタグ戦略を継続的に最適化し、より多くの視聴者にリーチすることが可能になります。
YouTubeのハッシュタグのつけ方に対するよくある質問

最後に、YouTubeのハッシュタグのつけ方に対するよくある悩みを、解消しておきましょう。
- ハッシュタグの登録はいつやるの?
- ハッシュタグはあとからつけられるの?
- ハッシュタグはどこにいれるの?
- ハッシュタグは勝手につくの?
- YouTubeショート動画のハッシュタグのつけ方は?
それでは、これらの質問点について1つずつ説明します。
ハッシュタグの登録はいつやるの?
ハッシュタグの登録は、動画のアップロード、またはそのあとからでも動画の説明欄への追加で対応可能です。
さらに、動画を投稿した後もタグを追加・修正できるため、動画の内容や戦略に応じて最適化を図ることができます。
ハッシュタグはあとからつけられるの?
動画をアップロードした後でも、ハッシュタグを追加または編集できます。
そのため、市場のトレンドやユーザーの反応を踏まえて、動画がより多くの視聴者に届くよう最適なハッシュタグに更新できます。
既存の動画に対しても、こうしたメンテナンスを行い、検索可能性を高めることで、長期的な視聴回数の増加に繋がるでしょう。
ハッシュタグはどこにいれるの?
YouTubeでのハッシュタグは、動画の「タイトル」や「説明欄」に入れることができ、特に説明欄に入れた場合、動画のタイトルの下部に掲載されます。
ハッシュタグは、英語のアルファベットである「#」とキーワードの連結であるため、全角の「#」では認識されません。
また、15個以上のハッシュタグを使用すると無効となるため、使用数にも注意が必要です。
ハッシュタグは勝手につくの?
YouTubeのハッシュタグは勝手につきません。
ニコニコ動画のような他のプラットフォームで採用されているような、視聴者がタグをつける機能ではないためです。
そのため、ハッシュタグは、投稿者が明示的に動画の説明欄などに入力しましょう。
YouTubeショート動画のハッシュタグのつけ方は?
YouTubeのショート動画においても、ハッシュタグをつけることができます。
書き方は非常に簡単で、タイトルや説明欄に「#」とキーワードをつなげて入力するだけです。
適切なハッシュタグを使用できれば、ショート動画の視認性が上がり、より多くの視聴者に自社の動画コンテンツを届けることが期待できます。
YouTubeのハッシュタグをうまく使って再生数や登録者を伸ばそう

ここまで「YouTubeのハッシュタグ」についてお伝えしてきました。
要点をまとめると、以下のとおりです。
- ハッシュタグの選定と配置により、再生数やチャンネル登録者数の増加が期待できる
- ハッシュタグを活用する際は、適切な数や関連性が重要であり、ポリシー違反を避ける必要がある
- ハッシュタグの探し方や注意点を理解し、動画内容との相性を考えながら戦略的な使用が肝心
しかし、ハッシュタグはすべての動画に即効性があるわけではなく、視聴者の離脱や動画内容とハッシュタグのミスマッチには相変わらず注意が必要です。
そのため、YouTubeハッシュタグを最大限に活用するためには、定期的な分析と更新、そしてトレンドの監視が推奨されます。
もし、YouTubeの運用に不安を感じているなら、ぜひNOGICの無料診断をご利用ください。
「YouTubeの動画をおすすめに表示させやすくする仕組みは?」「そもそもどのような仕組みでおすすめにのるんだろう?」とお悩みではないでしょうか。
実際に、動画がおすすめにのらずどうしたらいいか頭を抱えている方もいるかもしれません。
YouTubeの複雑なアルゴリズムも理解しなければなりませんし、視聴者へのアピールの仕方も常に変化しているため、難しく感じる方が多いのも当然です。
そこでこの記事では、動画がおすすめに選ばれる仕組みと、おすすめにのせるための具体的な戦略を徹底解説します。
この記事を読むことで、視聴者に響くクオリティの高いコンテンツ作りに自信が持てるようになるだけでなく、チャンネルが成長している実感も感じられるはずです。
YouTubeのおすすめ動画の仕組みとは?

YouTubeのおすすめ動画の仕組みは、ユーザーが興味を持っていると思われるコンテンツをピックアップして、ユーザーに届けるというものです。
具体的には、ユーザーの興味関心や視聴履歴に基づいて、パーソナライズされた動画が表示されます。
なお、おすすめ動画が表示されるのはYouTubeのホーム画面と、動画の視聴中に現れる「次の動画」パネルの2箇所です。
YouTubeを開くと最初に現れるホーム画面には、ユーザーの好みに合わせたおすすめの動画やフォローしているチャンネル、新しいニュースなどが載っています。
また「次の動画」パネルは、動画を見ている時に現れ、ユーザーにとって関連性が高い動画が次々と提案されるものです。
YouTubeのおすすめにのりやすい仕組みの動画は?

YouTubeでは、ユーザーの動画検索履歴や再生履歴、登録しているチャンネルに基づいてパーソナライズされた動画がおすすめにのりやすい傾向があります。
このおすすめにのる仕組みを理解し、効果的に利用するためには、以下のポイントに注意して動画を作成しましょう。
- 初動の再生回数が高い動画
- エンゲージメントが高い動画
- 専門性・信頼性の高い動画
- クリック率と総再生時間が高い動画
- 平均視聴時間の長い動画
- キーワードが盛り込まれた動画
- アンケートの結果が良い動画
それぞれのポイントを押さえた動画を作成することで、YouTubeの仕組みによる再生数やクリック数の増加だけでなく視聴者の満足度向上にも役立ちます。
①:初動の再生回数が高い動画
初動の再生回数が高い動画は、YouTubeのアルゴリズムにおいて人気があるコンテンツだと捉えられるため、おすすめに表示されやすくなります。
初動の再生回数を高める戦略として、ターゲットの視聴者数が増加する特定の時間帯に動画のアップロードを行うことがポイントです。
具体的には、平日の夕方や週末の昼間など、ターゲットがYouTubeを利用する時間を狙って公開すると良いでしょう。
また、YouTubeの外部からも視聴者を引き寄せる方法として、以下の戦略があります。
|
戦略 |
説明 |
|
事前告知 |
自身のSNSアカウントやメーリングリストを活用して動画をアップすることを告知し、視聴者の関心や期待感を高める |
|
SNSでのシェア |
視聴者にSNS上で動画を共有してもらうよう促し、拡散を目指す |
|
相互促進のコラボレーション |
他のクリエイターやチャンネルとコラボレーションを行い、お互いのファンからの認知やイメージアップを目指す |
ほかにも、動画の話題性を前面に打ち出すことも大切です。
視聴者の興味を引き、共感や警鐘を促す内容は初動で注目されやすく、高い再生回数を期待できます。
またオンライン広告の展開やインフルエンサーとの提携など、様々なプロモーション活動により、動画の視認性を増やす工夫を行うと良いでしょう。
②:エンゲージメントが高い動画
エンゲージメントとは視聴者が動画とどれだけ相互作用しているかを示す指標で、コメントや評価、共有などのアクティビティの量を意味します。
動画が高いエンゲージメントを得られるとYouTubeのアルゴリズムにさらに好まれ、YouTubeのおすすめにのる確率もグッと高まります。
例えば、以下の戦略が考えられます。
|
質問 |
動画内で視聴者に関連する質問をし、意見や感想を求めることで、コメント数の増加を目指す |
|
挑戦 |
視聴者に特定の行動や挑戦を提案し、結果を共有してもらうように促す |
|
投票 |
投票やアンケート機能を活用して、視聴者の意見を直接求めることで参加意欲を高める |
動画に対する積極的な視聴者の反応が多ければ動画の評価も上がるため、動画内でコメントや高評価、共有を促すことで、エンゲージメントを最大化できます。
それぞれの戦略を採用することで、視聴者とのコミュニケーションを活性化させることが可能です。
③:専門性・信頼性の高い動画
YouTubeにおける専門性と信頼性は、特にニュースや科学、教養といったジャンルの動画において非常に重要です。
なぜなら、誤情報や偽情報は視聴者にとって有害であり、YouTubeというプラットフォームの信頼性を損なうからです。
信頼されるコンテンツの条件としては、情報が正確で、検証可能なソースに基づいて制作されている必要もあります。
また、誇張されたタイトルや根拠のない情報を含むセンセーショナルな内容は、YouTubeに好まれず、表示順位が下げられることもあります。
加えて、審査担当者によるチェックも動画がおすすめに表示される可能性に大きく影響するものです。
動画が審査を通過しない場合、不正確、誤解を招く、有害、あるいは誤った情報提供者と見なされるため、結果としておすすめにのるアルゴリズムから除外されることになります。
以上のことから、信頼できる情報源を参考にしたうえで正確かつ信頼性の高い動画を制作することが極めて重要だと言えます。
④:クリック率と総再生時間が高い動画
YouTubeのおすすめにのせるためには、、クリック率(CTR)と総再生時間も重要な指標です。
YouTubeはこの2つのデータを使用して、動画が視聴者にとって魅力的かどうかを判断するためです。
- クリック率:検索結果や推薦リストでクリックされる割合
- 総再生時間:視聴者が動画を再生した時間の合計
クリック率が高いことは視聴者の注意を引き、関心も高いことを表します。
一方で総再生時間が長ければ、視聴者はコンテンツに満足し、興味を保持していることを意味します。
クリック率が高くても、総再生時間が短い場合は期待に応えていないコンテンツと見なされる可能性もあるため両方の指標を意識することが大切です。
効果的なサムネイルやタイトルを設定することに加えて、視聴者の期待を満たす価値の高いコンテンツを制作するようにしましょう。
⑤:平均視聴時間の長い動画
YouTubeでは、平均視聴時間もコンテンツの品質を示す重要な指標の1つです。
これは動画全体の再生時間を視聴者の数で割った値であり、視聴者が動画をどれだけ楽しんで見ているか、または内容に魅了されているかを測定するのに役立ちます。
一般的に、平均視聴時間が長ければ長いほど、高品質で視聴者の興味を持続的に引き付けていると見なされます。
平均視聴時間を高めるためには、視聴者を飽きさせない内容と構成が重要です。
YouTubeを使う視聴者が動画を途中でやめてしまう理由として、コンテンツの内容が予告やタイトルと異なることや、動画の内容が冗長であることなどが挙げられるためです。
視聴者が動画に飽きないように、また情報に価値を感じてもらうために、戦略的なアプローチを取りましょう。
⑥:キーワードが盛り込まれた動画
キーワードを適切に盛り込むことは、視聴者が興味を持つトピック対して動画を見つけやすくするために必要です。
主要なキーワードを以下の場所に含めることで、検索エンジンによるコンテンツへのマッチングがより正確になります。
|
要素 |
内容 |
|
タイトル |
検索キーワードを含む効果的なタイトルを付ける |
|
説明欄 |
キーワードを使って動画の説明をする |
|
タグ |
関連キーワードでタグ付けをする |
|
動画の内容 |
キーワードに関連する内容のコンテンツを作る |
|
ハッシュタグ |
ハッシュタグを適切に使用する |
それぞれの戦略を組み合わせることで検索エンジン最適化(SEO)に貢献し、なおかつYouTubeのおすすめリストに選ばれる可能性が高まります。
視聴者が動画を検索しやすくなればなるほど動画の視聴者数も向上し、おすすめに表示されやすくなるという好循環も生まれるでしょう。
⑦:アンケートの結果が良い動画
YouTubeでは、視聴後のアンケートも動画の評価に大きな影響をもたらします。
アンケートは、どの程度価値がある動画なのかを調査するために設けられている機能です。
YouTubeでは星4か星5の高評価を受けた動画が、視聴者に必要で役に立つコンテンツだと判断され、おすすめにのりやすくなります。
なおアンケートで高評価を受けるためには、以下の観点から視聴者にとって真に価値のある動画を作成する必要があります。
- 関連性の高いコンテンツ
- 質の高いコンテンツ
- エンゲージメントを促進する要素
- 継続的な価値の提供
それぞれを動画制作に取り入れることで高評価を獲得し、視聴者の満足度とエンゲージメントを高めましょう。
YouTubeのおすすめにのせて再生回数を伸ばす方法と仕組み

YouTubeの動画をおすすめにのせるためのポイントは、大きく分けて以下の2つです。
- 短期的にでも良いのでおすすめにのせて再生回数が欲しい場合
- トレンド動画を作る
- 長期的にチャンネルを伸ばしたい場合
- チャンネル単位でターゲットをしっかりと定める
- ターゲット視聴者にとって質の高い動画をしっかりと作り込む
- 一貫してターゲット視聴者に役立つ動画を投稿する
- ターゲット以外におすすめ表示が伸びる動画は非公開にする
ここからは、各ポイントについて見ていきましょう。
①:短期的にでも良いのでおすすめにのせて再生回数が欲しい場合
YouTubeで急速に人気を得るには、一時的であれ、おすすめに表示されることが非常に効果的です。
ここでは、トレンドに敏感な内容を取り入れた動画の作り方を解説します。
トレンド動画を作る
YouTubeにおいて視聴回数を短期的に増加させたい場合は、トレンドに敏感な動画作りが有効です。
特に、競合が少なくニーズも高い内容はおすすめ動画に表示されやすい特徴を持っています。
例としては、ニュースの速報系動画、一番くじの開封動画、アパレルブランドの最新コレクション紹介など、話題のトレンドを取り入れた動画が挙げられます。
トレンド動画を作る前に、YouTubeのアルゴリズムに影響を与える主要なポイントを押さえておきましょう。
|
急上昇動画のリスト更新間隔 |
15分ごと |
|
視聴回数 |
動画の視聴回数が多いほど良い |
|
視聴回数の伸び速度 |
急速に増加している動画が有利 |
|
視聴された地域 |
無視できない要素 |
|
動画の新しさ |
新しいほど良い |
|
他の動画とのパフォーマンス比較 |
チャンネル内での相対的な成績 |
上記を考慮し、タイムリーで視聴者の興味を引く内容を適切なタイトルとキーワードで配信することが、短期的な視聴回数の増加につながります。
ただ、トレンド動画が急増すると多様な視聴者を集めてしまい、ターゲットとするユーザー層が分散する可能性を捨てきれません。
またトレンドに特化した内容ばかりでは、他のジャンルでの視聴者がつかなくなる危険性があり、中長期的なチャンネル運営も困難を極めるでしょう。
②:長期的にチャンネルを伸ばしたい場合
長期的にチャンネルを伸ばしたい場合の戦略は以下の通りです。
- チャンネル単位でターゲットをしっかりと定める
- ターゲット視聴者にとって質の高い動画をしっかりと作り込む
- 一貫してターゲット視聴者に役立つ動画を投稿する
- ターゲット以外におすすめ表示が伸びる動画は非公開にする
それぞれ、見ていきましょう。
チャンネル単位でターゲットをしっかりと定める
YouTubeチャンネルを長期的に成長させるためには、ターゲット視聴者の明確な定義から始めることが欠かせません。
この流れは商品やサービスのマーケティング戦略に似ており、潜在的な視聴者の年齢、性別、興味、趣味といった要素を分析してターゲットを特定します。
一度ターゲットを定めたら、その視聴者層に響くコンテンツの計画と制作に集中しましょう。
例えば、子供向けのチャンネルなら教育的で楽しいアニメーションを、ゲーム好きな若者に向けたチャンネルなら最新のゲームレビューやプレイ動画を投稿するなどです。
また、ターゲットに合わせたコンテンツを配信することで以下の要素も満たせるため、最終的に視聴者の長時間滞在を促すことができます。
- 初動の再生回数の増加
- インプレッションからの高クリック率
- 長い視聴時間を獲得できる動画
このように、一貫性のあるコンテンツの投稿により、一回限りの視聴ではなく、熱心なファンを増やすことができます。
また、視聴者との信頼関係を築き、長期的な関係性を築くことにも期待できるでしょう。
ターゲット視聴者にとって質の高い動画をしっかりと作り込む
質の高い動画コンテンツを作ることで、ターゲット視聴者が定着しやすくなります。
動画の質を高めるための主要なポイントとしては、以下が挙げられます。
- 緻密な企画立案
- 丁寧な撮影
- 効果的な編集
映像の解像度が高く、音声もクリアであることは基本ですが、ストーリーテリングや視聴者の感情に訴えかける要素を取り入れることで、視聴者により良い印象を与えやすくなります。
また企画立案では、トレンドを意識した内容や視聴者のニーズに合ったオリジナリティが求められます。
加えて、撮影では視聴者が心地よく感じるビジュアルを、編集ではテンポの良い動画の流れを作ることが大切です。
このように、それぞれのバランスが整った動画を継続的にアップロードすることがチャンネル成長の鍵となります。
一貫してターゲット視聴者に役立つ動画を投稿する
また、一貫してターゲット視聴者に役立つ動画を投稿することも大切です。
ターゲット視聴者に役立つコンテンツのみを提供することで、視聴者がチャンネルを定期的に訪れる理由を見出しやすくなるためです。
さらには以下の内容を含む動画で、エンゲージメントを促進させることもできます。
- 教育的なコンテンツ
- 楽しいエンターテイメント
- 役立つ情報提供
総再生時間や平均視聴時間の増加にも期待できるため、YouTubeのおすすめに表示されやすくなることにもつながります。
このように、一貫性のある価値を提供することで、視聴者の期待に応えるだけでなく、チャンネルの成長にも期待できます。
ターゲット以外におすすめ表示が伸びる動画は非公開にする
ターゲット視聴者への影響が薄い動画やブランドイメージを乱す可能性がある動画は、思い切って非公開にしてしまうことも1つの手です。
YouTubeチャンネルのブランドイメージを構築するにあたっては、ターゲット視聴者からの再生をメインに考える戦略が重要だからです。
意図しないターゲット層からの再生が多い動画は、チャンネルのブランドイメージに混乱をきたす可能性があります。
よって、そういった動画は非公開設定を選ぶことでブランドイメージを統一しましょう。ターゲット以外におすすめが表示されている動画を探す場合は、YouTubeのアナリティクスを用いて、以下を確認しましょう。
- おすすめ表示になっている動画の分析
- ターゲットの視聴者に見られているかの確認
- ブランドのブレを起こす可能性のあるコンテンツの特定
これにより、長期的なブランドイメージの構築に役立ち、チャンネルをより効果的に成長させることができます。
YouTubeのおすすめ動画の仕組みを押さえよう
YouTubeのおすすめ動画は、ユーザーが見たい・価値があると思う動画を届ける仕組みです。
この仕組みは、ユーザーの視聴履歴や検索履歴などの行動を分析し、関連性の高い動画を提案することで実現されています。
YouTubeのおすすめ動画にのせるためには、短期的な方法と長期的な方法の2つがあります。
しかし、短期的な方法にはデメリットもあるため、継続的な効果が望めないこともあるでしょう。
そのため、ターゲティングを徹底し、質の高いコンテンツのみを提供するアプローチが理想です。
YouTubeのコンサルティングを行うNOGICでは、効果的なコンテンツ配信やチャンネル運営のアドバイスを行っています。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
「YouTubeは採用に活用できる?」「採用に活用した事例はある?」と疑問に思っている人は多いです。
採用活動において、多くの企業が工夫を凝らしていますが、実際に求める人材と出会えることはそう多くありません。
そこで試したいのが、YouTubeを活用した採用活動です。
YouTubeの特性を活かすことで、企業の魅力をより鮮明に伝えることができます。
さらに、視聴者とのコミュニケーションを強化し、志高い人材を引きつけることも可能です。
しかし、実際にYouTubeをどのように運営したら良いか、わからない方も多いです。
そこでこの記事では、YouTubeを活用した採用活動のメリットや成功のコツを具体的に解説します。
本記事を読むことで、具体的なアクションプランを立て、YouTubeを活用した効果的な採用活動を実現できます。より効果的な採用活動を行い、優秀な人材を獲得するための参考にしてください。
YouTubeは採用活動に効果的

YouTubeは、採用活動に効果的なツールであると言えます。
その理由は、YouTubeは動画というメディアを使って企業の魅力や働くイメージを視覚的に伝えることができるからです。
YouTubeは、学生が自分の都合の良いタイミングで視聴でき、視覚的に訴求できます。
また、動画は音声や音楽、編集などを工夫することで感情や雰囲気まで伝えることが可能です。
そのため、ホームページなどでは伝わりにくい会社のビジョンや見えずらい仕事内容について具体的に伝えることができます。
このように、YouTubeは学生の消費行動に合わせて、マーケティングできる便利な手法と言えるでしょう。
採用活動にYouTubeを活用するメリット
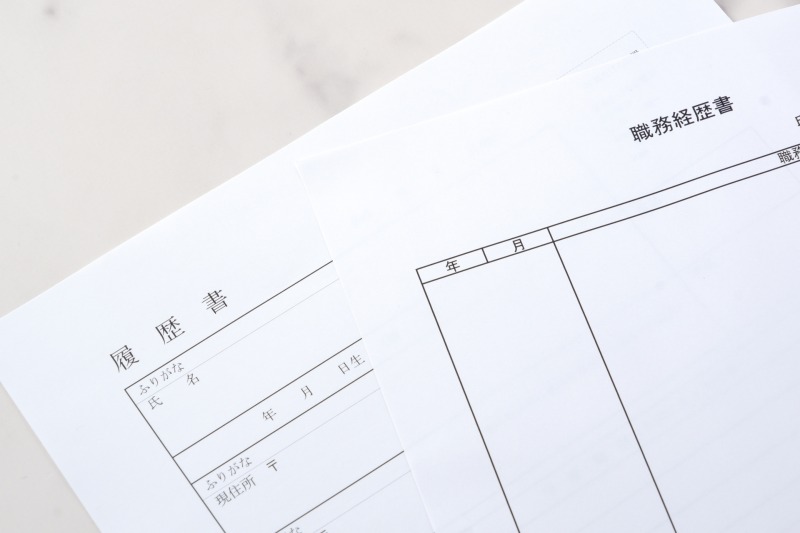
本章では、実際に採用活動にYouTubeを活用するメリットを解説します。
具体的なメリットを以下2つに分けて解説するので、ぜひ参考にしてください。
- 企業側のメリット
- 学生側のメリット
それぞれ詳しく見ていきます。
企業側のメリット
企業側のメリットは、主に下記の3つです。
- コストを削減できる
- 企業のブランディングにつながる
- ターゲティングを明確にした発信が可能
YouTubeのチャンネルは、無料で開設でき、動画の公開にも費用がかかりません。
そのため、広告やホームページの改善と異なり、コストを削減できるメリットがあります。
また、社員インタビューやオフィス紹介、仕事風景などの動画も公開可能です。これにより、学生に企業のオープンさや親しみやすさを伝え、関心や応募意欲を高めることもできます。
加えて、YouTubeでは動画のタイトルや説明文、タグなどの工夫で、ターゲットを明確にした集客が可能になります。
このように、企業側にとってYouTubeを採用活動に活かすのは効果的です。
学生側のメリット
学生側のメリットは、主に下記の2つです。
- 事業内容やビジョンを伝えられる
- 職場の雰囲気を伝えられる
YouTubeでは、企業の事業内容やビジョン、社風などを具体的に伝えられます。
これらの動画は、学生に企業の実態や将来性を伝え、自身の適性や志向と一致するか考えてもらうことに役立ちます。
また、社員や先輩などの生の声を配信する方法も有効です。普段の職場を撮影したり、現場の社員へのインタビュー動画を制作することで、社内の雰囲気を伝えることができます。
これらの情報は他メディアでは得られにくい情報です。
このように、学生にとって自分に合った会社を選べるようになることも、YouTubeを活用するメリットです。
特にYouTube活用がおすすめ企業

YouTubeを活用することで、企業の魅力や働く人の声を直接伝えることができます。
しかし、YouTubeを活用するには、どのような企業が向いているのでしょうか。ここでは、特にYouTube活用がおすすめの企業の特徴を紹介します。
- 業務内容が見えにくい企業
- 明確なビジョンを持っている企業
- 若くてフレッシュな人を求めている企業
それぞれ詳しく解説します。
業務内容が見えにくい企業
業務内容が見えにくい企業は、YouTubeの活用がおすすめです。
YouTubeを使うことで自社の仕事内容や魅力を説明することができます。
業務内容が見えにくい企業とは、一般的に知られていない業界や職種、あるいは独自のサービスや製品を提供している企業のことです。
YouTubeを活用することで、実際の業務風景などを視覚的に伝えることが可能です。これにより、応募者は企業の仕事に対するイメージを具体化できます。
たとえば、AIやIoTなどの最先端技術を扱っている企業は、自社の技術力や開発の流れをアピールすることで、技術志向の人材の関心を惹けます。
ほかにも、オンライン教育やフィットネスなどの新しい分野に挑戦している企業は、自社のサービスや製品の価値や使い方を動画で紹介することで、応募者の関心を惹けるでしょう。
このように、業務内容が見えにくい企業は、YouTubeを活用することで、自社の仕事内容や魅力を具体的に伝えることができます。
明確なビジョンを持っている企業
明確なビジョンを持っている企業は、YouTubeによって自社のビジョンや今後の方向性を伝えられます。
明確なビジョンを持っている企業とは、自社の存在意義や目標、理念などを明確に定めている企業のことです。
たとえば、代表者や経営陣のメッセージを動画で紹介することで、ホームページだと読み飛ばされてしまう想いを応募者へ伝えることが可能です。
また、社会貢献や環境保護などの高い志を持っている企業は、自社の取り組みや成果を動画でアピールできます。
他にも、海外展開やグローバル化などの大きな挑戦をしている企業は、自社の国際的な活動や多様性を動画で紹介することができるでしょう。
このように、YouTubeを活用することで、自社のビジョンや方向性に共感する人材を惹きつけることができます。
若くてフレッシュな人を求めている企業
自社の雰囲気やカルチャーを伝えることで、若くてフレッシュな人材の採用に役立ちます。
社員の日常やオフシーンなどを紹介することで、応募者は企業の雰囲気やカルチャーに親近感を覚えるからです。
たとえば、ベンチャーやスタートアップなどの成長志向の高い企業は、自社の挑戦や失敗、成功などを動画で紹介することで、成長意欲のある人材を惹きつけられます。
また、クリエイティブ性が重視される企業は、自社の作品やプロジェクト、イベントなどを動画で紹介すると良いでしょう。
企業がYouTubeを活用することで、社内の雰囲気やカルチャーに共感してくれる、意欲が高い人材を惹きつけることが可能です。
効果的にYouTubeで採用できている企業5選

実際に多くの企業がYouTubeを採用活動に活用しています。
本章では、効果的にYouTubeを活用できている企業の事例を5つ解説します。
- 施工管理チャンネル
- 年収チャンネル
- 大京警備保障株式会社
- 株式会社リソースクリエーション
- IT菩薩モロー
それぞれどのような内容を発信しているのか、詳しく見ていきましょう。
施工管理チャンネル
施工管理チャンネルは、「建設業界のリアルを伝える」をテーマに、業界の基本から裏話まで発信しているチャンネルです。
業界歴30年以上の元・施工管理社長が、自身の実体験を元に役立つ知識を伝えています。
登録者数は約2.07万人、総再生回数は約300万回です。
動画は、専門的かつリアルな内容で、分かりやすく丁寧な解説によって、視聴者とのコミュニケーションを実現しています。
また、建設業界に興味や関心がある人や、建設業界で働きたい人にとって、貴重な情報源となっています。
このチャンネルは、建設業界の魅力や可能性をYouTubeで発信することで、業界への理解や関心を高める役割を果たしている好例です。
年収チャンネル
年収チャンネルは、早稲田・慶應を始めとした高学歴の大学生を対象に、将来的に稼げるキャリアを真剣に討論するチャンネルです。
登録者数は163万人で、再生回数は10億回を超えています。
動画内では、各企業の年収・苦労話など、求職者が知りたい内容が盛り込まれています。
また、動画の中には専門的な知識やアドバイスも含まれており、視聴者にとって有益な情報を提供しています。
このチャンネルの特徴は、高学歴大学生というニッチなターゲットに対して、独自の視点や刺激的な内容を発信していることです。動画内でも「年収が高ければ良い」という世界観を作り出しています。
年収チャンネルは、これらの工夫によって、エージェントとして年収に興味がある高学歴の求職者を集客するのに成功しています。
大京警備保障株式会社
大京警備保障株式会社のYouTubeチャンネルは、東京の警備会社が運営しています。
登録者数は163万人で、動画の総再生回数は10億回を超えています。
動画の特徴は、実際の社員が社内で面白ろ企画を行なっていることです。
このチャンネルの特徴は、警備業界では前例がないSNSを駆使したブランディングにより経営改善を図っている点です。
業務内容ではなく、社内の雰囲気や社員を撮影することで、求職者から親近感が持たれる内容になっています。
YouTubeを活用する際には、企業の魅力だけでなく、リアルな企業像も発信していく必要があることを学べる事例です。
株式会社リソースクリエーション
株式会社リソースクリエーションは、求人広告の代理店や採用向けSNS運用代行サービスなどを提供する企業です。
その社員が仕事や遊びに関する動画を配信しているのが「RCの部屋」というYouTubeチャンネルです。
登録者数は5410人で、再生回数は52万回となっています。
このチャンネルが成功事例と言える理由は、企業の雰囲気やカルチャーを伝えることで、求職者に興味や共感を持ってもらえるからです。
YouTubeを使い企業内カルチャーを伝えることで、求職者の興味・関心を惹くことができます。
IT菩薩モロー
IT菩薩モローは、ITエンジニアの転職やキャリアに関する情報を発信するYouTuberのモローが運営しているチャンネルです。
モローは元IT人事であり、現在はエンジニア特化の転職エージェント「キッカケクリエイション」の副社長を務めています。登録者数は約1万人、総再生回数は約200万回です。
このチャンネルでは、モローが自身の経験や知識をもとに、エンジニアにとって有益な情報を分かりやすく伝えています。
その結果、エンジニアのニーズに応えるコンテンツを提供でき、高い視聴率やコメント率を獲得した成功事例です。
YouTubeを活用した採用を成功させるポイント5つ
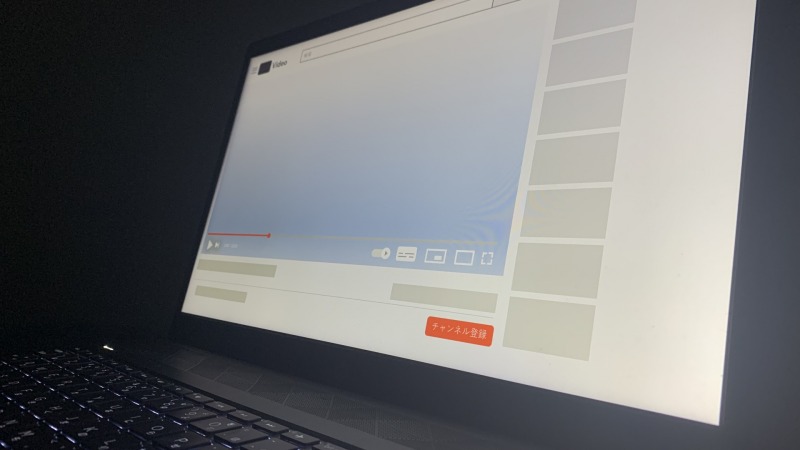
具体的にYouTubeを用いた採用活動を成功させるためのポイントについて解説します。
YouTubeを活用した採用を成功させるポイントは、下記の5つです。
- 目的をはっきりさせる
- 動画作成などにあてるリソースを確保する
- 良いところばかり発信しない
- SNSを活用して幅広く伝える
- 動画を最新情報に更新し続ける
それぞれ詳しく見ていきましょう。
目的をはっきりさせる
YouTubeを活用して採用を成功させるためには、YouTubeを活用する目的をはっきりさせる必要があります。
- YouTubeを活用した採用の目的は何か?
- 求める人材像はどのようなものか?
- YouTubeではどのようなメッセージを伝えたいのか?
これらの目的は、動画の企画や制作、配信の基礎となります。
目的がはっきりしていれば、動画の内容やターゲット層、配信方法なども効率的に決められます。また、目的に沿って動画の効果測定や改善も行えます。
YouTubeを活用した採用の目的は、事前に検討するようにしましょう。
動画作成などにあてるリソースを確保する
YouTubeを活用した採用には、動画制作だけでなく、配信や運用も含めて、それなりのリソースが必要です。
|
項目 |
内容 |
|
動画作成 |
機材や編集ソフト、撮影や編集スタッフ |
|
配信 |
YouTubeチャンネルの開設や管理、SEOや広告運用 |
|
運用 |
動画の更新や分析、コメントへの対応 |
すべてをスムーズに行うためには、予算や人員、時間などのリソースを確保する必要があります。
リソースが不足していると、動画の質や量が低下したり、効果が出なかったりする可能性があるからです。
YouTubeを活用した採用には、自社でできることと外部に委託することをわけて、効果的にリソースを管理しましょう。
良いところばかり発信しない
企業の魅力を発信することは大切ですが、良いところばかり発信することは避けてください。
良いところばかり発信すると、求職者に不信感を抱かせる可能性があるためです。
また、良いところばかり発信すると、求職者の期待と現実のギャップが大きくなり、採用後の離職率が高くなる恐れもあります。
反対に、企業の課題や改善箇所を伝えることで、求職者にリアルな企業像を見せることができます。
同時に課題を改善するための取り組みやビジョンも伝えることで、求職者にチャレンジや成長の機会を感じてもらうこともできます。
YouTubeを活用した採用では、良いところだけでなく、課題や改善箇所も正直に伝えるのがおすすめです。
SNSを活用して幅広く伝える
YouTubeを活用した採用は、SNSなど他のメディアでもシェアすることがおすすめです。
SNSを活用して動画を幅広く伝えることで、より多くの求職者にアプローチできるためです。
また、視聴者の関心を高めたり、応募者や採用候補者とのコミュニケーションを強化したりできます。
SNSを活用する際には、各メディアの特徴やユーザー層に合わせて、動画のタイトルや説明文、ハッシュタグなどを工夫しましょう。
また、SNSでは動画に対するコメントやシェアなどの反応を見て、動画の効果や改善点を分析することも可能です。
SNSを活用することで、YouTubeを活用した採用の効果を高めて多くの求職者にアピールしましょう。
動画を最新情報に更新し続ける
YouTubeを活用した採用では、動画を最新情報に更新し続けることが必要です。
企業や求人情報は常に変化しており、動画に古い情報や間違った情報が含まれると、求職者に不利益や不信感を与えることになります。
更新する際には、動画の内容だけでなく、タイトルや説明文、サムネイルなども見直しましょう。
また、動画を更新し続けることで視聴者の満足度を高めたり、応募者や採用候補者の期待や興味を引き上げたりできます。
このように、動画を最新情報に更新し続けることで、YouTubeの効果を高めることが可能です。
YouTubeを使った採用活動は実績のあるNOGICにお任せ
YouTubeを活用した採用活動は、企業や学生にとって非常に魅力的な手法です。
株式会社NOGICは、YouTubeマーケティングや動画コンテンツ制作のノウハウを活かし、「ビジネスに繋がる」YouTubeチャンネルの運用プランを提案しています。
YouTubeのチャンネル運用は、美しい動画を作り、投稿するだけではありません。
多くの情報を詰め込むことができる動画だからこそ、「集客」から「訴求」までの細かい部分の作り込みが大切です。
NOGICは、企業がYouTubeチャンネルを効果的に運用し、ビジネスにつなげるための支援を行なっています。
まずは、無料のお問い合わせからご希望やお悩みをお聞かせください。
「YouTubeを活かしたクリニックへの集客は可能?」と気になりお調べですね。
クリニックの集客は、信頼感だけでなく興味や関心を持ってもらうことが重要です。
そのため、多くの見込み顧客を獲得できるYouTubeを使った集客は効果的であり、視聴者にクリニックの魅力を伝えるツールとして活用できます。
しかし、本当にYouTubeが集客に向いているのか、注意すべき点はないのか気になる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、YouTubeを使ってクリニックへの集客が本当に可能なのかについて、具体的な成功事例を紹介しながら解説します。
未来のクリニックの成果をイメージし、YouTubeを使った集客に挑戦してください。
YouTubeを使ってクリニックへの集客は本当に可能?

YouTubeを使ってクリニックへ集客することは可能です。
実際に、YouTubeを活用し、クリニックの集客に成功している事例は多くあります。
例えば、Youtubeだとクリニックの中の雰囲気やスタッフの顔、施術の様子などを動画で見せることができます。
施術中の様子を見せ、具体的な効果を伝えることで、よりクリニックに対する信頼感を上げることが可能です。また、実際の店舗スタッフがYouTubeに出演することで、スタッフに対して親近感を持ってもらえます。
このように、YouTubeは視聴者に対してクリニックの魅力を多角的にアピールできる手段となります。
クリニックの集客にYouTubeが向いている理由は、下記のとおりです。
- クリニックの中の雰囲気まで知ってもらえる
- 既存顧客により親しみを持ってもらえる
- 若い年齢層にアプローチできる
- 他クリニックとの違いを知ってもらえる
それぞれ、詳しく解説します。
クリニックの中の雰囲気まで知ってもらえる
YouTubeでは、クリニックの内装や設備、スタッフや医師の様子など、クリニックの中の雰囲気を動画で知ってもらえます。
動画では、清潔さや快適さ、スタッフの笑顔や対応、施術の流れや痛みなどをリアルに感じてもらえるためです。
たとえば、下記のような動画があります。
|
内容 |
説明 |
効果 |
|
クリニック紹介動画 |
クリニックの外観や内装、受付や待合室、診察室や施術室などを紹介する動画 |
来院前にクリニックの雰囲気や設備を把握してもらい、安心感を与える |
|
スタッフ紹介動画 |
クリニックのスタッフ(医師や看護師など)を紹介する動画 |
スタッフとの親近感や信頼感を高め、来院へのハードルを下げる |
|
施術紹介動画 |
クリニックで行っている施術(美容整形やレーザー脱毛など)を紹介する動画 |
施術の流れや効果をわかりやすく説明し、患者の不安や期待を払拭する |
これにより、潜在顧客はクリニックに来院する前に、安心感や信頼感を持つことができます。
また、クリニックの特徴やサービス内容を分かりやすく説明することも可能です。
必要に応じて、最新の医療機器や技術を紹介したり、施術の流れや効果を実際に見せたりするのも良いでしょう。
このように、外側からではわからないクリニックの中の雰囲気まで、YouTubeでは余すことなく伝えられるのがメリットです。
既存顧客により親しみを持ってもらえる
YouTubeでは、既存の患者さんにも定期的にコンテンツを提供することで、クリニックへの親しみを持ってもらうことができます。
実際の医師やスタッフが顔出しで登場できるからです。
たとえば、下記のような動画が考えられます。
|
内容 |
説明 |
効果 |
|
Q&A動画 |
クリニックに関するよくある質問や施術に関する質問に答える動画 |
患者さんの疑問や不安を解消し、信頼感や満足度を高める |
|
ライブ配信動画 |
クリニックのスタッフがリアルタイムで患者さんとコミュニケーションする動画 |
患者さんとのコミュニケーションを通じて親しみや関心を高める |
|
患者さんの声動画 |
クリニックで施術を受けた患者さんの感想や体験談を紹介する動画 |
患者さんの感想や体験談を通じて感情移入や共感を促す |
これらの動画では、イラストや画像だけではない映像という情報で、既存顧客は医師やスタッフにより親しみを持つことができます。
また、医師やスタッフの人柄や考え方、専門性などを伝えることで、クリニックと患者さんの関係を長期的に維持することが可能です。
加えて、既存の患者さんがYouTubeの動画を口コミやSNSで拡散することで、新たな潜在的な患者さんにもアプローチできます。
このように、YouTubeはコメントや高評価などの機能で視聴者とのコミュニケーションもでき、既存顧客との関係を深めるチャンスとなるでしょう。
若い年齢層にアプローチできる
YouTubeを使うことで、若い年齢層にアプローチできるのも理由のひとつです。
YouTubeは、2021年時点で20代の男性の88.8%・20代の女性の90.3%が利用しているという結果が出ています。
また、女性の多くは「化粧/美容品」をYouTubeの影響で購入したことがあるという調査結果もあります。
そのため、YouTubeで若い年齢層にアプローチする際には、下記の若い年齢層に合わせたコンテンツ制作が考えられます。
|
内容 |
説明 |
効果 |
|
コラボ動画 |
クリニックと関連性のある人気YouTuberやインフルエンサーとコラボレーションする動画 |
クリニックの知名度を向上させ、新たな視聴者や患者を獲得する |
|
チャレンジ動画 |
クリニックで施術を受ける際に面白いチャレンジを行う動画 |
視聴者の興味を引きつけ、クリニックへの関心を高める |
|
ランキング動画 |
クリニックで人気の施術や商品をランキング形式で紹介する動画 |
視聴者の関心を引き、クリニックの特徴や強みを伝える |
また、口コミやSNSで拡散されやすいメディア媒体でもあるため、クリニックのターゲット層を広げることにもつながります。
このように、YouTubeでは若い年齢層にアプローチでき、クリニックのブランドイメージや知名度を向上させることにつながります。
出典:TestTee Lab「YouTubeに関する調査【2021年版】」
出典:Cross Marketing「YouTubeの利用実態に関する調査」
他クリニックとの違いを知ってもらえる
YouTubeを活用することで、他のクリニックとの違いを視聴者に知ってもらうこともできます。
動画内で自社クリニックの特徴や強みをアピールすることで、潜在的な患者さんの獲得に繋がります。
具体的には、以下のような動画内容が考えられます。
|
内容 |
説明 |
効果 |
|
クリニック比較動画 |
クリニックと競合する他のクリニックとの比較を行う動画 |
視聴者にクリニックの特徴や強みを理解させ、他のクリニックとの差別化を図る |
|
患者インタビュー動画 |
クリニックで治療を受けた患者のインタビュー動画 |
患者の実際の声や体験談を通じて、クリニックの信頼性や効果を訴求する |
|
専門知識動画 |
クリニックの医師やスタッフが専門的な知識や情報を提供する動画 |
クリニックの専門性や知識の深さを訴求し、視聴者に信頼感を与える |
これにより、視聴者はクリニックに対して信頼感や好感を持つようになります。
また、他のクリニックと比べてどのようなメリットや強みがあるのかを明確にすることで、視聴者から選ばれる可能性が上がります。
このように、YouTubeはクリニックの個性や魅力を伝えるツールとして活用でき、より多くの人へアプローチできるのです。
YouTubeによる集客で成功しているクリニックの事例

YouTubeによる集客で成功しているクリニックの事例は、下記の3つが挙げられます。
- 元神チャンネル
- ドラゴン細いfeatアマソラクリニック
- にしたんクリニック
それぞれ、詳しく解説します。
元神チャンネル
元神チャンネルは、男性の性的な悩みに特化したYouTubeチャンネルです。
包茎、ペニスの増大、早漏など、多くの男性が抱える問題に対する解決策を提供しています。
元神チャンネルには、具体的に以下の特徴があります。
- 専門性:男性の性的な悩みに特化している
- アクセシビリティ:匿名で情報を得られる
- インタラクティビティ:質問や相談が気軽にできる
元神チャンネルは、タブーとされがちなテーマに対して、専門的かつ親しみやすい情報を提供しています。
これにより、多くの方からフォローを得ている成功事例と言えるでしょう。
参考にしてYouTubeを運営する場合は、専門性の高いテーマで、親しみやすいコンテンツを作成するという施策が考えられます。
ドラゴン細井featアマソラクリニック
ドラゴン細井featアマソラクリニックは、美容外科と美容皮膚科に特化しています。
渋谷のアマソラクリニック、新宿のアマシオクリニックなど、複数のクリニックが提供する美容医療情報を発信しています。
本チャンネルには、以下の特徴があります。
- 多角的な情報提供:複数のクリニックからの情報がある
- エンタメ性:美容医療×エンタメを追求している
- 誠実性:正確な美容医療情報を提供している
なかでも、エンタメ性を取り入れることで、一般的な美容医療の情報提供以上の価値を生み出している点は、多くの視聴者を引きつけているポイントです。
一見すると難しい内容を取り扱う場合でも、エンタメ要素を取り入れることで多くの視聴者に興味を持ってもらうことができます。
にしたんクリニック
にしたんクリニックのYouTubeチャンネルは、美白や美肌の美容点滴・注射、HIFUやピコレーザーなどの美容皮膚・レーザー治療を中心とした内容を提供しています。
最新の医療を取り扱う一方で、自らの特徴を全面に打ち出した動画が特徴です。
- 多様な治療:美白、美肌、ダイエットなど多様な情報を発信している
- 高級感:上質で落ち着いたスペースを動画で余すことなく伝えている
- 健康と美容の融合:健康で若々しい生活をアピールしている
他のクリニックとは動画の雰囲気も異なり、さまざまなジャンルで動画をあげています。
多様なニーズに対応することで、多くの視聴者を獲得している事例です。
YouTubeで集客する場合の注意点

YouTubeで集客する場合の注意点は、下記のとおりです。
- YouTubeに対する知識が必要
- 成果が出るまで時間がかかる
いずれにおいても、運営に大きな影響があるため、それぞれ確認しましょう。
YouTubeに対する知識が必要
YouTubeで集客するには、YouTubeに対する知識が必要です。
YouTubeは、世界最大の動画共有サイトであり、毎日何億回もの動画が視聴されています。
しかし、その中で自分の動画が目立つようにするには、下記の基本的な知識が必要です。
- どのような動画を作るべきか
- どのようなタイトルやサムネイルを付けるべきか
- どのようなキーワードやタグを使うべきか
また、YouTubeは検索エンジンとしても機能しており、GoogleやYahoo!などの検索結果にも表示されます。そのため、SEO(検索エンジン最適化)の知識も必要です。
さらに、YouTubeはSNSとしての側面もあります。そのため、視聴者とのコミュニケーションやファンづくりも重要です。
このように、YouTubeを運営するには、多くの知識を学ぶ必要があります。
成果が出るまでに時間がかかる
YouTubeには、成果が出るまでに時間がかかるという特徴があります。
YouTubeで多くの視聴者やチャンネル登録者を獲得するには工夫がいります。
YouTubeには数多くの動画やチャンネルがあり、その中で自分の動画やチャンネルを知ってもらう必要があるからです。
自社のチャンネルを知ってもらうには、自社の強みや他社との差別化ポイントを明確にし、ターゲットに的確に訴求する必要があるのです。
また、動画を撮影するための機械や技術も必要になるため、始めるまでにも時間がかかります。
このように、YouTubeで集客する場合は成果が出るまで時間がかかるため、長期的な視点で取り組むことが重要です。
YouTubeを使った集客はNOGICへお任せ
YouTubeを使った集客は、NOGICへお任せください。
NOGICは、累計100チャンネル以上の運用事例を誇り、動画の企画から制作まで幅広く受けています。
NOGICでは編集・企画パッケージと運用フルパッケージの2種類のプランを用意しているので、自社で運用が難しい業務を請け負うことが可能です。
また、NOGICでは、YouTubeチャンネルが上手くいかない方に対する無料診断も行っています。
YouTubeを使った集客に興味がある方は、まずはNOGICにご相談ください。