採用活動にYouTubeを活用したいと考えているが、具体的な方法がわからず導入に至っていないという方も多いのではないでしょうか。
実際、採用にYouTubeを活用する際のポイントを押さえることは難しく、導入してもうまく活用できず苦労する企業も少なくありません。
そこで今回は、採用活動にYouTubeを効果的に活用する方法を解説します。
動画の方向性の設定から、KGI/KPIの設定、他SNSとの連携など、具体的なポイントにも触れるため、ぜひ参考にしてください。
そもそも採用でYouTubeの活用はおすすめ?

採用活動にYouTubeを活用することは、非常に効果的な戦略です。
まず、YouTubeを通じて求人広告や文字情報だけでは伝えきれない職場の雰囲気など、企業の魅力を直接的に伝えることが可能です。
文章だけでは伝えきれない視覚情報によって、応募者は企業の価値観をより深く理解でき、ミスマッチを減らすことができます。
さらに、YouTubeには広範な利用者層が存在し、必要なスキルを持つ候補者からの応募数を増やせる可能性も高まります。
特に若年層の利用率が高いYouTubeは、新卒採用や若手人材の獲得に効果的です。
このように、YouTubeを採用活動に活用することで、応募者数の増加、質の向上の両方を実現できます。
ビジュアルコンテンツの力を借りて、より効果的な採用戦略を展開できるでしょう。
採用活動でYouTubeを利用する場合の進め方

採用活動でYouTubeを利用する場合の進め方は、3ステップあります。
- 動画の方向性を考える
- 動画を作成する
- 動画を投稿する
採用戦略を成功させるために、計画的にアプローチしましょう。
動画の方向性を考える
採用活動でYouTubeを活用する際、最初に行うべきは動画の方向性を明確にすることです。
企業が訴求したい内容から逆算して、どのような動画を制作するかを決定します。
例えば、風通しの良さをアピールしたい場合、社長を巻き込んだドッキリ企画などが効果的です。
「ながの社長」や「ブラック社長」のチャンネルでは、このようなアプローチが成功を収めています。
成長機会の豊富さを強調したいときには、「ブラックな社長」や「ゆとらない日々」などのチャンネルを参考に、社内のノウハウ発信や企画会議の様子を公開します。
また、社内の良好な人間関係をアピールする際には、「三和交通」や「ライソン」のような社員によるネタコンテンツやダンス動画なども有効です。
動画を作成する
動画の方向性が決まったら、実際の制作に移ります。
YouTubeの一般的な動画尺である10分前後を目安に、社内の雰囲気や社員インタビューなどを織り交ぜながら、視聴者の興味を徐々に高めていくことが大切です。
採用活動に特化した動画では、以下の要素を盛り込むことで、求職者の関心を引き付けることができます。
- 企業理念や価値観の紹介
- 社員における1日のルーティンや業務内容の紹介
- 社内イベントや福利厚生の様子
- 成長の機会や研修制度の説明
- 社員の成功事例や成長ストーリーの共有
上記のような要素を組み合わせることで、求職者に対して企業の魅力を多角的に伝えましょう。
動画を投稿する
動画を制作したら、実際にYouTubeへ投稿します。
認知度の高い企業や、採用活動に十分な予算をかけられる企業であれば、YouTubeの通常尺の動画から始めても良いでしょう。
しかし、知名度が低かったり、採用予算が限られている場合は、まずショート動画で認知度を高めていく戦略が有効です。
さらに、YouTubeと併せてInstagramなどのSNSの活用によって、より効果的な採用活動が可能です。
例えば、Instagramのストーリー機能を使って視聴者からの質問に答えたり、企業の日常を共有したりすることで、求職者との双方向のコミュニケーションを実現できます。
YouTubeを活用した採用活動は、単に動画を投稿するだけでなく、戦略的なアプローチが求められます。
採用でYouTubeを活用する際の重要なポイント

採用でYouTubeを活用する際の重要なポイントには、以下の6つが挙げられます。
- KGIを明確にする
- KPIを設定する
- 他SNSの特徴を押さえ、目的に合わせて併用する
- 複数のSNSを効果的に活用する
- ショート動画を活用する
- 他社の事例から自社の方針を決める
効果的な採用動画マーケティングを展開するため、明確な目標設定と綿密な計画を立てる参考にしてください。
KGIを明確にする
YouTubeを使った採用活動におけるKGI(重要目標達成指標)の設定は、成功したかを判断するために必要です。
多くの企業は、採用人数と採用者の質を主要なKGIとして掲げています。
特に採用者の質に関しては、具体的なスキルセットや経験年数などを数値化し、明確な基準を設けます。
例えば、「プログラミング経験3年以上で、チームリーダー経験のある開発者を5名採用する」といった具体的な目標を立てることで、YouTubeを含む採用活動全体の方向性を明確にしましょう。
KPIを設定する
YouTubeを活用した採用マーケティングの成功を測るためには、適切なKPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。
主要なKPIとしては、以下の4点が挙げられます。
- 応募者数
- 書類選考通過率
- 面接通過率
- 採用コスト
特に注目すべきは、応募者数と採用コストです。
この指標を改善したい場合、YouTubeショート動画の活用が効果的です。
一方、通過率や選考率の向上を目指す場合は、より詳細な情報を提供できる長尺のYouTube動画が適しています。
このように、KPIに基づいて適切な動画戦略を選択することで、採用活動の効率を大幅に向上させることができます。
他SNSの特徴を押さえ、目的に合わせて併用する
YouTubeだけでなく、他のSNSプラットフォームも効果的に活用することで、採用活動の成功率を高めることができます。
各SNSには独自の特徴があり、それぞれの役割を明確にした運用が不可欠です。
- TikTok:認知度の拡大と応募検討者の母数拡大
- YouTube:採用のミスマッチを防ぎ、質の高い応募者数を増やす
- Instagram:応募検討者とのコミュニケーションツール
上記のSNSを目的に合わせて併用し、より包括的な採用戦略を展開しましょう。
複数のSNSを効果的に活用する
YouTubeを利用した採用では、複数のSNSを連携させて、応募者の採用プロセスを効率化することも大切です。
具体的には、TikTokで企業の魅力や仕事への姿勢を簡潔に紹介し、興味を持った応募検討者をYouTubeチャンネルへ誘導します。
その後、YouTubeではより詳細な職場環境や業務内容を紹介することで、ミスマッチを防ぎつつ、質の高い応募者を増やします。
さらに、Instagramの質問箱機能を活用して、応募を検討している求職者の疑問を直接解消しましょう。
このように、各SNSの特性を活かした情報提供により、効果的な採用活動を実現することが成功のポイントです。
ショート動画を活用する
採用活動において、ショート動画の活用は非常に効果的です。
YouTubeだけに限らず、TikTokであればは10代、20代の利用時間がもっとも長く、30代、40代の利用も増加傾向にあります。
こうしたショート動画の特徴として、企業の雰囲気が伝わりやすく、求める人材に直接アプローチできる点が挙げられます。
また、費用対効果が高く、TikTokのショート動画をInstagram ReelsやYouTube Shortsなど他のプラットフォームでも転用可能です。
さらに、フォロワーを効率的に増やしやすいという利点もあるほか、収益化にも繋がります。
この利点を活かし、ショート動画を採用戦略の中心に据えることで、効果的かつ効率的な採用活動を展開できます。
他社の事例から自社の方針を決める
YouTubeを筆頭に、多くの企業が動画、特にショート動画を活用した採用活動で成功を収めています。
例えば、三和交通はTikTokを使用してタクシードライバーの日常を魅力的に紹介し、応募者の増加に成功しています。
また、家電メーカーライソンは、製品開発の裏側や社員の働き方を紹介する動画で注目を集めた企業です。
最後に、大京警備は、警備員の仕事の重要性や魅力を伝える動画で、業界のイメージ向上に貢献しています。
こうしたすでにある成功事例を参考にしつつ、自社の特性や求める人材像に合わせた独自戦略を構築することが大切です。
他社の成功例を単に真似するのではなく、自社の強みを活かした独自のアプローチを見出しましょう。
YouTubeの採用はNOGICにお任せ!
採用活動にYouTubeを活用することは、今や効果的な戦略として注目を集めています。
採用活動に活用することで、テキストや静止画では伝えきれない御社の魅力を、より生き生きと伝えることができます。
しかし、何も考えずに動画を撮って公開するだけでは費用とリソースを投じるだけで終わりかねません。
そのため、NOGICでは単なる動画制作にとどまらず、企画段階から採用戦略全体を見据えた上で、目的に応じた多様なコンテンツの企画・制作を支援しています。
採用にYouTubeを活用したいと考えた際にはぜひNOGICにご相談ください。
「YouTubeでの発信を始めたいけれど、どうすればいいかわからない」
「カーディーラー業界で差別化を図りたい」というお悩みはありませんか?
現代のビジネスシーンでは、デジタルマーケティングの重要性が高まっています。
しかし、カーディーラー事業を運営している方々の中には、YouTubeを活用するメリットや具体的な始め方が分からない方も少なくありません。
この記事では、カーディーラーとYouTubeの相性について掘り下げ、YouTubeを始めることのメリットを具体的に解説します。
YouTubeを通じて、売り上げを上げたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
カーディーラーとYouTubeの相性は?

カーディーラーがYouTubeを活用することのメリットは、視覚的な魅力にあります。
自動車はデザイン、性能、そして走行シーンなど、視覚に訴える要素が豊富です。
YouTubeは、こうした動画コンテンツを気軽にアップロードし、多くのユーザーに見てもらえるため、カーディーラーにとって非常に相性の良いツールです。
また、カーディーラーがYouTubeで情報発信を行うことには、ブランド認知度や、顧客との信頼性の向上といったメリットもあります。
例えば、新しいモデルの紹介や、特定の車種の詳細なレビューなど、ユーザーが求める情報を提供することで、信頼感や専門性をアピールできます。
さらに、ユーザーからのコメントや質問に返信することで、直接的なコミュニケーションが図れ、顧客との関係を深めることができるでしょう。
現在、カーディーラー業界においてYouTubeを積極的に活用している企業はまだ多くありません。
他の業界に比べてデジタルマーケティングの導入が遅れている面もありますが、逆を言えば参入障壁が低いとも言えます。
カーディーラーがYouTubeを始めるメリット
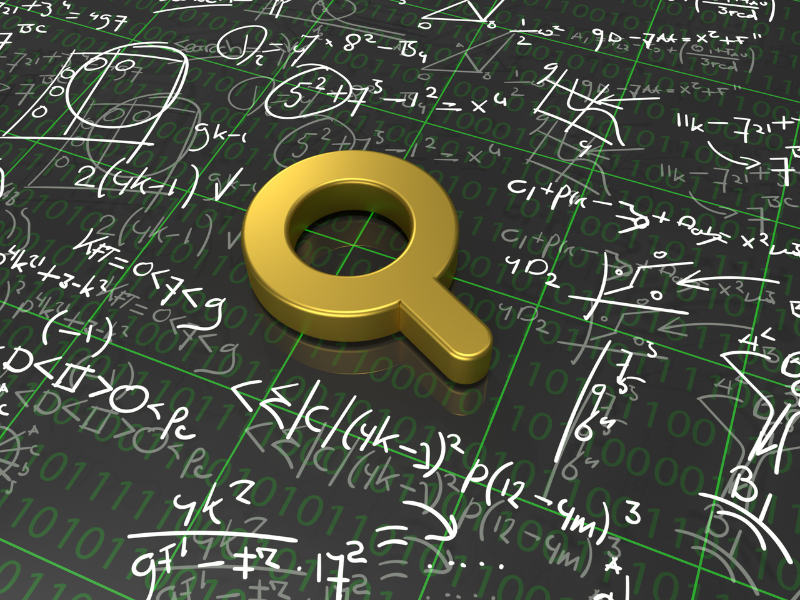
カーディーラーがYouTubeを始めるメリットは、主に3つあります。
- お問い合わせが増える
- 知名度が高まる
- 信頼感の向上が図れる
以下で詳しく解説していきます。
メリット①:問い合わせが増える
メリットの1つ目は、問い合わせ数の増加です。
YouTube動画を通じて、様々な車種を紹介することができるため、視聴者は自分の好みやニーズに合った車を見つけやすくなります。
例えば、テキストだけでは伝わりづらい内装の質感をリアルに伝えることができ、視聴者の購買意欲を刺激することができます。
さらに、YouTubeチャンネルを定期的に更新し続けることで、視聴者との間に信頼関係を築くことが可能です。
ディーラーの人柄や専門知識が視聴者に伝わり、親近感を持たれるようになると、「この人から車を購入したい」という動機が生まれます。
実際に「この人と話したいから車を買いに行く」と考える視聴者も少なくありません。
こうした視聴者は、販売員とのコミュニケーションを重視する傾向にあり、結果として問い合わせにつながります。
メリット②:知名度が高まる
2つ目のメリットは、「知名度の向上」が挙げられます。
YouTubeは、車が好きなターゲット層に直接アプローチすることが可能です。
特に車に興味がある人々は、新しいモデルのレビューやドライブの楽しさを伝える動画などに目を留めやすいです。
そうしたコンテンツを提供することで、自然とディーラーの名前が覚えられるようになります。
さらに、YouTubeでの動画がバズることは、それ自体が大きな宣伝効果をもたらします。
バズる動画とは、視聴者に強い印象を与え、共感や感動を呼び、多くのシェアやコメントを生むようなコンテンツのことです。
実現すると、ディーラーの存在を知らなかった人々にも広がり、結果としてブランドの知名度は大きく跳ね上がるのです。
YouTubeのアルゴリズムは、人々の関心を引くコンテンツを優先的に推薦するため、一度バズるとその影響力はとても大きくなります。
知名度を高めることは、ただ多くの人に名前を覚えてもらうだけでなく、ディーラーとしての信頼性や専門性をアピールするチャンスでもあります。
メリット③:信頼感の向上が図れる
3つ目のメリットは、「信頼感の向上」です。
YouTubeでディーラーが出演することで、視聴者は人柄や接客態度を直接見ることができます。
さらに動画でのコミュニケーションは、視聴者にとってスタッフを身近な存在感に感じさせることが可能です。
また、アフターサービスの様子を公開することで、購入後のサポートもしっかりしていることをアピールできます。
このように、実際の店舗での接客と同様に、オンライン上でも信頼を築くことができるのです。
信頼感が向上すると、ディーラーに対してポジティブなイメージを持ち、店舗を訪れた際には既に一定の信頼関係が築かれている状態になります。
その結果、お客様は購入に対する心理的ハードルが低くなり、実際に車を購入してもらいやすくなるのです。
信頼関係が成約率に直結するカーディーラーにとって、YouTubeはお客様との関係を深めるための重要なツールと言えます。
カーディーラーがYouTubeを始める上で注意すべき2つのポイント

カーディーラーがyoutubeを始める上で注意するべきポイントは2つあります。
- 炎上の恐れがある
- 動画投稿に手間がかかる
以下で詳しく解説していきます。
注意点①:炎上の恐れがある
YouTubeを活用することは、カーディーラーにとって大きなチャンスですが、同時に炎上のリスクも伴います。
特に、車の性能や安全性に関する誤った情報を提供したり、不適切な表現を使用したりすると、視聴者からの批判を受ける可能性があるからです。
このような炎上は、カーディーラーとしての信頼を大きく損なうことになりかねません。
車の性能や特徴について語る際は、メーカーから提供された公式な情報を基にし、誤解を招かないように注意深く情報を選びましょう。
差別的な表現は絶対に避け、誰もが快適に視聴できるコンテンツを心がけることが大切です。
万が一、炎上してしまった場合は、できるだけ早く状況を把握し、対応策を検討します。
正確な情報の提供と適切な表現を心がけることで、炎上のリスクを最小限に抑え、YouTubeを有効に活用しましょう。
注意点②:動画投稿に手間がかかる
YouTube投稿は、動画の企画、撮影、編集などの作業に相応の手間がかかります。
特に初めてYouTubeチャンネルを運営する場合、想像以上に時間と労力を要することがあります。
その結果、本業に割くべき時間が減少する可能性があるため、注意が必要です。
例えば、月に1回の新車紹介など、定期的なテーマを設けることで、撮影や編集のプロセスをスムーズに進めることができます。
また、動画制作の一部を外部のプロに委託することで、高品質なコンテンツを効率的に生産する方法もあります。
本業に支障をきたさないよう、動画制作にかかる手間を効率的に管理しましょう。
また、動画制作のプロセスを楽しむことも大切です。
自社の魅力を伝える動画を通じて、顧客との新たなコミュニケーションを築くことは、時間と労力をかける価値があります。
カーディーラーとして成功するためのポイント3つ

カーディーラーがYouTubeを活用して成功するためには、3つのポイントがあります。
- 定期的な更新を行う
- 誠実な運営を心がける
- 視聴者のニーズを捉える
以下で、1つずつ解説していきます。
1.定期的な更新を行う
YouTubeでの成功のポイントは、定期的なコンテンツの更新です。
視聴者は新鮮な情報を求めており、定期的に更新されるチャンネルを積極的に閲覧します。
また、定期的な更新はYouTubeのアルゴリズムにも好影響を与え、チャンネルの表示回数を高めることにつながります。
例えば、週に1回、特定の曜日に動画投稿することで、視聴者はそのチャンネルの更新を楽しみに待つようになるでしょう。
結果、視聴者との親近感が生まれ、ディーラーの好感度を高めることができます。
2.誠実な運営を心がける
誠実な運営は視聴者からの信頼を得るために不可欠です。
誠実さとは、自分の専門知識や経験に基づいて、正しい発言や振る舞いをすることを意味します。
この誠実さが欠けると、視聴者から「信頼できない」と思われ、長期的な関係構築に大きな障害となります。
自動車の専門家として、正確な情報を提供することはもっとも基本的な誠実さです。
新車や中古車の性能、特徴、価格などについて語る際は、常に最新かつ正確な情報を基にしてください。
誤った情報や誇張された内容を提供することは、視聴者の信頼を失うことにつながります。
また、YouTubeでは、コメント欄を通じて視聴者と直接コミュニケーションを取ることができます。
視聴者からの質問やコメントに対して、丁寧かつ迅速に返答することで、視聴者との信頼関係を築くことができます。
3.視聴者のニーズを捉える
3つ目のポイントは、視聴者のニーズを的確に捉えたコンテンツ制作です。
視聴者が何を知りたいのか、どのような情報を求めているのかを理解し、それに応える動画を制作することが重要です。
例えば、メンテナンスのハウツー動画など、視聴者が実生活で役立つ情報を提供することで、チャンネルの価値を高めることができます。
また、カーディーラーとしてYouTubeコンテンツを制作する際には、ターゲットとなる視聴者層を明確に定義することが重要です。
例えば、若年層をターゲットにする場合は、最新のトレンドやデザインに焦点を当てたコンテンツが効果的です。
一方で、ファミリー層をターゲットにする場合は、安全性や燃費、広さなどの要素を重視したコンテンツが求められます。
このようにターゲットを明確にすることで、より効果的に視聴者のニーズに応えるコンテンツを制作できます。
市場調査やターゲットの明確化を通じて、視聴者が求めるコンテンツを提供することで、チャンネルの魅力を高めることができるでしょう。
カーディーラーがYouTubeを始めるおすすめの方法2つ

効率的にYouTubeを活用するための方法は、主に2つあります。
- 動画制作の一部を外注する
- YouTube運用代行に依頼する
以下で詳しく解説していきます。
1.動画制作の一部を外注する
カーディーラーがYouTubeを始める際には、動画制作のプロセスを効率化することが大切です。
特に、動画編集は時間と技術を要するため、この部分を外注することで、時間の節約につながります。
動画編集とは、撮影された映像を切り取りエフェクトを加えるなど、視聴者にとって魅力的な内容に仕上げる作業です。
しかし、動画を自社で一から編集するには、専門的な知識や編集ソフトの操作スキル、さらには多くの時間が必要です。
そこで、動画編集を外注することをおすすめします。
外注を利用することで、動画の企画立案や撮影に専念でき、より質の高いコンテンツ制作に集中することができます。
また、動画編集に特化したプロに任せることで、視聴者を引きつける動画を作ることが可能です。
外注する際には、事前に編集者とコミュニケーションを取り、自社のブランドイメージや伝えたいメッセージをしっかりと伝えましょう。
また、編集のスタイルや納期、予算などの条件も明確にしておくことが重要です。
2.YouTube運用代行に依頼する
カーディーラーとしてYouTubeを始める際に効果的なのが、YouTube運用代行サービスの利用です。
運用代行サービスは、動画コンテンツの企画から撮影、編集、そしてアップロードに至るまでの一連のプロセスを行ってくれるサービスです。
YouTube運用には、動画の撮影や編集、さらにはSEO対策といった専門的な技術や知識が必要です。
しかし、代行サービスを利用すれば、これらの知識を持たないカーディーラーでも、質の高い動画を制作可能です。
また、運用代行サービスを活用することで、動画制作にかかる時間を大幅に削減し、その分他の業務を行えます。
このように、品質の高い動画コンテンツの提供、時間の節約、そして専門的な運用戦略により、効果的なマーケティング活動を行うことができます。
まとめ:カーディーラーでYouTubeを始めたい人はNOGICへ相談
カーディーラーとしてYouTubeを活用すると、顧客との接点を増やし、ブランドの信頼性と認知度を高めることができます。
さらに、動画を通じて価値ある情報を提供することで、視聴者の関心を引き、問い合わせの増加につなげることが可能です。
また、視聴者が動画を通じてスタッフの人柄を感じ取ることができれば、それが直接的な店舗訪問や購入に繋がります。
しかし、カーディーラーとしてYouTubeを活用し、事業の発展を図るためには、戦略的なアプローチと持続的な努力が必要です。
NOGICでは、YouTube戦略の立案から動画制作、チャンネル運用まで、一貫したサポートを提供しています。
YouTubeを活用したマーケティングを検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
「不動産投資のYouTubeはどのように運用すれば成功するの?」というお悩みはありませんか?
不動産投資は高額の費用がかかるため、不安を解消して正しく導くことが重要です。
この記事では、不動産投資のYouTubeチャンネルで成功した事例を紹介し、その運用方法を徹底解説します。
不動産投資のYouTubeを初めてみたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
不動産投資業界の特徴

不動産投資は、一般的に高額な商材を扱うため、投資家が一歩を踏み出すまでには大きな決断が必要となります。
例えば、物件の選び方、資金調達の方法、運用の戦略など、投資家が考慮すべき要素は多岐にわたります。
そのため、投資家は自身の投資スタイルに合った情報を探すことが必要ですが、その過程で多くの不安や疑問を抱くことも少なくないでしょう。
また、不動産投資には様々な考え方が存在し、一概に正解があるわけではありません。
このことから、情報提供者としては自身の意見を明確にし、投資家も迷わないように導くことが大切です。
【株式会社NOGIC事例】不動産投資のYouTubeで成功した事例

ここでは、不動産投資の情報をYouTubeで発信し、大きな成功を収めた弊社の事例を紹介します。
2か月で月間3.1万回再生、月間獲得面談数30件という結果を出すことのできた好例です。
弊社にご相談いただいたお客様は、もともと広く資産形成についてYouTubeで発信していた方です。
しかし、視聴者からの反応が芳しくなく、再生回数や面談の獲得数も伸び悩んでいました。
そこで、不動産投資という特定のジャンルに絞って情報を発信を始めました。
特定のジャンルに絞った理由は、主に2つあります。
まず、ターゲットの明確化です。不動産投資という特定のジャンルに絞ることで、視聴者が求める情報も明確になります。
その結果、視聴者が求める情報を的確に提供でき、視聴者からの反応も良くなりやすいです。
次に、情報の深堀りです。不動産投資というジャンルに絞ることで、そのジャンルについて深く掘り下げることが可能です。
そうすると、視聴者に対してより深い情報を提供できる結果、視聴者の満足度も高まります。
この事例から、YouTubeで情報発信を行う際には、特定のジャンルに絞った情報発信は効果的であることがわかります。
不動産投資のアカウントを運用する上で意識した5つのポイント

不動産投資は、その高いリターンと安定性から多くの人々が興味を持つ分野です。
しかし、YouTubeチャンネルの運用は、一筋縄ではいきません。
視聴者の興味を引き、チャンネルを成長させるためには、一定のポイントを押さえる必要があります。
本章では、不動産投資のYouTubeチャンネルを運用する上で意識したい5つのポイントを紹介します。
- ターゲットを絞る
- 何のジャンルで再生回数を取るのかを考える
- サムネにこだわる
- アカウントの意見を明確にする
- 視聴者が迷わない分かりやすい動線を作る
以下で詳しく解説していきます。
ポイント①:ターゲットを絞る
まず、YouTubeチャンネルの成功には、ターゲットを絞ることが非常に重要です。
ターゲットを絞ることで、チャンネルの方針を明確にし、視聴者に対してより具体的な価値を提供できます。
また、以下のメリットも得られます。
- 回遊率が高まることで動画の再生回数が増える
- ユーザーのより深い悩みを解決できることで、次のアクション(LINE登録、面談数)に繋がりやすい
- 何度も同じ人から動画を見てもらえる可能性が高まり、信用度が上がるため次のアクションにつなげやすい
具体的な事例として、弊社がコンサルティングを行った企業のケースを挙げてみましょう。
この企業はもともと、広くお金の悩みを持つ人をターゲットにしていました。
しかし、弊社のご提案で、ターゲットを「不動産投資で悩みを持つ人」に絞り込みました。
その結果、視聴者の具体的な悩みに対応した内容を提供することで、視聴者からの信頼を得ることができ、面談数などのKPIも大幅に向上できています。
このように、ターゲットを絞ることで、YouTubeチャンネルの運用効果を高めることが可能です。
特に不動産投資ジャンルでは、投資家の悩みや課題は具体的で深いため、ターゲットを絞り込むことで、視聴者に対して高い価値を提供し、チャンネルの成功につなげることができます。
ポイント②:何のジャンルで再生回数を取るのかを考える
次に、YouTubeでの再生回数を増やすためには、何のジャンルで再生回数を取るのかを考えます。
特に、不動産投資のノウハウを発信する動画と、再生回数を獲得するための動画を明確にわけることが効果的です。
まず、不動産投資のノウハウを発信する動画は、その専門性から既存のフォロワーに対する信頼性を高める役割を果たします。
具体的な投資方法や成功事例を紹介することで、視聴者に対して具体的な価値を提供し、チャンネルの信頼性を高めるのです。
一方、再生回数を獲得するための動画は、新規の視聴者を獲得するためのものです。
ここでは、ニーズが高く、時事性のある動画を発信することが重要です。
例えば、不動産市場の最新トレンドなど、多くの人が関心を持つテーマを取り上げることで、より多くの視聴者を引きつけることができます。
このように、不動産投資のノウハウを発信する動画と、再生回数を獲得するための動画を明確にわけることで、既存のフォロワーの信頼性を保ちつつ、新規の視聴者を獲得可能です。
ポイント③:サムネにこだわる
3つ目に、YouTubeの視覚的な要素の中でも特に重要なのが、動画の「サムネイル」です。
サムネイルは、視聴者が動画をクリックするかどうかを決定する最初の接点となるため、その訴求力は極めて重要となります。
また、ターゲットの違いによって、サムネイルの訴求内容も大きく変わります。
例えば、初心者をターゲットにする場合、サムネイルには「不動産投資の基本的な知識」など、初心者が興味を持ちやすい内容を盛り込みます。
一方、中級者以上をターゲットにする場合、「最新の投資情報」や「成功事例の紹介」など、より深い情報を求める視聴者に対する訴求が良いでしょう。
サムネイル作成は、Canvaなどの無料のデザインツールを活用することで、初めてでも簡単に取り組むことができます。
ポイント④:アカウントの意見を明確にする
YouTubeチャンネルを運営する上では、アカウントの意見を明確にすることも大切です。
視聴者は、自分の価値観に近い、または自分が学びたいと思う情報を提供するチャンネルを選びます。
そのため、チャンネルが何を提供し、どのような立場を取るのかを明確にすることで、視聴者の選択を助け、ファン化につなげることができるからです。
例えば、「資産を最短で伸ばす不動産投資が正義」という方針を立てるのか、それとも「節税対策になる不動産投資・区分投資などのリスクが限りなく低いが資産を増やすことに繋がらない投資には否定的な立場をとる」のかを明確にします。
この立場を明確にするだけでも、視聴者はチャンネルが自分の投資方針に合っているかどうかを判断しやすくなります。
また、初見の視聴者は、チャンネルが提供する情報の価値を判断するために、まずはチャンネルの立場を理解しようとします。
そのため、チャンネルの立場が明確であればあるほど、初見の視聴者が定期視聴者になる可能性も高まるのです。
ポイント⑤:視聴者が迷わない分かりやすい動線を作る
最後のポイントは、不動産投資に関するYouTubeチャンネルを運営する際、視聴者が迷わないように分かりやすい動線を作ることです。
視聴者がチャンネルを訪れた後、どの動画を見るべきか、どのようにチャンネルに登録するか、そして最終的にはどのように提供するサービスや商品につながるかを伝えます。
この部分を明確に示すことで、視聴者の行動を促すことができます。
ここで重要なのが、視聴者に対する「呼びかけ」です。
例えば、ターゲットに魅力的なLINE専用の特典を提供することで、LINEに誘導します。
また、LINEに登録した後の手順を動画でわかりやすく説明することで、安心して登録を促すことができます。
他にも「この動画が気に入ったらチャンネル登録をお願いします」や「詳しい情報は下の説明欄にリンクを貼っています」なども挙げられるでしょう。
このように、視聴者が迷わないように分かりやすい動線を作ることで、視聴者の行動を促し、チャンネルの成果を最大化することが大切です。
不動産投資ジャンルでYouTubeを運用する上での注意点

YouTubeは不動産投資のような専門的な知識を必要とする分野でも、理解しやすく伝えることが可能です。
しかし、その一方で、適切な運用をしなければ、逆に誤解を招く可能性もあります。
そのため、以下の5点に注意しながら運用することが重要です。
- 綿密な市場選定を行う
- チャンネルで発信する内容の方針を明確にする
- ターゲットを言語化する
- 競合よりも充実したコンテンツを作成する
- 面談までの導線を作り込む
それぞれを詳しく解説します。
注意点①:綿密な市場選定を行う
まず、YouTubeでの不動産投資ジャンルでは、綿密な市場選定を行います。
自社の強みから逆算して、参入する市場の隙間を探す必要があるからです。
参入を考えている市場に、すでに競合がいるのかを確認しましょう。
競合チャンネルのコンテンツの質、視聴者の反応、コメント欄の内容などを分析することで、自社のコンテンツが市場に受け入れられる可能性を見極めることができます。
次に、競合がいる場合、その競合に勝てるのかを考えてみましょう。
自社の強みは何か、それを活かして競合と差別化できるコンテンツを提供できるのかを検討することが求められます。
また、競合チャンネルがない場合でも、近しいジャンルのコンテンツが伸びているのかを確認することも重要です。
例えば、不動産投資に関連する金融知識や、不動産市場の動向について解説するチャンネルが人気の場合は、不動産投資に関するコンテンツに対する需要があることを示しています。
そのような市場の動向を把握することで、自社のコンテンツがどのように受け入れられるかのヒントを得ることができます。
注意点②:チャンネルで発信する内容の方針を明確にする
不動産投資におけるYouTubeチャンネル運用では、何を発信するか、どのような立場で発信するかという方針が重要です。
なぜなら、視聴者がチャンネルを選ぶ理由となるだけでなく、あなた自身がコンテンツを作る際の指針となるからです。
まず、何を発信するかについて考えてみましょう。
不動産投資には、様々な手法があります。
例えば、一棟買い、区分所有、海外不動産投資など、その範囲は広大です。
予算という制約がある以上、すべての手法をカバーするのは難しいでしょう。
そこで、自社が得意とする、または特化したい領域を選び、その領域に関する情報を発信することをおすすめします。
その結果、特定のニーズを持つ視聴者に対して、深い情報を提供できるはずです。
次に、どのような立場で発信するかについて考えてみましょう。
例えば、初心者向けの情報をわかりやすく解説する「教育者」の立場で発信するのか、自身の投資経験を元にリアルな情報を提供する「経験者」の立場で発信するのか、などが例として挙げられます。
いずれも全く異なるアプローチであり、視聴者からの評価や反応も変わってきます。
こうした方針を明確にすることで、自社の立ち位置が明確になり、視聴者にとってもチャンネルが何を提供してくれるのかがはっきりします。
注意点③:ターゲットを言語化する
不動産投資のYouTube運用において、ターゲットを言語化することも大切です。
ここでのターゲットとは、動画を見てほしいと思う具体的な人物像のことを指します。
明確にすることで、自社の方針を明確にし、動画の方向性のブレも抑えられます。
例えば、ターゲットが「不動産投資に興味があるが、まだ手を出していない20代〜30代のサラリーマン」であるとしましょう。
この場合、動画の内容は「不動産投資の基礎知識」や「成功するためのポイント」、「リスクの回避方法」など、初心者が知りたいと思う情報を提供することが求められます。
また、グラフや図表を用いる、専門用語をなるべく避けて説明するなど、視聴者の理解を助ける工夫も必要です。
一方で、ターゲットが「すでに不動産投資を始めているが、さらなる収益向上を目指している40代〜50代のビジネスパーソン」であるならどうでしょうか。
おそらく動画の内容では「最新の市場動向」や「成功事例の紹介」、「高度な投資戦略」など、より深い知識や情報が求められます。
また、具体的な数字やデータを用いて説明する、専門用語を使って深い議論をするなど、視聴者の知識レベルに合わせた配慮が有効でしょう。
このようにターゲットを言語化することで、どのような内容の動画を作成すべきか、どのように伝えるべきかが明確になります。
注意点④:競合よりも充実したコンテンツを作成する
YouTubeでの不動産投資ジャンルの成功には、競合他社との差別化も不可欠です。
そのためには、競合他社よりも充実したコンテンツを作成することが求められます。
まず、競合他社の動画を徹底的にリサーチしましょう。
例えば、その動画がどれだけの視聴者を獲得しているのか、コメントやいいねの数はどれくらいなのか、などが挙げられます。
それぞれの情報から、視聴者が何を求めているのか、どのようなコンテンツが好評なのかを見極めるのです。
次に、自社の動画が競合他社の動画よりも見やすいかどうかを確認します。
視聴者が動画を見続けるためには、視覚的な要素が重要です。
例えば、画面の構成や色使い、フォントの選択など、目に見える要素を工夫することで、視聴者にとって見やすい動画を作ることができます。
そして、競合他社よりもリッチなコンテンツを作りましょう。
最新の市場動向や成功事例、失敗事例など、視聴者が他では得られない情報を提供することが、視聴者を獲得するポイントです。
注意点⑤:面談までの導線を作り込む
最後に、視聴者が安心して行動に移せるような導線作りも重要です。
主に、視聴者が問い合わせやLINE登録などのアクションを取りやすいような環境を整えます。
例えば、動画の説明欄やエンドスクリーンに問い合わせ先のリンクを設置することで、視聴者が行動に移しやすい環境を作ることができます。
また、視聴者が面談を申し込む際に、その手順が複雑であると行動をためらう可能性もあるでしょう。
そのため、面談の申し込み手順を動画内で具体的に説明しておくフォローアップも有効です。
さらに、視聴者がスムーズに面談の申し込みができるよう、手順をシンプルにし、迷わないような導線を作りましょう。
このように、視聴者が安心して行動に移せるような導線を作ることで、不動産投資のYouTube運用の成功につながります。
不動産投資のYouTubeを始めたい方はNOGICにご相談!
不動産投資ジャンルでYouTubeを運用する際には、競合との差別化、魅力的なコンテンツ作成、視聴者の行動を促す導線作りなどが重要です。
特に、不動産投資という専門性の高い分野では、視聴者のニーズに応じた具体的な情報提供が求められます。
しかし、簡単にニーズといっても、そのジャンルや伝えられる情報の選択には非常に複雑な分析を必要とします。
不動産投資に特化したYouTubeチャンネルの立ち上げを行いたい方は、ぜひNOGICにご相談ください。
専門的な知識と豊富な事例を基に、チャンネルが成功するためのサポートを提供します。
すでにYouTubeを運営している方も、無料診断を実施しているので、お気軽にお声がけください。
「YouTubeを使って集客したいけど、どうすればいいのか分からない」という悩みをお持ちではありませんか?
視覚的に情報を伝えやすいYouTubeは、クリニックの集客に大いに役立ちます。
しかし、YouTubeを始めるにあたっては、ただ動画をアップロードするだけではなく、適切な戦略が必要です。
そこで、この記事では、具体的な成功事例を参考にクリニックジャンルでYouTubeを成功させる方法を徹底解説します。
これからYouTubeを始めようと考えているクリニック経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
クリニックはYouTubeを始めるべき?

新たなマーケティング手段として、YouTubeを検討しているクリニックも多いのではないでしょうか。
結論から言うと、クリニックを運営している場合はYouTubeによる発信がおすすめです。
YouTubeは、世界中で2番目に多く利用されている検索エンジンであり、毎日何百万もの動画が視聴されています。
その中には、健康や美容に関する情報を求めている人々も多く含まれています。
このことから、問題を解決できる・軽減できる専門的な内容をわかりやすく発信することで、多くの方へアプローチが可能です。
このように、YouTubeはクリニックのマーケティングにおいて有効な手段です。
クリニックジャンルの特徴

クリニックジャンルの特徴は主に2つあります。
- 視聴者が根深い悩みを持っている
- 解決に高額な費用がかかる
以下で詳しく解説していきます。
視聴者が根深い悩みを持っている
クリニックジャンルの視聴者は、自身の健康や美容に関する根深い悩みを解決するための情報を求めていることが多いです。
例えば、肌のトラブルや体調不良など、自身で解決できない問題を抱えている方は、専門的な知識を持つクリニックの動画を視聴することで、解決策を見つけようとします。
このような視聴者のニーズを満たすためには、正しい知識をわかりやすく伝えることが大切です。
専門的な医学用語を一般的な言葉に置き換えて説明したり、視覚的な図解やアニメーションを用いて理解を深めることが必要です。
そのため、正確でわかりやすい情報を提供することで、視聴者の信頼を得て、クリニックのブランド力を高めることができます。
解決に高額な費用がかかる
視聴者が施術を受ける場合、その費用は高額になる可能性があります。
しかし、この高額な費用が視聴者にとってハードルとなり、施術を受けることをためらう方も少なくありません。
そのため、クリニック経営者としてYouTubeを活用する際には、視聴者が自身でできる対処法や予防法を紹介することも重要です。
例えば、「シミの予防法」について動画を投稿する場合、日焼け止めの選び方や正しい塗り方、紫外線対策の具体的な方法などを紹介できます。
しかし、自分でできる対処法を紹介する際には、専門的な知識を持つ医師や看護師が正確な情報を提供することが求められます。
誤った情報を提供すると、視聴者の健康を害する可能性があるため、注意が必要です。
そのため、クリニック経営者は、正しい対処法を伝えるコンテンツ作りを心がけましょう。
YouTubeで成功した事例

クリニックジャンルで成功した事例を紹介します。
本チャンネルでは、2022年12月時点で再生回数が24.8万回、登録者数が836人でした。
しかし、ショート動画の投稿へと方針を切り替え、通常の動画で自社のサービス内容を投稿することにしました。
その結果、わずか1年1か月の間で、登録者数は1.8万人増加し、視聴回数は391万回再生にまで跳ね上がっています。
以下で、成功した理由を詳しく解説していきます。
成功要因
YouTubeにただ動画をアップロードするだけでは、視聴者の目に留まることは難しいです。
そこで、成功要因となるのが「特定のジャンルに絞った投稿」と「コンテンツ数の増加」です。
YouTubeで注目を集めるためには、自分がどのジャンルに特化しているのかを明確にすることが重要です。
例えば、今回の事例の場合、「腸内洗浄」に特化した投稿を行うことで、その分野に興味を持つ視聴者から注目を集めました。
こうした特定のジャンルに絞ることで、自分の専門性をアピールすることも可能です。
また、YouTubeは、投稿された動画の数が多いほど、そのチャンネルが推奨されやすくなるという特性があります。
したがって、定期的に動画をアップロードし、コンテンツ数を増やすことで、着実に再生回数を増やしていくことが可能です。
YouTubeショートであれば、短いコンテンツを多数配信できます。
今回の事例でも、ショートでYouTube上での情報露出を増やした結果、登録者数が増えています。
再生回数が増えた要因
YouTubeの再生回数を増やすために効果的な施策は、以下の3つです。
- 有名人とのタイアップ
- 認知獲得に強いショート動画の活用
- チャンネル全体として特定の悩みに特化する
それぞれの活用によって、クリニックジャンルのYouTubeチャンネルでも再生回数を増やすことが可能です。
まず、有名人とタイアップすることによって、その人物のファンからの視聴が見込めるため、再生回数を増やすことができます。
次に、ショート動画は、視聴者が手軽に視聴できるため、再生回数を増やすのに有効です。
特に、クリニックの場合、施術の様子やアフターケアの方法などをショート動画で紹介することで、視聴者の関心を引くことができます。
さらにチャンネル全体として特定の悩みに特化することで、悩みを持っている人々からの視聴が見込めます。
そのため、情報を求めてYouTubeを検索する人々が、そのチャンネルの動画を見つけやすくなります。
成功したチャンネルに見られる特徴

成功したチャンネルには特定の特徴が見られます。
それは、専門性の高さを活かしたポジショニングを取ることで、特定の悩みを持つユーザーを着実に獲得するというものです。
ポジショニングとは、自社の商品やサービスが市場の中でどのような位置づけになっているかを明確にすることです。
これにより、自社の強みや特徴を強調し、競合他社との差別化を図ることができます。
クリニックの場合、その専門性を活かしたポジショニングを行いましょう。
例えば、アンチエイジングや美白など、特定の悩みを持つユーザーに対して、その解決策を提供することで、ユーザーの信頼を得ることができます。
結果、ユーザーは自分の悩みを解決できるクリニックとして認識し、訪れる可能性が高まります。
クリニックジャンルでYouTubeを始めるステップ

クリニックジャンルでYouTubeを始めるステップは主に3つあります。
- アカウントの設計
- コンテンツ設計
- 有名人とのタイアップ
以下で詳しく解説していきます。
ステップ1.アカウントの設計
YouTubeを活用したクリニックのプロモーションを成功させるためには、まずアカウント設計が重要となります。
その中でも特に重要なのが、自身が何の専門家であるか、そして何の悩みを解決するのかを明確にすることです。
例えば、美容皮膚科の場合、その専門性を活かして「美肌になりたい」「肌トラブルを解決したい」といった悩みを持つ人に向けた情報発信を行います。
このように、自身の専門性と解決すべき悩みを明確にすることで、自身のYouTubeチャンネルにおける独自のポジションを決定できます。
その結果、視聴者がチャンネルを訪れた際に、自分が求めている情報を得られることを知り、チャンネル登録を行う可能性も高まります。
競合が多い場合でも、自身の専門性や視点を活かして差別化を図ることで、新たな市場を開拓することも可能です。
ステップ2.コンテンツ設計
次は、アカウント設計段階で設定したポジショニングをズラさないように、コンテンツを市場のニーズに合わせていくことが重要です。
まず、市場のニーズを把握するためには、自分のクリニックが提供するサービスや治療法について、どのような情報が求められているのかを調査します。
例えば、美容皮膚科クリニックであれば、最新の美容技術や肌の悩みに対するアドバイスなどが求められるでしょう。
次に、そのニーズに合わせたコンテンツを作成します。
そして、作成したコンテンツが市場のニーズに合っているかどうかを、YouTubeの数値(各種KPI)で確認します。
視聴回数や「いいね!」の数、コメントの内容などから、視聴者の反応を見ることができます。
また、YouTube経由でのお客さんの来院が増えているかどうかも、コンテンツが効果的であるかの重要な指標となります。
ステップ3.有名人とのタイアップ
最後に、自社が狙っているターゲット層に影響力がある有名人やインフルエンサーに依頼して、タイアップ動画をあげます。
有名人やインフルエンサーとのタイアップは、自社のブランドやサービスを広く知らしめる効果的な手段です。
特にYouTubeは、視覚的な情報を伝えることができるため、クリニックの施設や設備、スタッフの雰囲気などを具体的に伝えることが可能です。
さらに、有名人やインフルエンサーが自社のクリニックを訪れ、その様子を動画で公開することで、視聴者に対してリアルな体験も共有できます。
結果、より多くの人々にその動画を見てもらい、自社クリニックの認知度向上につながります。
ただし、ターゲット層とフォロワー層の一致、動画内容の工夫、動画の積極的なシェアなど、様々な要素を考慮する必要があります。
まとめ:クリニックジャンルでYouTubeを始めたい方はNOGICにご相談!
新たなマーケティング手段としてYouTubeを活用することは、非常に有効です。
YouTubeは、専門的な知識を広く伝え、視聴者の理解を深めるための情報を提供できる場です。
成功するためには、専門知識をわかりやすく伝え、視聴者の問題解決に役立つ情報を提供し、定期的にコンテンツを更新することが重要です。
しかし、成功のためのYouTube戦略を立てるのは簡単ではありません。
NOGICでは、クリニック専門のYouTubeチャンネル開設と運営の支援を行っており、多くのクリニックが成功を収めています。
専門的な知識を持つスタッフが、チャンネルの設計からコンテンツの制作、アップロードのタイミングの最適化まで、一貫してサポートします。
YouTubeを通じてクリニックの魅力を伝えたい方は、ぜひNOGICにご相談ください。
「自分のYouTubeチャンネルをもっと多くの人に知ってもらうために、SNSを上手く活用できないだろうか」という悩みはありませんか?
多くのクリエイターや企業が直面しているのが、コンテンツの露出不足と、効果的なマーケティング戦略が取れていないことです。
もちろん、YouTubeだけでも成果を目指すことは可能ですが、SNSを組み合わせることでその可能性をさらに広げることが可能です。
しかし、SNSを運用する際は、不適切な投稿による炎上リスクや、投稿内容が各SNSの特性に合っていないと効果を発揮できないという注意点も存在します。
そこでこの記事では、YouTubeとSNSを組み合わせて運用するメリットと、相性のいいSNSの選び方、そして実際に運用する際の注意点を解説します。
「自分のチャンネルを成長させたい」「SNSの活用法を知りたい」という方はぜひ最後までご一読ください。
YouTubeとSNSを組み合わせて運用するメリット

YouTubeとSNSを組み合わせて運用するメリットは、以下の4つが挙げられます。
- 宣伝効果が期待できる
- クロスプロモーションが可能になる
- コミュニケーションの促進に繋がる
- 既存のコンテンツを活用できる
それぞれの利点は、マーケティング戦略を最適化し、多角的なアプローチによって視聴者との結びつきを強化できるということです。
結果として、効果的なブランディングと収益化に繋がります。
それでは、各メリットについて以下で詳しく見ていきましょう。
メリット①:宣伝効果が期待できる
YouTubeとSNSの組み合わせによる運用では、高い宣伝効果が期待できます。
YouTubeの動画コンテンツをX(旧:Twitter)やInstagramといった他のSNSに共有することで、それぞれのプラットフォーム特有のユーザーにアプローチできるためです。
例えば、魅力的なサムネイルやメッセージ、動画のURLを投稿することで、その動画に興味を持ったユーザーをYouTubeチャンネルに誘導できます。
その結果、異なるターゲット層にもリーチ可能であり、YouTubeでは定着していない新しい視聴者層にもアプローチが可能です。
また、より広い範囲での拡散により、チャンネル登録者数の増加や収益化の促進にもつながります。
メリット②:クロスプロモーションが可能になる
複数のプラットフォームを横断したクロスプロモーションにより、コンテンツをより多くの人に届けることができます。
異なるプラットフォームでファンを獲得し、ブランドの認知度を全方位から高めることが可能です。
例えば店舗を経営している場合、顧客相談やコミュニケーションをInstagramで行い、詳細な情報を動画で伝える活動をYouTubeで行うといった使い分けが可能です。
このように、各プラットフォームの特性を活かしたコンテンツを作ることで、あらゆる角度からブランドや製品の魅力を発信することが可能です。
コンテンツの相乗効果によって視聴者のエンゲージメントを高め、最終的には売上増加にも繋がる可能性があります。
なお、クロスプロモーションを行う際は、各プラットフォームの特性をうまく利用し、統一感を持ってブランドメッセージを伝えることがポイントです。
メリット③:コミュニケーションの促進に繋がる
YouTubeは動画投稿と閲覧をメインとしたプラットフォームであり、即時的なコミュニケーションを行うには限界があります。
そこでX(旧:Twitter)などの他のSNSと組み合わせることで、視聴者との直接的なコミュニケーションが促進されるメリットもあります。
視聴者とのより深い繋がりを築くことで、ロイヤリティの高いファンの獲得にも期待できるでしょう。
例えば、YouTubeで投稿した動画に対してXで意見・感想を求めることで。コミュニティ内でのブランドや製品に対する積極的なフィードバックが得られやすくなります。
メリット④:既存のコンテンツを活用できる
YouTubeに投稿した長尺の動画コンテンツは、YouTube Shortsで活用できることはもちろん、TikTok、Instagramといった他のSNSの短尺動画や画像としても再活用できます。
コンテンツを再活用する際は、各SNSの利用者が好むコンテンツ形式に合わせることで、より多くの視聴者にリーチできます。
動画のハイライトやキーポイントを抽出し、短い動画として再構築するのも良いでしょう。
特に、TikTokとYouTubeはアルゴリズムの仕組みが似ているため、両プラットフォームでの成功につながるケースもあります。
これによって、コンテンツ制作の効率を高めるとともに、同じコンテンツでも異なる視聴者層にアプローチが可能です。
こうしたYouTube以外のプラットフォームでの露出を意識することで、新たな流入源にもなります。
YouTubeと相性のいいSNS

YouTubeと特に相性のいいSNSは、以下の4つです。
- X(旧Twitter)
- TikTok
- LINE
下記にて、各SNSでの効果的な活用方法について詳しく確認していきましょう。
相性のいいSNS①:X(旧Twitter)
YouTubeコンテンツの拡散には、X(旧Twitter)が極めて有効です。
YouTube動画のリンクをツイートすることで、瞬時にフォロワーへと情報が届き、動画へのアクセスが促されます。
また、リポストや「いいね」といった機能によって動画コンテンツのシェアも容易なため、さらなる拡散へと繋がりやすいのも特徴です。
その他のYouTubeとXの組み合わせ方の具体的な例は、次のとおりです。
- 視聴者によるフィードバックを受けるために、動画について意見を求めてみる。
- クリップ(動画の一部分)や動画のハイライトをツイートし、視聴者の関心を誘う。
- 特定のハッシュタグを使い、特定のトピックやトレンドに関連した動画として注目してもらう。
それぞれの戦略は、視聴者との安定したコミュニケーションを保ちつつ、YouTube動画に対する視聴回数や評価、登録者を増やすのに効果的です。
また、ユーザー交流が活発化するのもXを利用するメリットです。コラボ依頼やタイアップの依頼などは、ほとんどがXかInstagramのDMで行われるため、YouTubeを運用している方はX利用がおすすめです。
相性のいいSNS②:Instagram
Instagramを活用することの最大のメリットは、ストーリーで双方向のコミュニケーションが取れることです。例えば、ストーリーの質問機能で、悩みを募集して、質問に答えることで濃いファンを作ることができます。
また、InstagramはビジュアルコンテンツがメインのSNSであることで知られています。
そのため、YouTubeの動画コンテンツを視覚に訴えかけるような方法でプロモーションするのに適しています。
例えば、InstagramでのYouTube動画の活用は以下のように行えます。
- YouTubeの動画プレビュー、サムネイルやハイライトを共有することで、動画への興味を喚起し視聴を促す。
- ストーリーズにYouTube動画のプレビューをアップし、スワイプアップ機能(ストーリーズ中にリンクを挿入し、上にスワイプすると該当ページに遷移する機能)を使って本編へ誘導する。
- IGTVを活用し、長尺のYouTube動画もInstagram内で視聴できるようにする。
- ユーザーのカルーセル投稿(複数の写真やビデオを1つの投稿でスライドショー形式に見せる機能)にYouTube動画のハイライトを配置する。
このようにInstagramでYouTube動画を共有・再活用することで、動画のリーチ(到達範囲)を広げられるため、新規の視聴者獲得に繋がります。
相性のいいSNS③:TikTok
一般的に若年層ユーザーが多く、短い動画コンテンツがメインのTikTokも、YouTubeと相性のいいSNSの一つです。
YouTube動画のハイライトや視聴者の興味を引く瞬間をTikTokで共有することで、新しいチャンネル視聴者を獲得する絶好の機会が生まれます。
YouTubeコンテンツの効果的なTikTokでのシェア方法には、以下があります。
- TikTokのトレンドを取り入れた動画を投稿して、YouTube動画への興味を惹く。
- TikTokのプロフィール欄にYouTubeチャンネルへのリンクを配置し、フォロワーの誘導を図る。
- YouTubeの動画からTikTok用の短い動画を作りシェアする。
若い視聴者を獲得したい場合や、新規の視聴者層を開拓したい場合は、TikTokを活用してみるといいでしょう。
相性のいいSNS④:LINE
LINEはプライベートなコミュニケーションに特化したSNSであり、YouTube動画のパーソナライズなプロモーションを行うのに適しています。
具体的には、公式LINEアカウントを利用して最新の動画や情報を登録フォロワーに直接届けることができます。
これは、チャンネルへの熱量が高い視聴者にアプローチしたいときに高い効果を発揮するでしょう。
YouTubeコンテンツをLINEで宣伝する際の手法は、以下のとおりです。
- 公式アカウントを作成し、新しいYouTube動画をアップロードした通知を送る。
- 視聴者がすぐにアクセスできるようにニュースレターやメッセージで動画リンクを共有する。
- 特定の動画やイベント情報を公式アカウント経由で先行してファンに知らせる。
ただし、この方法は公式LINEアカウントに登録している視聴者に限定されるため、広告のメイン手段とすることはできません。
とはいえ、LINEは日本での利用率が高いため、YouTube動画の視聴者層のエンゲージメントをさらに高めたい場合はおすすめです。
YouTubeとSNSを組み合わせて運用するときの注意点

YouTubeとSNSを組み合わせて運用するときの注意点は、以下のとおりです。
- 離脱率が上がる可能性がある
- チャンネル登録に直接繋がらないこともある
- 各SNSの特性に合わせた投稿が必要になる
- 拡散性が高い分、炎上に留意する必要がある
- SNSのフォロワーが少ないと拡散力が期待できない
それぞれの注意点について、次項で具体的な説明をします。
注意点①:離脱率が上がる可能性がある
YouTubeとSNSを組み合わせた宣伝は非常に有効な手法ですが、懸念すべき点として離脱率の上昇リスクがあります。
離脱率とは視聴者が動画視聴を途中でやめる割合のことを指します。
SNSからYouTubeに遷移する際、多くはSafariなどのブラウザで動画が開かれます。
これが使用感を損ね、視聴者が動画を途中で閉じるリスクを高めてしまいます。
また、SNSは短いコンテンツが好まれます。
長いYouTube動画をそのまま投稿すると、視聴者の注意を引き続けることが難しいため、SNSに適した短い動画を作成する必要が生じるでしょう。
注意点②:チャンネル登録に直接繋がらないこともある
SNSからYouTubeに遷移させる場合、チャンネル登録に直接繋がるとは限りません。
なぜなら視聴者がブラウザを通じて動画を視聴する場合、YouTubeにログインしていない状態であることが多いためです。
その結果、チャンネルを登録することや、動画にグッドボタンをつけるハードルが上がってしまいます。
注意点③:各SNSの特性に合わせた投稿が必要になる
YouTubeのコンテンツをSNSで宣伝する際には、SNSごとの特性を理解し、それに合わせたアプローチを取ることが重要です。
SNSの特性を活かした投稿をするためには、次のアプローチが有効です。
- 各SNSで人気のフォーマットを分析し、それに沿った動画を制作する。
- ハッシュタグやキーワードを適切に使用して露出を高める。
- 視聴者からのエンゲージメント(反応)を高めるため、対話を促すための要素を取り入れる。
このように、SNSによって視聴者層、コンテンツの形式、対話性が異なることをふまえた戦略が必要です。
注意点④:拡散性が高い分、炎上に留意する必要がある
SNSの特性として、コンテンツが迅速かつ広範囲に拡散される可能性があります。
これは大きな宣伝効果となる反面、コンテンツが炎上(ネガティブな反応が大量に広がる現象)してしまうリスクもあります。
炎上のリスクを避けるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 不正確またはセンシティブな情報を避ける。
- 文化的、社会的な文脈に考慮したコンテンツを発信する。
問題が生じた際には、以下のように行動することが求められます。
- ネガティブなコメントや批判に対しては、迅速に反応する。
- 炎上時には透明性のある誠実な対応を心がける。
- 場合によっては公式の謝罪声明を発表し、対策についても共有する。
- 信頼を築くため、炎上後も定期的にフォローアップする。
このように、デリケートなテーマや確証のない情報は慎重に扱い、仮に炎上が起きてしまったら、素早く・誠実に対応することが大切です。
注意点⑤:SNSのフォロワーが少ないと拡散力が期待できない
SNSを使ってYouTube動画の宣伝を行う際には、SNSアカウントのフォロワー数も重要な要素となります。
フォロワー数が少ないとコンテンツの拡散力も低くなり、期待した宣伝効果を得ることができません。
もし宣伝のために新しくアカウントを作る場合、成長するまでに時間が必要なため、根気よく長期間にわたって管理していくことが大切です。
この場合は、以下の戦略を検討してみてください。
- コンテンツの質:高品質で価値のあるコンテンツを提供し、フォロワーを増やす。
- エンゲージメント:視聴者と積極的に会話し、コミュニティを形成する。
- インフルエンサーとのコラボレーション:フォロワー数が多いアカウントと交流する。
また、SNSでの存在感を保つためには、定期的にコンテンツをアップすることが大切です。
可能な範囲で、狙ったターゲット層に響くプロモーションを行い、自然とコンテンツを共有したくなるような関係を築きましょう。
YouTubeで成果を上げたいならSNSを活用するのがおすすめ
YouTubeでの成果を高めたいなら、SNSの活用が効果的です。
宣伝効果が期待できるだけでなく、クロスプロモーションが可能になること、コミュニケーションの促進に繋がること、コンテンツの再活用が可能になることなどさまざまなメリットがあります。
しかし、同時に注意すべき点もあるため、注意を払ったSNS運用が必要です。
YouTubeとSNSを上手く組み合わせれば、チャンネルの登録者数や再生時間をさらに伸ばすことが可能なので、ぜひ試してみてください。
YouTubeとSNSの最適な組み合わせで効果を最大化したいとお考えの方は、ぜひNOGICにご相談ください。
専門の知識を持ったメンバーが、チャンネルの状況やニーズに合わせた最適な戦略を提供いたします。
自社サービスの宣伝や消費者への商品訴求を行う際に、YouTuberの起用を考えたことがある方も多いのではないでしょうか。
人気があるYouTuberに、YouTuber自身のチャンネル内で自社商品を紹介してもらうことで、狙った年齢層へのリーチや、再生回数を伸ばすことが可能です。
一方で、費用面やキャスティングするYouTuberの選定など、頭を悩ませる要素も少なくありません。
こうした課題を解決すべく、本記事ではYouTuberをキャスティングするメリットや注意点、かかる費用やキャスティングの進め方について解説します。
本記事を参考にして、YouTubeチャンネルの成長と目的達成に役立ててください。
YouTuberをキャスティングするメリット5つ

YouTuberをキャスティングするメリットについて解説します。
- 狙った年齢層にリーチしやすい
- 特定の属性をもったユーザーをターゲティングしやすい
- 動画制作のプロに依頼できる
- 再生回数が伸びやすい
- SNSによる二次的な拡散も期待できる
それぞれのメリットを詳しく解説します。
メリット①:狙った年齢層にリーチしやすい
まずYouTuberをキャスティングすることにより、狙った年齢層にリーチしやすくなります。
YouTube公式によると、YouTubeは18歳から34歳の若者層が最も多く利用しており、他のメディアと比べても圧倒的な利用率を誇っています。
また総務省の調査によれば、全年代の利用割合は88.2%と非常に高く、あらゆる年齢層に対応していることも特徴です。
|
項目 |
調査利用率 |
|
10代 |
97.2% |
|
20代 |
97.7% |
|
30代 |
96.8% |
|
40代 |
93.5% |
|
50代 |
82.8% |
|
60代 |
68.1% |
|
全年代 |
88.2% |
そのため、YouTuberが確立しているフォロワー・コミュニティーに訴求できれば、狙った年齢層へ的確なアプローチが可能になるでしょう。
メリット②:特定の属性をもったユーザーをターゲティングしやすい
YouTuberのキャスティングは、特定の属性を持った視聴者を的確に狙いたい際にも役立ちます。
YouTuberは、個人が中心となりコンテンツを発信しているものがほとんどです。
そのため、その個性やライフスタイルが多くのフォロワーたちにとって共感の対象となり、特有のコミュニティを形成しています。
その結果、例えば以下のように様々な属性に基づいて対象を絞り込めるのです。
- 性別
- 年収
- 趣味・関心事
- 世帯構成(子どもの有無等)
これにより、特定の趣味、興味、生活様式を持つユーザーグループに対して高精度なターゲティングが行えるでしょう。
メリット③:動画制作のプロに依頼できる
動画制作のプロであるYouTuberは、高品質なコンテンツを作成し視聴者を魅了するための技術を持っています。
企業が自社で同様の品質を出すためには、プロのビデオグラファー、エディター、作家を雇い、高額な機材を取りそろえなければなりません。
一方、人気YouTuberは既にそれらをそろえており、企業は彼らと協力することでそれぞれを短期間かつ効率的に利用可能となるわけです。
さらに、彼らのコンテンツはすでに大きな支持を集めており、何が視聴者を惹きつけるのかを知り尽くしています。
そのため、YouTuberが保有する実績と経験を通じて、企業は多くの視聴者に受ける動画を着実に作成できます。
メリット④:再生回数が伸びやすい
YouTuberが参加している動画は、再生回数が急激に増加する傾向も見られます。
保有する大きなファンベースにより、瞬時に拡散される可能性を秘めているためです。
この仕組みを通じて、キャンペーンや商品の露出は最小限であっても最大限に拡大し、結果として次のメリットが得られることになります。
- ファンの結びつきの強さを活用したマーケティングの効果性向上
- 同じコストでより多くの視聴者にリーチ
- YouTuberの社会的証拠と影響力を活用したブランディング強化
- 興味のない層へのアプローチ
YouTuberが提供する高いレベルの拡散は、企業が大規模な予算を投じなければ達成することが困難です。
コストの効率化が望まれる中、YouTuberのキャスティングは特に価値ある選択と言えるでしょう。
メリット⑤:SNSによる二次的な拡散も期待できる
先ほども触れたように、YouTuberの動画コンテンツは、インスタグラムやXなどの様々なSNSプラットフォームで拡散されやすい特徴があります。
SNSは、ユーザー間のコミュニケーションツールとして広く利用されているものです。
そして一人のユーザーが気に入った動画を公開するだけで、そのユーザーの友人やフォロワーに即座に情報が伝わることになります。
またトレンドに敏感なSNSユーザー達は新しい動画を発掘し、見つけ次第すぐに友人たちと共有する傾向も見られます。
その結果、想定以上の拡散とリーチを実現できることもあるでしょう。
ただし、拡散を狙う場合は各SNSの特徴を踏まえた投稿を心がけてください。
YouTuberのキャスティングにかかる主な費用3つ

YouTuberのキャスティングにかかる主な費用は、以下の3つです。
- YouTuberの出演料
- 動画編集にかかる費用
- その他の諸費用
それぞれ見ていきましょう。
費用①:YouTuberの出演料
出演料はYouTuberの知名度やチャンネルの登録者数に左右されるため、相場は一概には言えません。
ただしタイアップ動画では、チャンネル登録者数に応じて出演料が計算される傾向にあります。
例えば、以下のような出演料が一つの目安です。
|
タイプ |
期間 |
相場 |
|
WEB広告出演 |
3か月 |
数万〜数十万円 |
|
WEB広告出演 |
1年 |
数十万〜数百万円 |
|
タイアップ動画 |
– |
登録者数×2〜4円 |
話題性のあるYouTuberを起用する場合は、それだけ高額になることを予測しておきましょう。
費用②:動画編集にかかる費用
動画コンテンツを制作する場合、動画編集の費用もかかります。
プロに編集を求める場合、そのスキルに応じた対価が必要です。
特にYouTuberの品質に準じた動画を求める場合、チャンネルでの編集スタイルを理解し、それを踏襲するために編集者に追加で費用がかかる可能性があるでしょう。
編集作業は手間と時間を要するため、費用はそれに比例して高くなる傾向にあります。
自社の商品やサービスをクオリティ高く紹介するためにも、予算内で最適な編集費用を見込むことが必要です。
費用③:その他の諸費用
YouTuberのキャスティング全体にかかる費用を考えるとき、撮影場所や小道具にかかる諸費用も重要です。
撮影場所としては、例えばスタジオ利用料や外部ロケ地の費用がかかります。
また小道具や装飾品の予算、YouTuberが外部から来る場合にかかる交通費や宿泊費も計上する必要があるでしょう。
それぞれの諸費用は案件によって異なるため、事前に詳細な計画を立て、見積もりを取ることが大切です。
YouTuberをキャスティングする場合の注意点

YouTuberのキャスティングは、注意深く行う必要があります。
本章では、以下2つのケースについて解説します。
- YouTuberに自身のチャンネル内でサービス紹介してもらうケース
- 自社チャンネル内でサービスを紹介してもらうケース
以下でそれぞれ詳細に解説するので、ぜひ参考にしてください。
YouTuberに自身のチャンネル内でサービス紹介してもらうケース
まず企業のターゲットオーディエンスと異なるYouTuberを選択した場合です。
企業イメージと異なるキャラクターや価値観を持つYouTuberが関与すると、企業の信頼性やブランド価値を損ねるリスクが生じます。
一度ブランド価値を損ねてしまうと、既存のファンも離れてしまう可能性があるため注意が必要です。
キャスティングするYouTuberによって、企業へのリターンが大きく変わるため、選定作業は慎重かつ戦略的に行いましょう。
自社チャンネル内でサービスを紹介してもらうケース
自社チャンネルのターゲット層とYouTuberのターゲット層がズレていると、YouTubeのアルゴリズム上望まないターゲット層にコンテンツが配信されてしまう可能性があります。
チャンネルの活性化に悪影響を及ぼす可能性があるのです。
具体的な失敗事例を紹介します。同じ美容ジャンルでも、ターゲットとする年齢層が異なるYouTuberとのコラボでの失敗例です。
- 若い世代をターゲットとした美容ジャンルアカウントが、中年層に影響力を持つ美容系インフルエンサーとコラボを行った結果、コンテンツでミスマッチを起こしてしまった。
- コラボ以前は、ニキビケアや二重アイテムの動画で再生回数1,000回を超えていたのが、コラボ相手の年齢層に合わせた「しわケア」を扱ってしまったことで、再生回数が300回以下に落ち込んでしまった。
この失敗例は、YouTubeにおける正しいターゲット層の理解とマッチングの重要性を示しています。
ターゲット層のニーズを満たすコンテンツ作りが、視聴者の関心を引き続き維持するうえで重要です。
また、ジャンル選定だけではなく、年齢層を含む具体的なターゲットの分析も不可欠でしょう。
幅広い共感を呼ぶには視聴者層とコンテンツの親和性に着目して、キャスティングを行う必要があります。
キャスティング候補を探す際のチェックポイント2つ

YouTuberのキャスティングを行う際、特に重要なチェックポイントが2つあります。
- 狙いたいターゲット層にリーチできるか
- 影響力はあるのか
2つのポイントを押さえて、効果的なYouTuberキャスティングを目指しましょう。
チェックポイント①:狙いたいターゲット層にリーチできるか
まず1つめのポイントは、狙いたいターゲット層にリーチできるかどうかです。
キャスティング候補を探す際には、自社サービスの内容・ブランドイメージに合わせて、どのような視聴者を獲得したいのかを明確にしましょう。
そして、その視聴者が好む動画のイメージやジャンルを考えます。
同じジャンルでも、動画のスタイルやトーンが異なれば視聴者の反応も変わってきます。
そのため、同ジャンルで影響力があるからと言って安易に選ばないことが大切です。
狙いたいターゲット層にリーチできるかどうかを判断するためには、以下の2つを意識するとよいでしょう。
- どういう動画を好んで見る視聴者を獲得したいのかを考える
- イメージに近い動画で再生回数を出しているチャンネルをピックアップする
それぞれ詳しく解説します。
どういう動画を好んで見る視聴者を獲得したいのかを考える
まず、どういう動画を好んで見る視聴者を獲得したいのかを考えることが重要です。
自社ブランドのイメージに沿って、どのような層にアプローチしたいのかを決める必要があります。
例えば、自社サービスが教育系であれば、知識やスキルを学びたいと思っている人や、自己啓発に興味がある人などがターゲット層です。
この場合は、分かりやすくて信頼感のある動画や、実践的で役立つ情報が盛り込まれた動画などが好まれます。
動画の傾向などを分析し、どのような視聴者を獲得したいのかしっかり検討しましょう。
イメージに近い動画で再生回数を出しているチャンネルをピックアップする
次に、自社ブランドのイメージに近い動画で再生回数を出しているチャンネルをピックアップすることです。
自社が狙っているターゲット層と同じような視聴者を持っているチャンネルを探すことで、リーチ対象にズレが生じません。
また、動画イメージが近ければ、その後の交渉や動画の完成度も高くなります。
例えば、自社のサービスが教育系であれば、「○○さんの仕事術」などのチャンネルが候補となるでしょう。
チェックポイント②:影響力はあるのか
2つめのポイントは、影響力はあるのかどうかです。
キャスティング候補を探す際には、単に再生回数が多いからと言って選ぶのではなく、影響力があるかどうかをチェックするとよいでしょう。
影響力とは、視聴者に対して何らかの行動や感情を促す力のことです。
例えば動画を見た後に視聴者に商品を購入してもらったり、サービスに登録してもらったりできれば、影響力があると言えるでしょう。
影響力がある人ほど、自分のチャンネルの認知度や信頼度を高められます。
影響力は、以下の3つの方法で測ることが可能です。
- 平均再生回数を確認する
- 動画のコメントを確認する
- 他のSNSも確認する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
平均再生回数を確認する
まず、平均再生回数を確認する方法です。
公開動画のいくつかが伸びているだけでなく、全体的に再生回数が多いかどうかに着目します。
影響力がある人のチャンネルほど、視聴者は動画の中身より人を見にくるため、平均再生回数が高い人はインフルエンス力が高いと言えるのです。
動画のコメントを確認する
次に、動画のコメントを確認する方法です。
視聴者からどういう風な見られ方をしているのかを確認します。
例えばアンチコメントや、視聴者からの指摘コメントが多い人は避けたほうがよいでしょう。
そういった人は信用度が低かったり、不満を持たれていたりする可能性があるからです。
その一方で「いつも理解しやすい」や「参考になる」といった肯定的なコメントをよく受けている人は、信頼できると考えられます。
他のSNSも確認する
最後に、他のSNSも確認することをおすすめします。
他のSNSの投稿に対しても多くのいいねやコメントがついていれば、視聴者がその人に対して好感や共感を持っていると言えるからです。
他のSNSでも人気を集めている人は、影響力があると言えるでしょう。
また複数のプラットフォームでの活動や支持は、より広い影響を示すため、異なる視聴者層へのアプローチも可能です。
YouTuberとのキャスティングを進める流れ【7ステップ】

YouTuberのキャスティングを進める際は、正確な流れを理解し、適切なキャスティングと効率的な商材のアピールが不可欠です。
YouTuberのキャスティングを進める具体的な流れは以下の7ステップです。
- 連絡方法の確認
- 打ち合わせの依頼
- 打ち合わせ
- 案件の詳細を伝える
- 案件自体に興味があるのかを確認する
- スケジュール通りに進行可能かを確認する
- 予算内でやってもらえるかを確認する
- 直近のアナリティクスを見せてもらえるかを確認する
- 類似案件の実績を確認する
- 他SNSでの拡散も予算内で可能かを確認する
- キャスティングするYouTuberの選定
- 詳細の交渉
- 契約(契約書を取り交わす)
- 案件の進行
各ステップは目標達成に不可欠であり、特に契約前の内容のすり合わせは後々のトラブルを防ぐために重要です。
適切なキャスティング、効果的なマーケティングを実現するためにも、それぞれのステップをしっかり押さえておきましょう。
ステップ①:連絡方法の確認
キャスティングを成功させるための最初のステップは、連絡方法の確認です。
YouTuberの連絡先を探すところから始めましょう。
多くのYouTuberは連絡先を公開しています。
連絡先が公式のWebサイト、YouTubeチャンネルの説明セクション、もしくはSNSプロフィールに載っていないか確認してみましょう。
なお連絡先が見つからない場合には、代替手段としてSNSでのダイレクトメッセージ(DM)を利用します。
例えば、InstagramやTwitterのDMです。
連絡を取る際は、相手への敬意を忘れずに礼儀正しく行いましょう。
また、事前にこちら側のプロフィールや企画内容を明確にしておくことで、YouTuberからの信頼を得やすくなります。
ステップ②:打ち合わせの依頼
次に、打ち合わせをお願いするステップです。
打ち合わせの依頼をする際には、案件の概略を伝えると同時に、対面またはオンラインでの詳細な打ち合わせをお願いしましょう。
この時点で、プロジェクトの期待値や意図する方向性などを簡潔に述べて、YouTuberの興味を引くことが大切です。
コミュニケーションを通じて案件についての理解を深め、相互の期待が合致するよう努めましょう。
初回のコンタクトは信頼関係の構築にもつながるため、丁寧かつ具体的なアプローチを心がけてください。
ステップ③:打ち合わせ
打ち合わせでは、以下の7つの情報を伝える必要があります。
- 案件の詳細を伝える
- 案件自体に興味があるのかを確認する
- スケジュール通りに進行可能かを確認する
- 予算内でやってもらえるかを確認する
- 直近のアナリティクスを見せてもらえるかを確認する
- 類似案件の実績を確認する
- 他SNSでの拡散も予算内で可能かを確認する
情報をしっかりと整理し、相手がマネージャー不在でも迅速に回答を得られるよう調整することが大切です。
案件の詳細を伝える
案件の詳細を伝える際は、プロジェクトの目的、目指す成果、狙うターゲット層、期待するアウトカムなどを包括的に説明します。
可能であれば、案件の背景や目標市場、キャンペーンの期間、期待される貢献なども詳細に伝えます。
これにより、相手が案件について詳しく理解し、具体的なビジョンを持って参加できるでしょう。
また、案件に関連する特別な要求や特定の制限事項があれば、それも明確に伝える必要があります。
案件自体に興味があるのかを確認する
次に、キャスティング候補に案件への興味や関心を持っているかどうかを確認しましょう。
その人が、プロジェクトにどれだけ熱意を持って取り組むかを判断する上で重要です。
例えば、候補者が案件の内容や目標に対して興味を示し、それに対する質問や提案を持っているかどうかで見極めます。
これにより、ただの仕事としてではなく、より積極的で創造的なアプローチを取る可能性があるかどうかを評価できるでしょう。
また、候補者の価値観や目標が案件の目的と一致しているかどうかも確認可能です。
スケジュール通りに進行可能かを確認する
さらに、案件がスケジュール通りに進行できるかどうかも確認します。
具体的には、案件のタイムライン、重要なマイルストーン、期限などについて話し合いましょう。
また、候補者が他に抱えている案件や予定されている活動が、プロジェクトのスケジュールにどのような影響を与えるかを理解することも重要です。
プロジェクトの進行に影響を与える可能性のある障害や制約を早期に特定し、それらに対処するための計画も立てておくと安心でしょう。
予算内でやってもらえるかを確認する
また、キャスティング候補者に予算内での対応が可能かどうかを確認することが不可欠です。
具体的な金額や支払い条件を初期段階で話し合うことで、後々の誤解やトラブルを避けることができます。
可能であれば、予算の制約内で最大限の価値を得るために、候補者がどのようなクリエイティブな提案や効率的な解決策を提供できるかも見ると良いでしょう。
直近のアナリティクスを見せてもらえるかを確認する
キャスティング候補者の実績と信頼性を正確に評価するためには、直近のアナリティクスデータを見せてもらうことが有効です。
これにより候補者のパフォーマンス、視聴者のエンゲージメント、コンテンツのリーチなどを具体的に把握できます。
またアナリティクスを見せてもらうことで、候補者が過去にどのような成功を収めてきたか、どのターゲット層にリーチしているかなど、重要な情報も得ることが可能です。
こうした情報の透明性と開示は信頼関係構築に不可欠であり、プロジェクトの成功に向けた良好なスタートを切るためにも役立つでしょう。
類似案件の実績を確認する
類似案件での実績を確認することも重要です。
キャスティング候補者が、特定のジャンルやテーマにおいてどれだけの経験と成功を持っているかを調べられます。
また、候補者が過去に手がけた類似のプロジェクトやキャンペーンの結果を見ることで、その能力やクリエイティビティ、対象市場への影響力も評価できるでしょう。
- 候補者が自身のプロジェクトに適しているか
- 必要なスキルや経験を持っているか
などを判断する上で非常に役立ちます。
他SNSでの拡散も予算内で可能かを確認する
最後に、予算内でYouTube以外の他SNSプラットフォームへのコンテンツ拡散が可能かどうかを確認します。
また過去の拡散キャンペーンの成功例や、特定のプラットフォームでの影響力を示す事例を求めることもおすすめです。
加えて、それぞれのプラットフォームに適したコンテンツ戦略やメッセージングをどのように展開するかも話し合う必要があります。
予算内で最大のリーチと影響力を得るために、効果的なマルチプラットフォーム戦略を策定しましょう。
ステップ④:キャスティングするYouTuberの選定
ステップ③までを踏まえて、キャスティングするのに最適なYouTuberを選定します。
複数の候補との打ち合わせをもとに、案件にぴったりのインフルエンサーを見極めましょう。
YouTuberの視聴者層やチャンネルのコンテンツスタイルが、自社の企画と相性が良いかを検討してください。
また、打ち合わせでのコミュニケーションにおける相手の対応の良さや、関心度も重要な選定基準になります。
最終的な判断は案件の成功に大きく影響するため、じっくりと時間をかけて検討しましょう。
ステップ⑤:詳細の交渉
詳細の交渉では、金額、納期、成果物の具体的な内容など、案件の全体像をしっかりと固めます。
提案内容について、より詳細に調整を行い、両者の理解と合意を深めていく段階です。
交渉がスムーズにいかない場合や、相手の対応に疑問を感じることがあれば、別の候補への変更も視野に入れなければなりません。
このステップでの明確な合意は、その後のトラブルを避けるために非常に重要になるため、注意深い対応を心がけましょう。
ステップ⑥:契約(契約書を取り交わす)
YouTuberとの契約は、必ず契約書を取り交わしましょう。
契約書には、具体的な作業範囲や報酬金額、納期など重要な条件を明文化し、両者が同意の上で署名します。
この流れには、後々のトラブルを未然に防ぐために特に注意を払うべきです。
契約書作成段階では法的な知識が求められることもあるため、不明な点があれば専門家に相談することをおすすめします。
ステップ⑦:案件の進行
案件がスケジュール通りに進行するためには、定期的な確認が重要です。
YouTuberに一任するだけではなく、進捗を把握しておくことで、計画通りに案件が進むようにする必要があります。
また、実際の内容に齟齬が生じないよう、コミュニケーションを密に取るとよいでしょう。
案件進行中に生じる疑問や変更点があれば、速やかに話し合い、互いの理解を深めていくことが、案件成功には不可欠です。
YouTuberのキャスティングなどYouTube運営にお困りの人はNOGICに相談
YouTuberのキャスティングは、商品やサービスのプロモーション、自社ブランドの認知拡大において非常に重要です。
しかし、適切なYouTuberを選ぶことは一筋縄ではいきません。
企業が直面する課題として、キャスティング相手の選定の難しさや費用対効果、キャンペーンの成功を左右するマッチングの重要性などが挙げられます。
また、企業のYouTubeチャンネル運営には複数のノウハウが必要であり、専門のマーケティング知識が不可欠です。
NOGICでは、こうしたYouTube運営全般にわたる問題に対し、専門知識および対策を提供しています。
ビジネス視点での集客から訴求、ターゲットに合った動画制作など、YouTubeチャンネルの成長サポートや、教育・研修系サービスのデジタルトランスフォーメーション(DX)を含め、幅広いサポートが可能です。
YouTubeの運営でお困りの際は、ぜひNOGICへご相談ください。
「YouTubeの動画をおすすめに表示させやすくする仕組みは?」「そもそもどのような仕組みでおすすめにのるんだろう?」とお悩みではないでしょうか。
実際に、動画がおすすめにのらずどうしたらいいか頭を抱えている方もいるかもしれません。
YouTubeの複雑なアルゴリズムも理解しなければなりませんし、視聴者へのアピールの仕方も常に変化しているため、難しく感じる方が多いのも当然です。
そこでこの記事では、動画がおすすめに選ばれる仕組みと、おすすめにのせるための具体的な戦略を徹底解説します。
この記事を読むことで、視聴者に響くクオリティの高いコンテンツ作りに自信が持てるようになるだけでなく、チャンネルが成長している実感も感じられるはずです。
YouTubeのおすすめ動画の仕組みとは?

YouTubeのおすすめ動画の仕組みは、ユーザーが興味を持っていると思われるコンテンツをピックアップして、ユーザーに届けるというものです。
具体的には、ユーザーの興味関心や視聴履歴に基づいて、パーソナライズされた動画が表示されます。
なお、おすすめ動画が表示されるのはYouTubeのホーム画面と、動画の視聴中に現れる「次の動画」パネルの2箇所です。
YouTubeを開くと最初に現れるホーム画面には、ユーザーの好みに合わせたおすすめの動画やフォローしているチャンネル、新しいニュースなどが載っています。
また「次の動画」パネルは、動画を見ている時に現れ、ユーザーにとって関連性が高い動画が次々と提案されるものです。
YouTubeのおすすめにのりやすい仕組みの動画は?

YouTubeでは、ユーザーの動画検索履歴や再生履歴、登録しているチャンネルに基づいてパーソナライズされた動画がおすすめにのりやすい傾向があります。
このおすすめにのる仕組みを理解し、効果的に利用するためには、以下のポイントに注意して動画を作成しましょう。
- 初動の再生回数が高い動画
- エンゲージメントが高い動画
- 専門性・信頼性の高い動画
- クリック率と総再生時間が高い動画
- 平均視聴時間の長い動画
- キーワードが盛り込まれた動画
- アンケートの結果が良い動画
それぞれのポイントを押さえた動画を作成することで、YouTubeの仕組みによる再生数やクリック数の増加だけでなく視聴者の満足度向上にも役立ちます。
①:初動の再生回数が高い動画
初動の再生回数が高い動画は、YouTubeのアルゴリズムにおいて人気があるコンテンツだと捉えられるため、おすすめに表示されやすくなります。
初動の再生回数を高める戦略として、ターゲットの視聴者数が増加する特定の時間帯に動画のアップロードを行うことがポイントです。
具体的には、平日の夕方や週末の昼間など、ターゲットがYouTubeを利用する時間を狙って公開すると良いでしょう。
また、YouTubeの外部からも視聴者を引き寄せる方法として、以下の戦略があります。
|
戦略 |
説明 |
|
事前告知 |
自身のSNSアカウントやメーリングリストを活用して動画をアップすることを告知し、視聴者の関心や期待感を高める |
|
SNSでのシェア |
視聴者にSNS上で動画を共有してもらうよう促し、拡散を目指す |
|
相互促進のコラボレーション |
他のクリエイターやチャンネルとコラボレーションを行い、お互いのファンからの認知やイメージアップを目指す |
ほかにも、動画の話題性を前面に打ち出すことも大切です。
視聴者の興味を引き、共感や警鐘を促す内容は初動で注目されやすく、高い再生回数を期待できます。
またオンライン広告の展開やインフルエンサーとの提携など、様々なプロモーション活動により、動画の視認性を増やす工夫を行うと良いでしょう。
②:エンゲージメントが高い動画
エンゲージメントとは視聴者が動画とどれだけ相互作用しているかを示す指標で、コメントや評価、共有などのアクティビティの量を意味します。
動画が高いエンゲージメントを得られるとYouTubeのアルゴリズムにさらに好まれ、YouTubeのおすすめにのる確率もグッと高まります。
例えば、以下の戦略が考えられます。
|
質問 |
動画内で視聴者に関連する質問をし、意見や感想を求めることで、コメント数の増加を目指す |
|
挑戦 |
視聴者に特定の行動や挑戦を提案し、結果を共有してもらうように促す |
|
投票 |
投票やアンケート機能を活用して、視聴者の意見を直接求めることで参加意欲を高める |
動画に対する積極的な視聴者の反応が多ければ動画の評価も上がるため、動画内でコメントや高評価、共有を促すことで、エンゲージメントを最大化できます。
それぞれの戦略を採用することで、視聴者とのコミュニケーションを活性化させることが可能です。
③:専門性・信頼性の高い動画
YouTubeにおける専門性と信頼性は、特にニュースや科学、教養といったジャンルの動画において非常に重要です。
なぜなら、誤情報や偽情報は視聴者にとって有害であり、YouTubeというプラットフォームの信頼性を損なうからです。
信頼されるコンテンツの条件としては、情報が正確で、検証可能なソースに基づいて制作されている必要もあります。
また、誇張されたタイトルや根拠のない情報を含むセンセーショナルな内容は、YouTubeに好まれず、表示順位が下げられることもあります。
加えて、審査担当者によるチェックも動画がおすすめに表示される可能性に大きく影響するものです。
動画が審査を通過しない場合、不正確、誤解を招く、有害、あるいは誤った情報提供者と見なされるため、結果としておすすめにのるアルゴリズムから除外されることになります。
以上のことから、信頼できる情報源を参考にしたうえで正確かつ信頼性の高い動画を制作することが極めて重要だと言えます。
④:クリック率と総再生時間が高い動画
YouTubeのおすすめにのせるためには、、クリック率(CTR)と総再生時間も重要な指標です。
YouTubeはこの2つのデータを使用して、動画が視聴者にとって魅力的かどうかを判断するためです。
- クリック率:検索結果や推薦リストでクリックされる割合
- 総再生時間:視聴者が動画を再生した時間の合計
クリック率が高いことは視聴者の注意を引き、関心も高いことを表します。
一方で総再生時間が長ければ、視聴者はコンテンツに満足し、興味を保持していることを意味します。
クリック率が高くても、総再生時間が短い場合は期待に応えていないコンテンツと見なされる可能性もあるため両方の指標を意識することが大切です。
効果的なサムネイルやタイトルを設定することに加えて、視聴者の期待を満たす価値の高いコンテンツを制作するようにしましょう。
⑤:平均視聴時間の長い動画
YouTubeでは、平均視聴時間もコンテンツの品質を示す重要な指標の1つです。
これは動画全体の再生時間を視聴者の数で割った値であり、視聴者が動画をどれだけ楽しんで見ているか、または内容に魅了されているかを測定するのに役立ちます。
一般的に、平均視聴時間が長ければ長いほど、高品質で視聴者の興味を持続的に引き付けていると見なされます。
平均視聴時間を高めるためには、視聴者を飽きさせない内容と構成が重要です。
YouTubeを使う視聴者が動画を途中でやめてしまう理由として、コンテンツの内容が予告やタイトルと異なることや、動画の内容が冗長であることなどが挙げられるためです。
視聴者が動画に飽きないように、また情報に価値を感じてもらうために、戦略的なアプローチを取りましょう。
⑥:キーワードが盛り込まれた動画
キーワードを適切に盛り込むことは、視聴者が興味を持つトピック対して動画を見つけやすくするために必要です。
主要なキーワードを以下の場所に含めることで、検索エンジンによるコンテンツへのマッチングがより正確になります。
|
要素 |
内容 |
|
タイトル |
検索キーワードを含む効果的なタイトルを付ける |
|
説明欄 |
キーワードを使って動画の説明をする |
|
タグ |
関連キーワードでタグ付けをする |
|
動画の内容 |
キーワードに関連する内容のコンテンツを作る |
|
ハッシュタグ |
ハッシュタグを適切に使用する |
それぞれの戦略を組み合わせることで検索エンジン最適化(SEO)に貢献し、なおかつYouTubeのおすすめリストに選ばれる可能性が高まります。
視聴者が動画を検索しやすくなればなるほど動画の視聴者数も向上し、おすすめに表示されやすくなるという好循環も生まれるでしょう。
⑦:アンケートの結果が良い動画
YouTubeでは、視聴後のアンケートも動画の評価に大きな影響をもたらします。
アンケートは、どの程度価値がある動画なのかを調査するために設けられている機能です。
YouTubeでは星4か星5の高評価を受けた動画が、視聴者に必要で役に立つコンテンツだと判断され、おすすめにのりやすくなります。
なおアンケートで高評価を受けるためには、以下の観点から視聴者にとって真に価値のある動画を作成する必要があります。
- 関連性の高いコンテンツ
- 質の高いコンテンツ
- エンゲージメントを促進する要素
- 継続的な価値の提供
それぞれを動画制作に取り入れることで高評価を獲得し、視聴者の満足度とエンゲージメントを高めましょう。
YouTubeのおすすめにのせて再生回数を伸ばす方法と仕組み

YouTubeの動画をおすすめにのせるためのポイントは、大きく分けて以下の2つです。
- 短期的にでも良いのでおすすめにのせて再生回数が欲しい場合
- トレンド動画を作る
- 長期的にチャンネルを伸ばしたい場合
- チャンネル単位でターゲットをしっかりと定める
- ターゲット視聴者にとって質の高い動画をしっかりと作り込む
- 一貫してターゲット視聴者に役立つ動画を投稿する
- ターゲット以外におすすめ表示が伸びる動画は非公開にする
ここからは、各ポイントについて見ていきましょう。
①:短期的にでも良いのでおすすめにのせて再生回数が欲しい場合
YouTubeで急速に人気を得るには、一時的であれ、おすすめに表示されることが非常に効果的です。
ここでは、トレンドに敏感な内容を取り入れた動画の作り方を解説します。
トレンド動画を作る
YouTubeにおいて視聴回数を短期的に増加させたい場合は、トレンドに敏感な動画作りが有効です。
特に、競合が少なくニーズも高い内容はおすすめ動画に表示されやすい特徴を持っています。
例としては、ニュースの速報系動画、一番くじの開封動画、アパレルブランドの最新コレクション紹介など、話題のトレンドを取り入れた動画が挙げられます。
トレンド動画を作る前に、YouTubeのアルゴリズムに影響を与える主要なポイントを押さえておきましょう。
|
急上昇動画のリスト更新間隔 |
15分ごと |
|
視聴回数 |
動画の視聴回数が多いほど良い |
|
視聴回数の伸び速度 |
急速に増加している動画が有利 |
|
視聴された地域 |
無視できない要素 |
|
動画の新しさ |
新しいほど良い |
|
他の動画とのパフォーマンス比較 |
チャンネル内での相対的な成績 |
上記を考慮し、タイムリーで視聴者の興味を引く内容を適切なタイトルとキーワードで配信することが、短期的な視聴回数の増加につながります。
ただ、トレンド動画が急増すると多様な視聴者を集めてしまい、ターゲットとするユーザー層が分散する可能性を捨てきれません。
またトレンドに特化した内容ばかりでは、他のジャンルでの視聴者がつかなくなる危険性があり、中長期的なチャンネル運営も困難を極めるでしょう。
②:長期的にチャンネルを伸ばしたい場合
長期的にチャンネルを伸ばしたい場合の戦略は以下の通りです。
- チャンネル単位でターゲットをしっかりと定める
- ターゲット視聴者にとって質の高い動画をしっかりと作り込む
- 一貫してターゲット視聴者に役立つ動画を投稿する
- ターゲット以外におすすめ表示が伸びる動画は非公開にする
それぞれ、見ていきましょう。
チャンネル単位でターゲットをしっかりと定める
YouTubeチャンネルを長期的に成長させるためには、ターゲット視聴者の明確な定義から始めることが欠かせません。
この流れは商品やサービスのマーケティング戦略に似ており、潜在的な視聴者の年齢、性別、興味、趣味といった要素を分析してターゲットを特定します。
一度ターゲットを定めたら、その視聴者層に響くコンテンツの計画と制作に集中しましょう。
例えば、子供向けのチャンネルなら教育的で楽しいアニメーションを、ゲーム好きな若者に向けたチャンネルなら最新のゲームレビューやプレイ動画を投稿するなどです。
また、ターゲットに合わせたコンテンツを配信することで以下の要素も満たせるため、最終的に視聴者の長時間滞在を促すことができます。
- 初動の再生回数の増加
- インプレッションからの高クリック率
- 長い視聴時間を獲得できる動画
このように、一貫性のあるコンテンツの投稿により、一回限りの視聴ではなく、熱心なファンを増やすことができます。
また、視聴者との信頼関係を築き、長期的な関係性を築くことにも期待できるでしょう。
ターゲット視聴者にとって質の高い動画をしっかりと作り込む
質の高い動画コンテンツを作ることで、ターゲット視聴者が定着しやすくなります。
動画の質を高めるための主要なポイントとしては、以下が挙げられます。
- 緻密な企画立案
- 丁寧な撮影
- 効果的な編集
映像の解像度が高く、音声もクリアであることは基本ですが、ストーリーテリングや視聴者の感情に訴えかける要素を取り入れることで、視聴者により良い印象を与えやすくなります。
また企画立案では、トレンドを意識した内容や視聴者のニーズに合ったオリジナリティが求められます。
加えて、撮影では視聴者が心地よく感じるビジュアルを、編集ではテンポの良い動画の流れを作ることが大切です。
このように、それぞれのバランスが整った動画を継続的にアップロードすることがチャンネル成長の鍵となります。
一貫してターゲット視聴者に役立つ動画を投稿する
また、一貫してターゲット視聴者に役立つ動画を投稿することも大切です。
ターゲット視聴者に役立つコンテンツのみを提供することで、視聴者がチャンネルを定期的に訪れる理由を見出しやすくなるためです。
さらには以下の内容を含む動画で、エンゲージメントを促進させることもできます。
- 教育的なコンテンツ
- 楽しいエンターテイメント
- 役立つ情報提供
総再生時間や平均視聴時間の増加にも期待できるため、YouTubeのおすすめに表示されやすくなることにもつながります。
このように、一貫性のある価値を提供することで、視聴者の期待に応えるだけでなく、チャンネルの成長にも期待できます。
ターゲット以外におすすめ表示が伸びる動画は非公開にする
ターゲット視聴者への影響が薄い動画やブランドイメージを乱す可能性がある動画は、思い切って非公開にしてしまうことも1つの手です。
YouTubeチャンネルのブランドイメージを構築するにあたっては、ターゲット視聴者からの再生をメインに考える戦略が重要だからです。
意図しないターゲット層からの再生が多い動画は、チャンネルのブランドイメージに混乱をきたす可能性があります。
よって、そういった動画は非公開設定を選ぶことでブランドイメージを統一しましょう。ターゲット以外におすすめが表示されている動画を探す場合は、YouTubeのアナリティクスを用いて、以下を確認しましょう。
- おすすめ表示になっている動画の分析
- ターゲットの視聴者に見られているかの確認
- ブランドのブレを起こす可能性のあるコンテンツの特定
これにより、長期的なブランドイメージの構築に役立ち、チャンネルをより効果的に成長させることができます。
YouTubeのおすすめ動画の仕組みを押さえよう
YouTubeのおすすめ動画は、ユーザーが見たい・価値があると思う動画を届ける仕組みです。
この仕組みは、ユーザーの視聴履歴や検索履歴などの行動を分析し、関連性の高い動画を提案することで実現されています。
YouTubeのおすすめ動画にのせるためには、短期的な方法と長期的な方法の2つがあります。
しかし、短期的な方法にはデメリットもあるため、継続的な効果が望めないこともあるでしょう。
そのため、ターゲティングを徹底し、質の高いコンテンツのみを提供するアプローチが理想です。
YouTubeのコンサルティングを行うNOGICでは、効果的なコンテンツ配信やチャンネル運営のアドバイスを行っています。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
「YouTubeを活かしたクリニックへの集客は可能?」と気になりお調べですね。
クリニックの集客は、信頼感だけでなく興味や関心を持ってもらうことが重要です。
そのため、多くの見込み顧客を獲得できるYouTubeを使った集客は効果的であり、視聴者にクリニックの魅力を伝えるツールとして活用できます。
しかし、本当にYouTubeが集客に向いているのか、注意すべき点はないのか気になる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、YouTubeを使ってクリニックへの集客が本当に可能なのかについて、具体的な成功事例を紹介しながら解説します。
未来のクリニックの成果をイメージし、YouTubeを使った集客に挑戦してください。
YouTubeを使ってクリニックへの集客は本当に可能?

YouTubeを使ってクリニックへ集客することは可能です。
実際に、YouTubeを活用し、クリニックの集客に成功している事例は多くあります。
例えば、Youtubeだとクリニックの中の雰囲気やスタッフの顔、施術の様子などを動画で見せることができます。
施術中の様子を見せ、具体的な効果を伝えることで、よりクリニックに対する信頼感を上げることが可能です。また、実際の店舗スタッフがYouTubeに出演することで、スタッフに対して親近感を持ってもらえます。
このように、YouTubeは視聴者に対してクリニックの魅力を多角的にアピールできる手段となります。
クリニックの集客にYouTubeが向いている理由は、下記のとおりです。
- クリニックの中の雰囲気まで知ってもらえる
- 既存顧客により親しみを持ってもらえる
- 若い年齢層にアプローチできる
- 他クリニックとの違いを知ってもらえる
それぞれ、詳しく解説します。
クリニックの中の雰囲気まで知ってもらえる
YouTubeでは、クリニックの内装や設備、スタッフや医師の様子など、クリニックの中の雰囲気を動画で知ってもらえます。
動画では、清潔さや快適さ、スタッフの笑顔や対応、施術の流れや痛みなどをリアルに感じてもらえるためです。
たとえば、下記のような動画があります。
|
内容 |
説明 |
効果 |
|
クリニック紹介動画 |
クリニックの外観や内装、受付や待合室、診察室や施術室などを紹介する動画 |
来院前にクリニックの雰囲気や設備を把握してもらい、安心感を与える |
|
スタッフ紹介動画 |
クリニックのスタッフ(医師や看護師など)を紹介する動画 |
スタッフとの親近感や信頼感を高め、来院へのハードルを下げる |
|
施術紹介動画 |
クリニックで行っている施術(美容整形やレーザー脱毛など)を紹介する動画 |
施術の流れや効果をわかりやすく説明し、患者の不安や期待を払拭する |
これにより、潜在顧客はクリニックに来院する前に、安心感や信頼感を持つことができます。
また、クリニックの特徴やサービス内容を分かりやすく説明することも可能です。
必要に応じて、最新の医療機器や技術を紹介したり、施術の流れや効果を実際に見せたりするのも良いでしょう。
このように、外側からではわからないクリニックの中の雰囲気まで、YouTubeでは余すことなく伝えられるのがメリットです。
既存顧客により親しみを持ってもらえる
YouTubeでは、既存の患者さんにも定期的にコンテンツを提供することで、クリニックへの親しみを持ってもらうことができます。
実際の医師やスタッフが顔出しで登場できるからです。
たとえば、下記のような動画が考えられます。
|
内容 |
説明 |
効果 |
|
Q&A動画 |
クリニックに関するよくある質問や施術に関する質問に答える動画 |
患者さんの疑問や不安を解消し、信頼感や満足度を高める |
|
ライブ配信動画 |
クリニックのスタッフがリアルタイムで患者さんとコミュニケーションする動画 |
患者さんとのコミュニケーションを通じて親しみや関心を高める |
|
患者さんの声動画 |
クリニックで施術を受けた患者さんの感想や体験談を紹介する動画 |
患者さんの感想や体験談を通じて感情移入や共感を促す |
これらの動画では、イラストや画像だけではない映像という情報で、既存顧客は医師やスタッフにより親しみを持つことができます。
また、医師やスタッフの人柄や考え方、専門性などを伝えることで、クリニックと患者さんの関係を長期的に維持することが可能です。
加えて、既存の患者さんがYouTubeの動画を口コミやSNSで拡散することで、新たな潜在的な患者さんにもアプローチできます。
このように、YouTubeはコメントや高評価などの機能で視聴者とのコミュニケーションもでき、既存顧客との関係を深めるチャンスとなるでしょう。
若い年齢層にアプローチできる
YouTubeを使うことで、若い年齢層にアプローチできるのも理由のひとつです。
YouTubeは、2021年時点で20代の男性の88.8%・20代の女性の90.3%が利用しているという結果が出ています。
また、女性の多くは「化粧/美容品」をYouTubeの影響で購入したことがあるという調査結果もあります。
そのため、YouTubeで若い年齢層にアプローチする際には、下記の若い年齢層に合わせたコンテンツ制作が考えられます。
|
内容 |
説明 |
効果 |
|
コラボ動画 |
クリニックと関連性のある人気YouTuberやインフルエンサーとコラボレーションする動画 |
クリニックの知名度を向上させ、新たな視聴者や患者を獲得する |
|
チャレンジ動画 |
クリニックで施術を受ける際に面白いチャレンジを行う動画 |
視聴者の興味を引きつけ、クリニックへの関心を高める |
|
ランキング動画 |
クリニックで人気の施術や商品をランキング形式で紹介する動画 |
視聴者の関心を引き、クリニックの特徴や強みを伝える |
また、口コミやSNSで拡散されやすいメディア媒体でもあるため、クリニックのターゲット層を広げることにもつながります。
このように、YouTubeでは若い年齢層にアプローチでき、クリニックのブランドイメージや知名度を向上させることにつながります。
出典:TestTee Lab「YouTubeに関する調査【2021年版】」
出典:Cross Marketing「YouTubeの利用実態に関する調査」
他クリニックとの違いを知ってもらえる
YouTubeを活用することで、他のクリニックとの違いを視聴者に知ってもらうこともできます。
動画内で自社クリニックの特徴や強みをアピールすることで、潜在的な患者さんの獲得に繋がります。
具体的には、以下のような動画内容が考えられます。
|
内容 |
説明 |
効果 |
|
クリニック比較動画 |
クリニックと競合する他のクリニックとの比較を行う動画 |
視聴者にクリニックの特徴や強みを理解させ、他のクリニックとの差別化を図る |
|
患者インタビュー動画 |
クリニックで治療を受けた患者のインタビュー動画 |
患者の実際の声や体験談を通じて、クリニックの信頼性や効果を訴求する |
|
専門知識動画 |
クリニックの医師やスタッフが専門的な知識や情報を提供する動画 |
クリニックの専門性や知識の深さを訴求し、視聴者に信頼感を与える |
これにより、視聴者はクリニックに対して信頼感や好感を持つようになります。
また、他のクリニックと比べてどのようなメリットや強みがあるのかを明確にすることで、視聴者から選ばれる可能性が上がります。
このように、YouTubeはクリニックの個性や魅力を伝えるツールとして活用でき、より多くの人へアプローチできるのです。
YouTubeによる集客で成功しているクリニックの事例

YouTubeによる集客で成功しているクリニックの事例は、下記の3つが挙げられます。
- 元神チャンネル
- ドラゴン細いfeatアマソラクリニック
- にしたんクリニック
それぞれ、詳しく解説します。
元神チャンネル
元神チャンネルは、男性の性的な悩みに特化したYouTubeチャンネルです。
包茎、ペニスの増大、早漏など、多くの男性が抱える問題に対する解決策を提供しています。
元神チャンネルには、具体的に以下の特徴があります。
- 専門性:男性の性的な悩みに特化している
- アクセシビリティ:匿名で情報を得られる
- インタラクティビティ:質問や相談が気軽にできる
元神チャンネルは、タブーとされがちなテーマに対して、専門的かつ親しみやすい情報を提供しています。
これにより、多くの方からフォローを得ている成功事例と言えるでしょう。
参考にしてYouTubeを運営する場合は、専門性の高いテーマで、親しみやすいコンテンツを作成するという施策が考えられます。
ドラゴン細井featアマソラクリニック
ドラゴン細井featアマソラクリニックは、美容外科と美容皮膚科に特化しています。
渋谷のアマソラクリニック、新宿のアマシオクリニックなど、複数のクリニックが提供する美容医療情報を発信しています。
本チャンネルには、以下の特徴があります。
- 多角的な情報提供:複数のクリニックからの情報がある
- エンタメ性:美容医療×エンタメを追求している
- 誠実性:正確な美容医療情報を提供している
なかでも、エンタメ性を取り入れることで、一般的な美容医療の情報提供以上の価値を生み出している点は、多くの視聴者を引きつけているポイントです。
一見すると難しい内容を取り扱う場合でも、エンタメ要素を取り入れることで多くの視聴者に興味を持ってもらうことができます。
にしたんクリニック
にしたんクリニックのYouTubeチャンネルは、美白や美肌の美容点滴・注射、HIFUやピコレーザーなどの美容皮膚・レーザー治療を中心とした内容を提供しています。
最新の医療を取り扱う一方で、自らの特徴を全面に打ち出した動画が特徴です。
- 多様な治療:美白、美肌、ダイエットなど多様な情報を発信している
- 高級感:上質で落ち着いたスペースを動画で余すことなく伝えている
- 健康と美容の融合:健康で若々しい生活をアピールしている
他のクリニックとは動画の雰囲気も異なり、さまざまなジャンルで動画をあげています。
多様なニーズに対応することで、多くの視聴者を獲得している事例です。
YouTubeで集客する場合の注意点

YouTubeで集客する場合の注意点は、下記のとおりです。
- YouTubeに対する知識が必要
- 成果が出るまで時間がかかる
いずれにおいても、運営に大きな影響があるため、それぞれ確認しましょう。
YouTubeに対する知識が必要
YouTubeで集客するには、YouTubeに対する知識が必要です。
YouTubeは、世界最大の動画共有サイトであり、毎日何億回もの動画が視聴されています。
しかし、その中で自分の動画が目立つようにするには、下記の基本的な知識が必要です。
- どのような動画を作るべきか
- どのようなタイトルやサムネイルを付けるべきか
- どのようなキーワードやタグを使うべきか
また、YouTubeは検索エンジンとしても機能しており、GoogleやYahoo!などの検索結果にも表示されます。そのため、SEO(検索エンジン最適化)の知識も必要です。
さらに、YouTubeはSNSとしての側面もあります。そのため、視聴者とのコミュニケーションやファンづくりも重要です。
このように、YouTubeを運営するには、多くの知識を学ぶ必要があります。
成果が出るまでに時間がかかる
YouTubeには、成果が出るまでに時間がかかるという特徴があります。
YouTubeで多くの視聴者やチャンネル登録者を獲得するには工夫がいります。
YouTubeには数多くの動画やチャンネルがあり、その中で自分の動画やチャンネルを知ってもらう必要があるからです。
自社のチャンネルを知ってもらうには、自社の強みや他社との差別化ポイントを明確にし、ターゲットに的確に訴求する必要があるのです。
また、動画を撮影するための機械や技術も必要になるため、始めるまでにも時間がかかります。
このように、YouTubeで集客する場合は成果が出るまで時間がかかるため、長期的な視点で取り組むことが重要です。
YouTubeを使った集客はNOGICへお任せ
YouTubeを使った集客は、NOGICへお任せください。
NOGICは、累計100チャンネル以上の運用事例を誇り、動画の企画から制作まで幅広く受けています。
NOGICでは編集・企画パッケージと運用フルパッケージの2種類のプランを用意しているので、自社で運用が難しい業務を請け負うことが可能です。
また、NOGICでは、YouTubeチャンネルが上手くいかない方に対する無料診断も行っています。
YouTubeを使った集客に興味がある方は、まずはNOGICにご相談ください。
YouTubeを始めたばかりの多くの方が、「本当に企業のYouTubeが成功するのか」「どうやれば成功するのか」と悩んでいます。
企業によるYouTube運営は、個人のチャンネルと異なり、具体的な発信内容を考えることが難しいです。
しかし、実際に企業YouTubeとして成功している事例を知ることで、自身のYouTubeチャンネルやビジネスに活かすヒントが得られます。
一方で、実際に取り組んで失敗してしまったというケースが散見されるのも見逃せません。
そこで本記事では、成功している企業YouTubeの事例を11選解説し、成功している企業の共通点・失敗している企業の特徴についても解説していきます。
ぜひ、企業YouTubeの成功事例を理解し、自身のYouTubeチャンネルやビジネスに活かしてください。
企業YouTubeの成功事例11選

企業YouTubeの成功事例は、下記のとおりです。
- 武田塾チャンネル
- 葬儀・葬式CH有限会社佐藤葬祭
- 楽待チャンネル
- ザ・レスポンスtheresponse
- アトム法律事務所
- サントリー公式チャンネル
- アングラーズ
- くら寿司 178イナバニュース
- イヤホン・ヘッドホン専門店eイヤホン
- 片付けトントン
- ハードオフ久留米国分店公式チャンネル
それぞれ、詳しくみていきましょう。
※登録者数および動画数は、2023年10月調査時点の情報です。
武田塾チャンネル
|
チャンネル名 |
武田塾チャンネル |
|
登録者数 |
20.9万人 |
|
動画数 |
6737本 |
武田塾チャンネルは、大学受験生や高校生を対象にした教育コンテンツを提供するYouTubeチャンネルです。
武田塾チャンネルが成功事例と言える理由は、高い専門性と質の高いコンテンツによって、特定のターゲット層に強く訴求しているからです。
具体的には以下の内容が発信されています。
- 参考書の使い方
- 数学の解説
- 英語の勉強法
- 大学受験情報
武田塾チャンネルでは、専門家による詳細な解説があり、視聴者が理解しやすいように工夫されています。
武田塾チャンネルは、高い専門性と質の高いコンテンツで多くの登録者を獲得し、ターゲットに合わせたコンテンツ戦略の重要性を示した好例といえます。
葬儀・葬式CH有限会社佐藤葬祭
|
チャンネル名 |
葬儀葬式ch有限会社佐藤葬祭 |
|
登録者数 |
9.06万人 |
|
動画数 |
2255本 |
葬儀・葬式CH有限会社佐藤葬祭は、葬儀の知識と情報を発信する目的で運営されています。
創業80余年の有限会社佐藤葬祭が運営しており、代表取締役の佐藤信顕氏が直接話をしています。
- 損傷の激しい遺体の取り扱い
- 火葬直前の葬儀社の選定
- 火葬炉前での撮影禁止の理由
- 幽霊の存在について
動画では、一般的には知られていない葬儀の裏側や疑問点について解説しています。
葬儀・葬式CH有限会社佐藤葬祭のチャンネルが成功している理由は、専門的な知識をわかりやすく伝え、多くの人々に有用な情報を提供している点です。
専門的なテーマでも、わかりやすく、かつ深く情報を提供することで多くのフォロワーを獲得しています。
楽待チャンネル
|
チャンネル名 |
不動産投資の楽待 (らくまち) |
|
登録者数 |
44.2万人 |
|
動画数 |
827本 |
楽待チャンネルは、不動産投資に特化したYouTubeチャンネルです。
動画は専門家による解説が豊富で、視聴者に具体的なアドバイスを提供しています。
- 不動産投資の基礎知識
- 物件選びのポイント
- ファイナンスの管理
- 税金対策
楽待チャンネルでは、リアルなケーススタディを多く取り上げています。
そのため、知識がない視聴者でも簡単に理解する事ができ、実用性がある情報を得ることができるのです。
専門性の高い領域のチャンネルは、わかりやすさを踏まえた高品質なコンテンツが、多くのフォロワーを獲得する上で必要な要素となります。
ザ・レスポンスtheresponse
|
チャンネル名 |
ザ・レスポンスtheresponse |
|
登録者数 |
5.24万人 |
|
動画数 |
912本 |
ザ・レスポンスtheresponseは、主に小さな会社の社長向けにマーケティングのヒントを提供するYouTubeチャンネルです。
- セールスライティング
- ランディングページ制作
- Web広告
- 経営・戦略・マネジメント
- 商品の作り方
- ジェイエイブラハム特集
- ダンケネディ特集
- 初心者のためのFacebook広告
動画の特徴は、具体的なマーケティング戦略やテクニックを解説している点です。
また、視覚的な要素も豊富で、初めての方でも理解しやすい内容となっています。
ターゲットに合わせた質の高いコンテンツを提供することで、自社サービスの集客に繋げている好例です。
アトム法律事務所
|
チャンネル名 |
アトム法律事務所 |
|
登録者数 |
154万人 |
|
動画数 |
2104本 |
アトム法律事務所のYouTubeチャンネルは、法律に関する多様なトピックを扱っています。
主に岡野タケシ弁護士が出演し、法律の知識をわかりやすく提供しています。
- 契約法
- 離婚手続き
- 相続問題
- 消費者トラブル
動画は専門的な内容でありながら、一般の人々にも理解しやすいように工夫されています。
具体的なケーススタディまで解説しており、法律の複雑な側面をシンプルに理解できます。
アトム法律事務所は、一般人が普段接する機会の少ない法律の知識を、手軽に学べるプラットフォームとして成功しているのです。
リアルなケーススタディをQ&A形式で取り上げることで、関心があるフォロワーを集めています。
サントリー公式チャンネル
|
チャンネル名 |
サントリー公式チャンネル (SUNTORY) – YouTube |
|
登録者数 |
31.8万人 |
|
動画数 |
1733本 |
サントリー公式チャンネルは、日本の大手飲料メーカー、サントリーが運営するYouTubeチャンネルです。
多様なテーマで一貫したブランドメッセージを伝えています。
- 新製品の紹介
- レシピ動画
- イベントのハイライト
- サステナビリティ活動
サントリー公式チャンネルでは、多様なコンテンツで幅広いターゲット層にアピールしており、高いエンゲージメントを維持しています。
ブランドの認知度と信頼性が高めながら、ブランドメッセージを効果的に伝えている点が、YouTubeマーケティングの成功事例と言えるでしょう。
アングラーズ
|
チャンネル名 |
アングラーズチャンネル |
|
登録者数 |
2.17万人 |
|
動画数 |
531本 |
アングラーズのYouTubeチャンネルは、釣り愛好者に特化したコンテンツを提供しています。
具体的には以下の内容です。
- 釣りのテクニック
- 釣具のレビュー
- 釣りスポットの紹介
- 釣果報告
専門家による解説や実際の釣りの様子を撮影しており、視聴者にリアルな体験を提供しています。
アングラーズチャンネルのポイントは、視聴者が明日から使えるテクニックまで解説している点です。
釣り愛好者に特化した高品質なコンテンツを定期的に更新しており、成功を収めた事例と言えます。
くら寿司 178イナバニュース
|
チャンネル名 |
くら寿司 178イナバニュース |
|
登録者数 |
11.3万人 |
|
動画数 |
500本 |
くら寿司178イナバニュースは、くら寿司の社員が運営するYouTubeチャンネルです。
さまざまな動画を出しており、中にはくら寿司の裏側を公開するものもあります。
- くら寿司の裏側を大公開
- 新商品の紹介
- お店の効率的な仕組み
- ゲーム動画
くら寿司178イナバニュースは、多様なコンテンツと高い登録者数・再生回数によって、ブランドの認知度と信頼性を高めています。
多様なコンテンツを作りつつも、一貫したブランドメッセージが、高いエンゲージメントを生んだことで成功を収めた事例です。
イヤホン・ヘッドホン専門店eイヤホン
|
チャンネル名 |
イヤホン・ヘッドホン専門店eイヤホン |
|
登録者数 |
12.4万人 |
|
動画数 |
2334本 |
イヤホン・ヘッドホン専門店eイヤホンのYouTubeチャンネルは、オーディオ機器に特化した情報提供を行っています。
- 製品レビュー
- 使い方ガイド
- 新製品の紹介
- イベントのレポート
動画は専門家による詳細なレビューと解説が特徴で、高品質なコンテンツとイヤホンを探している視聴者に対する専門性の高い情報提供を行なっています。
ターゲットを意識したコンテンツ作りが、ブランドの信頼と認知度を高める鍵となった好例です。
片付けトントン
|
チャンネル名 |
片付けトントン |
|
登録者数 |
24.2万人 |
|
動画数 |
36本 |
片付けトントンは、プロのクリーニングチームが運営するYouTubeチャンネルです。
主に、お客様宅での片付けや掃除のドキュメンタリー、整理収納や掃除のコツを公開しています。
- 不用品回収
- 整理収納
- ゴミ屋敷片付け
- 生前整理
- 遺品整理
動画は非常に実用的で、視聴者が自宅で簡単にできる掃除や整理方法を発信しています。
また、ビフォー・アフターの比較があり、自社の魅力を効果的に伝えているのも特徴です。
このように、自社の魅力や高い技術を発信することで、視聴者からの信頼を獲得しています。
ハードオフ久留米国分店公式チャンネル
|
チャンネル名 |
永田 ハードオフ久留米国分店 |
|
登録者数 |
27.6万人 |
|
動画数 |
76本 |
ハードオフ久留米国分店の公式チャンネルでは、店員の永田さんが一人で演奏、撮影、編集、演出を行っています。
- ジャンク品での楽器演奏
- 有名曲のカバー
- 商品紹介
- イベント告知
動画の特徴は、店員の永田さんがジャンク品で楽器を演奏し、有名な曲をカバーしていることです。
一人の店員が多くの役割を担い高いクオリティを出すことで、注目を集めています。
このように、限られたリソースでもクリエイティビティを活かすことで、多くのフォロワーが獲得できます。
YouTubeで成功している企業の共通点

YouTubeで成功するには、ただ動画を投稿するだけでは不十分です。YouTubeで成功している企業には、下記に挙げた4つの共通点があります。
- 定期的に動画更新がされている
- 狙っているターゲットが明確
- SEOがされている
- 視聴や登録を促す取り組みがされている
自社で実践して失敗しないためにも、それぞれ詳しく解説します。
定期的に動画更新がされている
YouTubeで成功している企業の特徴の1つは、定期的に動画更新がされていることです。
定期的に動画を更新することで、視聴者に対して信頼感や親近感を与えられます。
また、YouTubeのアルゴリズムによって、更新頻度を上げることで視聴者におすすめされる可能性が高まるので、視聴者数や登録者数を増やすことにもつながります。
このように、定期的に動画更新を行うことは、YouTubeで成功する企業の共通点です。
狙っているターゲットが明確
狙っているターゲットが明確であることもYouTubeで成功する上で重要な要素です。
ターゲットを明確にすることで、動画の内容やスタイルを最適化できます。
たとえば、釣り愛好者に特化したコンテンツを提供する「アングラーズチャンネル」では、釣りに興味がある視聴者を狙った動画が発信されています。
そのため、釣りのテクニックや釣り具のレビュー、釣りスポットの紹介、釣果報告など、釣り愛好者にとって有用な情報が幅広く発信されているのです。
このように、成功事例として紹介された企業の多くは、独自のターゲットに向けたコンテンツを提供することで、YouTubeでの成功を収めています。
SEO対策がされている
YouTubeで成功している企業では、SEO対策がされていることも共通点として挙げられます。
SEOとは、検索エンジン最適化のことであり、検索結果において上位に表示されるように工夫することです。
YouTubeでは、動画のタイトルや説明文、サムネイルなどがSEOの要素となります。
これらの要素で、検索キーワードを意識したキーワードやタグを設定することで、検索結果でより上位に表示されるようになります。
たとえば、アトム法律事務所は、YouTubeチャンネルのタイトルや説明文に関連キーワードを適切に使用しています。
また、eイヤホンは、動画のタイトルや説明文に関連キーワードを組み込むだけでなく、タグやサムネイルの最適化にも取り組んでいます。
成功事例として紹介した企業の多くは、SEOを重視しており、その結果、高い視聴者数や登録者数を獲得しています。
視聴や登録を促す取り組みがされている
YouTubeで成功している企業の多くは、他の動画の視聴やチャンネル登録を促す取り組みをしています。
視聴や登録を促す取り組みとは、動画の最初や最後に視聴者に対してアクションを求めたり、コメントやいいねを募ったりすることです。
いずれのチャンネルでも、こうした取り組みを行うことで、視聴者のエンゲージメントを高めています。
また、視聴者のフィードバックや要望を反映させることで、動画の品質や満足度を向上させることも可能です。
YouTubeで失敗する企業の特徴

YouTubeで失敗する企業には、下記の共通の特徴があります。
- ターゲットを意識した企画になっていない
- チャンネルに統一感がない
- 定期的な動画更新がない
それぞれ見ていきましょう。
ターゲットを意識した企画になっていない
YouTubeで成功するためには、ターゲットとなる視聴者のニーズや関心を把握し、それに応えるような企画を立てる必要があります。
しかし、多くの企業は自社の商品やサービスを紹介するだけの動画を作ってしまいます。
これでは、視聴者にとって魅力的な動画になりづらく、チャンネル登録や高評価などのアクションにもつながりません。
ターゲットを意識した企画とは、たとえば以下のような内容です。
- 商品やサービスの使い方やメリットを分かりやすく伝えるハウツー動画
- ターゲットとなる人物像やライフスタイルを描くストーリー動画
これらの動画は、視聴者にとって有益であると感じさせるだけでなく、自社のブランドイメージや差別化要素もアピールできます。
チャンネルに統一感がない
YouTubeで成功するためには、チャンネルに一貫したテーマやコンセプトを持つことも重要です。
しかし、多くの企業はバラバラな内容やジャンルの動画を投稿してしまいます。
これでは、視聴者にとってチャンネルの特徴や方向性が分かりません。また、興味を持ち続けることも難しくなります。
チャンネルに統一感を持たせるためには、下記の工夫が必要です。
- ターゲットとなる視聴者層やニッチな市場を明確に定める
- 動画のタイトルやサムネイル、BGMなどのビジュアルや音声要素に一貫性を持たせる
こうした取り組みの積み重ねが、視聴者にとってチャンネルの認知度や信頼度を高めることにつながります。
定期的な動画更新がない
YouTubeで成功するためには、定期的に新しい動画を投稿することも重要です。
しかし、多くの企業は動画制作に時間やコストがかかると感じてしまい、不定期にしか動画を更新しないか、あるいは途中で挫折してしまいます。
その結果、視聴者にとってチャンネルへの期待感や関心度が低下してしまいます。
加えて、YouTubeのアルゴリズムからも優先的におすすめ表示されにくくなるのです。
定期的な動画更新を続けるためには、動画制作の流れやスケジュールを明確に決めておくことが大切です。
また、動画制作の負担を軽減するために外部の制作会社やパートナーと協力することなども工夫として挙げられます。
YouTubeは、企業にとって有効なマーケティングやブランディングのツールですが、失敗しないためにもこうした共通点に当てはまらない工夫を行いましょう。
YouTube運営に時間がさけない企業が行うべき2つの対策

実際に多くの企業が、YouTube運営に時間をさけないと悩んでいます。
そこで、YouTube運営に時間がさけない企業が行うべき2つの対策を紹介します。
- YouTube運用代行に依頼する
- 一部の業務を外注化する
以下で詳細に解説するので、ぜひ参考にしてください。
YouTube運用代行に依頼する
YouTube運用代行とは、YouTubeチャンネルの企画、制作、配信、分析などを専門の会社や個人に任せることができるサービスです。
YouTube運用代行に依頼するメリットは、下記のとおりです。
- YouTubeの専門知識や技術で品質の高い動画を作成できる
- 最新のトレンドやアルゴリズムに対応した戦略を立ててもらえる
- 自社の時間や人員を節約できる
YouTube運用代行に依頼する場合は、自社の目的や予算にあった会社を選ぶことが重要です。
また、運用代行者とのコミュニケーションやフィードバックも欠かせません。
YouTube運用代行に依頼することで、YouTube運営に時間がさけない企業でも効果的な動画マーケティングができます。
一部の業務を外注化する
YouTube運用代行には、費用がかかります。また、自社のブランドやメッセージを伝えるには、自社で動画を作成することも必要です。
そこで、一部の業務を外注化するという方法があります。
具体的には下記のイメージです。
- 動画の編集や字幕作成などの技術的な部分を外部に委託する
- 動画のアイデアやキーワードなどの企画的な部分を外部に依頼する
- 動画の配信や分析などの運用的な部分を外部に任せる
一部の業務を依頼することで、自社の得意な部分や重要な仕事に集中でき、外部から新しい視点やアドバイスを得られます。
また、運用代行に依頼するケースと比較して、費用を抑えられることもメリットです。
一部の業務を外注化する場合は、自社で担当する部分と外注する部分を明確に決めることが重要です。
さらに外注先との契約や納期、品質管理などもしっかりと行う必要があります。
一部の業務を外注化することで、YouTube運営に時間がさけない企業でも効率的な動画制作ができます。
YouTubeを始めようか悩んでいる企業はNOGICへ相談
YouTubeは、単に動画を投稿するだけでなく、チャンネル運営や視聴者とのコミュニケーション、分析・改善などが重要です。
しかし、これらの作業は時間がかかり本来の業務に支障が出る可能性もあります。
また、専門的な知識やスキルも必要になるため、時間がかかってしまうこともあります。
もし、そのような理由からYouTubeを始めようか悩んでいる場合には、ぜひNOGICへご相談ください。
NOGICは、YouTubeのプロ集団が貴社のチャンネルを分析し、最適な企画・制作・拡散の方法を提案します。
これから始める企業も、既に始めている企業でも問題ありません。まずは無料でご相談ください。
中小企業にとって、YouTubeマーケティングは大きなチャンスです。
YouTubeは、世界で最も利用されている動画共有サイトであり、多くの人が日々利用しています。そのため、広い層に自社の製品やサービスをアピールできます。
しかし、何の戦略も考えずにYouTubeで成功することはできません。
この記事では、YouTubeマーケティングを行う上でのコツを紹介しながら、中小企業がYouTubeを活用する方法を具体的に解説します。
多くのチャンネルに埋もれてしまって失敗しないために、ぜひ参考にしてください。
中小企業こそYouTubeを利用しマーケティングを行うべき

中小企業の多くは、YouTubeをマーケティングに活用していません。これは、大きな機会損失です。
中小企業がYouTubeを利用することで、以下のようなメリットが得られます。
|
メリット |
説明 |
|
費用対効果が高い |
無料で動画をアップロードできるため、高額な広告費をかけずに世界中に自社の動画を公開できる。 |
|
気軽に多くの情報を発信しやすい |
動画であれば何でもアップロードできるため、自社の商品やサービスだけでなく、会社の歴史や社員の紹介など、さまざまな情報を動画で伝えられる。 |
|
細かいターゲティングが可能 |
視聴者の属性や興味に応じて動画を表示するため、自社の商品やサービスにあったターゲット層に動画を届けられる。 |
一方、YouTubeを利用しない場合は、以下のようなリスクやデメリットがあります。
|
リスク / デメリット |
説明 |
|
競争力の低下 |
YouTubeを利用していない中小企業は、集客力や信頼性が低くなる。 |
|
時代遅れのイメージ |
YouTubeを利用しない中小企業は、時代遅れのイメージを持たれる可能性がある。 |
|
情報伝達の限界 |
YouTubeを利用しない中小企業は、自社のメッセージや魅力を十分に伝えられない可能性がある |
中小企業によるYouTube活用は、費用対効果が高く競合との差別化も図れるため非常におすすめです。
機会損失を避け、競争力を高めるためにも積極的に取り組んでいくことが大切です。
中小企業のYouTubeマーケティングを行うメリット

ここからは、中小企業のYouTubeマーケティングを行うメリットについて、以下の3点にわけて説明します。
- 費用対効果が高い
- 気軽に多くの情報を発信しやすい
- 細かいターゲティングが可能
費用対効果が高い
YouTubeマーケティングの最大のメリットは、費用対効果が高いことです。
YouTubeは基本的に無料で利用でき、広告を多くの人に届けることができます。
そのため、時間や手間などのリソースがかかる以外は、大きなコストはかかりません。
このように、YouTubeマーケティングは、少ない投資で大きな効果が得られます。
YouTubeを運営することで、中小企業は高額な広告費をかけずに自社の動画を世界中に公開することが可能です。
気軽に多くの情報を発信しやすい
気軽に多くの情報を発信しやすいことも、YouTubeを行う上でメリットになります。
YouTubeはユーザーが自由にコンテンツを作成できるプラットフォームです。
中小企業はYouTubeを利用することで自社の商品やサービスだけでなく、会社の歴史や社員の紹介など様々な情報を伝えられます。
このように、自社を知ってもらう上でYouTubeマーケティングおすすめのマーケティング方法です。
細かいターゲティングが可能
YouTubeマーケティングのメリットの1つに、細かいターゲティングが可能なことがあげられます。
YouTubeは視聴者の属性や興味に応じて動画を表示できます。
これは、YouTubeのアルゴリズムが視聴者の行動履歴や検索履歴などを分析して、最適な動画を訴求しているためです。
これにより、中小企業は自社の商品やサービスにあったターゲット層に動画を届けることができます。
たとえば、ある中小企業が自社の商品を使ったレシピ動画をYouTubeにアップロードした場合、その動画は料理に興味のある視聴者に表示されます。
このように、YouTubeマーケティングは、細かいターゲティングが可能です。
YouTubeマーケティングでやるべきこと

YouTubeマーケティングには、ただ動画を投稿するだけではなく、戦略に沿った運用が必要。
露出の機会を逃すことや視聴者とのコミュニケーションの機会を失う前に、YouTubeマーケティングでやるべきことは以下の4つです。
- チャンネル開設
- 動画広告の運用
- インフルエンサーとのコラボ
- 紹介動画やショートの投稿
それぞれのポイントについて、詳しく紹介します。
チャンネル開設
YouTubeマーケティングの第一歩は、自社のチャンネルを開設することです。
YouTubeチャンネルは、ブランドのメッセージを伝え、視聴者との関係を築くための基盤となります。
たとえば、自社の製品や歴史に関する動画を投稿することで、自社についての理解を深めてもらえます。
この結果、視聴者のロイヤルティが高まり、長期的なビジネスの成功に繋がるのです。
動画広告の運用
動画広告の運用も重要な戦略です。
動画広告は視覚的な情報を提供し、視聴者の感情に訴えられるため、効果的なマーケティングに繋がります。
動画広告を運用する際は、製品の使用方法を示すチュートリアル動画や顧客の体験談を共有するテストモニアル動画などがおすすめです。
これにより、視聴者に自社商品の使用感をイメージしてもらえます。
インフルエンサーとのコラボ
インフルエンサーとのコラボレーションも有効な戦略です。
インフルエンサーは大量のフォロワーを持っており、その影響力を利用することで新たな視聴者層へ訴求できます。
たとえば、人気のインフルエンサーと共同でプロモーション動画を作成することで、そのインフルエンサーのフォロワーに自社の製品やサービスを紹介できます。
これはブランドの認知度を大幅に向上させ、新たな顧客を獲得する機会を生み出します。
紹介動画やショート動画の投稿
紹介動画やショート動画の投稿も効果的な戦略です。
これらの動画は視聴者に対して短時間で情報を提供し、視聴者の注意を引くことができます。
具体的には、新製品の紹介や製品の使い方を示すショート動画を投稿することで、視聴者に対して素早く情報提供し、製品への関心を惹くことができます。
これにより、製品の販売を促進することができ、ビジネスをより成長させることが可能です。
YouTubeマーケティングを活用するコツ

YouTubeマーケティングはただ動画を投稿したら良いわけではなく、押さえるべきコツがあります。
具体的には、以下の3つのコツを押さえておく必要があります。
- 堅い動画ではなく楽しめる動画がよい
- SNSを併用して行う
- テーマ選びをきちんと行う事
堅い動画ではなく楽しめる動画が良い
YouTubeマーケティングでは、堅い動画よりも気軽に楽しめる動画の方が良いです。
気軽に見れる動画はユーザーの興味や感情を引きつけます。
たとえば、商品の特徴や機能をただ羅列するだけの動画よりも、商品を使って楽しく遊んだり、笑い話を交えたりする動画の方が魅力的です。
視聴者が楽しめる動画は好印象を与えるとともに、シェアやコメントなどの反応を促せます。これにより、動画の視聴回数やチャンネル登録者数を増やせます。
SNSを併用して行う
YouTubeマーケティングではSNSを併用して行うことが重要です。
SNSはYouTubeと相性が良く、動画の拡散やファンの獲得に役立つからです。
たとえば、YouTubeの動画をシェアしたり、動画に関する情報や裏話を投稿したりできます。
TwitterやFacebookでは、動画のリンクやサムネイルを貼って拡散することも可能です。
また、InstagramやTikTokでは、動画の一部分やメイキング映像を投稿して、視聴者YouTubeの本編に対しても興味を持たせることができます。
このように、SNSを併用することでYouTube以外のプラットフォームでもユーザーにアピールできます。
また、SNSでユーザーとコミュニケーションを取ることで、ファンとの関係性を深められるはずです。
テーマ選びをきちんと行う事
YouTubeマーケティングでは、テーマ選びをきちんと行うことが大切です。チャンネルとしてのテーマを設定し、視聴者へ何を伝えるかを明確にする必要があります。
テーマ選びでは、自社の商品やサービスに関連するものだけでなく、トレンドや季節なども考慮する必要があります。
たとえば、クリスマスやバレンタインなどのイベント時期には、それに合わせた商品やサービスの紹介、プレゼント企画などを行うと良いです。
また、テーマによって動画のバリエーションを増やすことで、視聴者の飽きを防げます。
中小企業のYouTube成功例4選

YouTubeマーケティングを成功させるためには、戦略的なアプローチが必要です。
以下は、中小企業がYouTubeマーケティングを活用して成功した4つの例です。
- 株式会社リンクロノヴァ
- 株式会社ダブルジェイシー
- 株式会社即決営業
- 日本コカ・コーラ株式会社
株式会社リンクロノヴァ
株式会社リンクロノヴァは、レシピサイト「macaroni」を運営するライフスタイルメディアです。
YouTubeチャンネルでは、簡単レシピやコンビニスイーツのレビューなどを配信しています。
ターゲットは「食から暮らしを豊かにする」ことを求める女性です。動画は清潔感のあるキッチンと爽やかなBGMで構成されています。
1日3本程度の動画をアップし、料理のバリエーションに悩む主婦層にアピールしています。
株式会社ダブルジェイシー
株式会社ダブルジェイシーは、アウトドアメディア「CAMP HACK」を運営する会社です。
YouTubeチャンネルでは、キャンプ初心者向けに格安キャンプ道具の紹介やキャンプテクニックの解説などを行っています。
動画には目次があり、視聴者は必要な情報を簡単に見つけることが可能です。
また、動画で紹介したキャンプ道具はWebメディアでも紹介され、商品を購入するためのリンクも提供されています。
株式会社即決営業
株式会社即決営業は、「日本初、授業をしない塾」として知られる武田塾を運営する会社です。
YouTubeチャンネルでは、「学びの手順」や「受験相談」といったコンテンツを提供しています。
このチャンネルでは単に授業を行うのではなく学習方法を教えるという画期的な方針を取っており、各動画は3分〜5分程度の短い時間で構成されているのです。
これにより、受験生が勉強の息抜きとして視聴できるようになっています。
日本コカ・コーラ株式会社
日本コカ・コーラ株式会社は、世界的に有名な飲料メーカーです。
YouTubeチャンネルでは、「コカ・コーラ」や「ファンタ」などの商品紹介だけでなく、「コカ・コーラ サウンドオブジャパン」という音楽プロジェクトや「ファンタ ファニーフェイス」という表情認識技術を使ったゲームなど、エンタメ性の高いコンテンツを展開しています。
視聴者に商品だけでなくブランドの魅力や価値観を伝えることで、ファンづくりに努めています。
中小企業でYouTubeを迷っている担当者はNOGICまで!

YouTubeマーケティングは、中小企業でも手軽に始められるマーケティング手法です。
自社の商品やサービスを紹介するだけでなく、視聴者が楽しめる動画を配信することで視聴者との関係を築き、ブランドの認知度を高められます。
しかし、中には、「YouTubeチャンネルの立ち上げ方がわからない」「自社でYouTubeを始めても成功しないのではないか」と不安に思う中小企業も多いです。
NOGICでは、「YouTubeチャンネル立ち上げ成功判断」や「YouTube無料診断」などを行なっております。
YouTubeを始めるべきかを悩んでいる企業の担当者は、ぜひNOGICにご相談ください。
一度プロの目からYouTubeを進めるべきかの評価を受けることで、安心してYouTubeの施策に取り組むことができるようになります。

